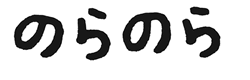 |
| 農文協 > 食農教育 > 2006年3月号 > |
|
|
食農教育 No.46 2006年3月号より
農高って、どんなところ?
農高は命・地域の学びを切り拓く宝の山だ
農文協教科書編集部
「ヤギ草刈り隊」って何? ―農高生たちの挑戦
「ヤギ草刈り隊ボランティア」、これは昨年行なわれ、二万八千点を超える応募があった「第15回地球にやさしい作文・活動報告コンテスト」(読売新聞社主催、文部科学省、環境省など後援)の「作文・活動報告部門〈高校生の部〉」で文部科学大臣賞を受賞した農高生の作品のタイトルである。この活動には、農高とそこでの学習活動の特色が端的に現われている。
中国山地の中央部に位置する農高(広島県立庄原実業高校)の生徒たちは、高齢化などによって農地や畦畔などの草刈りが困難になってきているなかで、学校で飼育しているヤギを活用した地域の草刈り(ヤギの採食による除草)に取り組み、地域の人びとや子どもたちとの交流を深めていく活動を開始したのである。ヤギに着目したのは、ヤギはどんな草でもきれいに食べてくれる草食動物で糞の量も少なく環境にやさしいこと、ヤギはかわいらしく高齢者や子どもでも扱いやすい中家畜であること、などの理由からである。
実際の「ヤギ草狩り隊」の活動は、農家の草刈り予定地の調査から開始し、その結果をもとに活動に参加する生徒の人数や場所にあった草刈り方法を検討し、遊休水田ではヤギを有効利用するために電気牧柵を張ってからヤギを放牧するといった工夫もしている。そこでは、日々の農業学習や実験・実習などのなかで学んだ課題解決に向けた活動の進め方、家畜の生理・生態についての知識や飼育技術などが生かされ、「自然のまま」ではなく「農の営み」によってが環境が守られることが鮮明にされており、地域の未来を拓く農高ならではの活動と言える。
こうした地域と連携した取組みは、農村部だけでなく都市部も含めて全国各地の農高で広範に取り組まれており、前述のコンテスト〈高校生の部〉で、優秀賞・入賞七点のうち四点を農高生が占めていることも、その取組みの広がりと内容の充実ぶりの一端を示している。
地域の文化圏ごとに存在する約四〇〇の農高
現在、こうした命(いのち)輝く農高は全国にどれくらいあるかと言えば、約四〇〇校である。そのなかには、○○農業高校や△△園芸高校といった農業の単独校だけでなく、農業に関する学科やコースなどを設置している総合制高校や農業関連の系列を設置する総合学科の高校なども少なくない。地域に密着したユニークな教育活動を展開している分校や、多様な教育課程を編成している定時制・通信制の学校も各地にみられる。
それらは、高校全体(五四一八校)からみれば、一割にも満たないが、その立地には注目すべき点がある。北は北海道の宗谷岬近くから、南は沖縄の西之表島にまで及び、しかも、それぞれの農高は、自然や産業、文化などに共通性を有する各地の文化圏ごとに立地している(図1)。それは、わが国の多様な地域の産業や文化、教育などの原型が形づくられた江戸時代の三百諸藩の分布と重なる場合も多く興味深いものがある。
また、農高の沿革をみると、郡立や町村立としてあるいはいくつかの近隣町村が協同して設立された学校も少なくない(北海道の農高は、現在も九校が町村立である)。つまり、多くの農高は地域の高校として生まれ、地域に育てられ、地域社会を担う人材を輩出してきたのである。一方、近年では、地域や都道府県を越えて生徒の集まる農高もみられるようになっており、学校や地域の新たな活力の源ともなっている。
 生徒自身が作物を育てながら発見する農高での学び(「農業基礎」〈「農業科学基礎」〉での栽培プロジェクト)
生徒自身が作物を育てながら発見する農高での学び(「農業基礎」〈「農業科学基礎」〉での栽培プロジェクト)農高再生、「総合的な学習の時間」の道を拓いた学びの転換
とは言え、地域の高校としての農高の足どりは、必ずしも平坦なものではなかった。たとえば、昭和三十年代の食料増産の時代には、地域と一体となって農業技術の改善や新技術開発などに積極的に取り組み、まさに地域のセンターとしての役割を果たしてきた。しかし、昭和四十年代には減反政策の影響や農高における自営者の激減、生徒の学力低下など、農高を取り巻く状況は非常に厳しくなり、地域とのつながりも弱くなった。
そうしたなかで、農高を再生させていく一つの画期になったのは、昭和五十年代年に本格的化した科目「農業基礎」(現在の「農業科学基礎」「環境科学基礎」)の取組みであった。そこでは、「教師が知識や技術を教え込む」指導から、「生徒が作物や家畜を育てながら生徒自身による知的学習の向上を図る」指導への転換がなされ、プロジェクト学習の見直しも行なわれた(図2)。つまり、そこでは「作物や家畜が先生」であり、教師の重要な仕事は生徒の学習活動を支援・援助、コーディネートすることであった。当時、農高の先生方は次のような指摘をされている。
「あまりに整理されすぎた研究成果、完璧なまでに体系化された理論は、それ自体真実をふり落としていることもある。その体系を背負って教師が生徒の前に立つと、生徒は農業が嫌いになること必定である。なぜならば生徒が自分で作物や家畜の真実に触れることができないからである。私は、本当は何もわかっていないんだ、お前らとことん調べてみろ、という導入に始まる体験学習で一貫させたい」
(『農業教育16号』昭和五十三年発行)「生徒に作物・家畜を育てさせ、それらを自主的に探究させると、必ず生徒なりの認識(感動)が生じ、その認識にそって作物・家畜に働きかける。そして、その認識と働きかけの適否を作物・家畜の変化のうちに見出そうとする。そこで、自分の認識とはたらきの正しさが検証できたり、あるいはそれらの一面性を悟って修正したりするとき、生徒は自ら学習したという実感をもつようになる。農業は、さまざまな要因が複雑にからみ合って成り立っており、育てながら学ぶことは、農業の複雑なしくみのなぞを解いていくこと、自然と人間のかかわりあいのありかたを追求することであり、探求はつきないものである。これは知識を覚え込まされる一般普通教育よりもすぐれて知的な学習である」
(『農業基礎教師用指導書』昭和五十七年発行)こうした先生方の実感は、生きもの(命)や農業のもつ教育力の現代的意味を確信させるものであり、系統学習か体験学習かといった議論を超えて、教育現場の活性化へとつながっていく。「農業基礎」を起点とするプロジェクト学習は、二、三年次の本格的な課題解決学習や地域と連携した多面的な探究活動へも発展していった。そして、こうした学びは、生徒自身が課題を設定して、調査・研究や作品製作などに取り組む科目「課題研究」へと発展的に継承され、さらには「農業基礎」や「課題研究」の取組みや成果が、「総合的な学習の時間」(「総合学習」)への道を拓いたと言っても過言ではない。
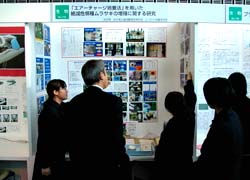 日本学生科学賞(最終審査)で自分たちの研究(地域の伝統的な作物の増殖)を発表する農高生(最終審査には全国から16研究が参加)
日本学生科学賞(最終審査)で自分たちの研究(地域の伝統的な作物の増殖)を発表する農高生(最終審査には全国から16研究が参加)地域と連携した自分たちの研究で自信をつける
農高の地域課題に着目し地域と連携した学習活動の成果は、学校農業クラブ活動(教科学習の一環)の「プロジェクト発表」をはじめとして、さまざまな機会に積極的に発表して、各方面から高く評価されている。
たとえば、「高校生の研究活動の甲子園」とも言える「日本学生科学賞(研究部門)」や「高校生科学技術チャレンジ(JSEC)」などにも、毎年のように出場して、生徒たちは大きな自信をつけている(図3)。
沖縄県の宮古農林高校の生徒たちは、地域の地下水(命の源)の水質汚染を防ぐために地域未利用資源を活用した有機質資材の開発と普及に取り組み、「ストックホルム青少年水大賞」(「水のノーベル賞」と言われる「ストックホルム水大賞」のジュニア版)においてアジアで初めて大賞を受賞している(本誌二〇〇四年十一月号参照)。
近年では、こうした挑戦を通し、「受験勉強ではなく自分たちの研究」をして大学に進学する生徒も少なくない。
「教えて学ぶ」ことで命・地域の教育力を高める
農高では「作物や家畜、地域に学ぶ」という学び方に加え、農高生が地域の小中学生や社会人などに「教えることで学びを深める」という学び方も創造し、多くの農高で取り組まれるようになっている。こうした学びの創造は、昭和六十年前後に各地で開始され、幼保・小中学校との交流活動(農業体験の受入れなど)、移動動物園(出前授業)、学校開放講座、学校農場を活用した市民農園など、じつに多彩な挑戦が行なわれた。それらは、生徒減少期を迎え高校再編が急速に進むなかで、農高のPRや地域へのサービスのために先生方が中心になって企画・運営していた場合も少なくなかったが、それを生徒たちに取り組ませると、生徒は人に教えるためにこれまで学んだことを理解し直したり、人に伝わりやすくするために表現方法を工夫したりするなど、学びそのものを深めることができ、生徒の自信につながるのである。
 「グリーンライフ」などの授業で地域に残る農家蔵と蔵のある景観をガイドする農高生
「グリーンライフ」などの授業で地域に残る農家蔵と蔵のある景観をガイドする農高生そうした取組みは、従来は教科学習とは別に行なわれることも多かったが、新学習指導要領では農業教育の一分野としてヒューマンサービス分野が創設され、科目「グリーンライフ」(おもに農業・農村の機能や多様な地域資源の発見・活用法、グリーン・ツーリズムなどの都市農村交流について学ぶ、図4)、「生物活用」(おもに園芸作物や社会動物などの農業生物の特性を生かした対人サービス〈園芸・動物セラピー〉について学ぶ)が新設され、教科学習のなかに位置づけられた。そのことによって、農高はさらにダイナミックに進化している。
その第一は、授業のなかで生徒が校外や地域に出かけたり、多様な人びとが学校にやって来たりするようになったことである。その対象も幼保・小中学校はもとより、養護学校、福祉施設、地域のNPO、企業などへと広がっている。また、教材として扱う生きものや題材も、従来の主要作物や産業動物だけでなく、地域の伝統的な作物や在来品種、イヌなどの社会動物、さらには地域の野生動植物や希少動植物、伝統的な建物や景観、生業(炭焼き、紙漉き、養蜂など)などへと広がっている。それらを教材とした学び方も工夫され、交流授業をはじめとして、ワークショップ、地域ガイド、起業体験、社会参加(地域への政策提案)なども登場してきている。
その豊饒さは、これまで日本の学校には存在しなかった、とも言えるものであり、ある面ではとまどいを覚えるほどかもしれないが、挑戦を続ける農高は、それぞれの地域に根をおろして現存している宝の山である。
長野県の農高で数々の挑戦を続けてこられた永田栄一先生は著書『農業高校ってすごい―学校教育への挑戦―』(平成六年発行)の中で次のように述べている。
「野菜も人間も、かってに生き、育ってはいく。しかし、必ず収穫が約束されているわけではない。命とのかかわりは、誰もが日常的に接する世界でありながら、誰もがうまくいくわけではないし、教えて教えられる世界ではない。育てることの楽しさは、体験や観察の中や、決断の苦しさの中から生まれる世界でもある。知識や効率だけの価値観では計りきれない、歴史や文化、気象や生態・生理など多面的総合的な見方が、そして『結果の言い訳ができない』のが『命』や『生きもの』の世界とも思える。」
「効率がわるくても、芽が出るのを待ったり、食べるために殺す場面で生きている自分が嫌になったりすることがあっても、皆が同じことを考え、同じ結果を求める世界(教育)よりは正常な気がする。そしてわが国で『命の学校』、『現実を生き抜く力を身に付ける学校』としての学校教育の世界を追求し続けてきたのが農高ではなかっただろうか。」
農高に限らず、生きものや地域を題材としそれらと深くあるいは多面的に関われば、一つとして同じ考えや結果は生まれてこないといっても過言ではない。その意味では、「総合的な学習の時間」をはじめとする生きものや地域を題材とした小中学校の学習においても、それぞれの地域の農業高校と連携・協働することで、その地域―文化圏ならではの教育を創っていくことが可能だし、そこには大きな教育力が埋もれているにちがいない。
※本稿に関連する農文協発行の資料としては、雑誌『自然と人間を結ぶ 農業教育』(五・十一月発行、四〇〇〜六〇〇円)、単行本『農業高校ってすごい』(一九〇〇円)、高校教科書『農業科学基礎』(一一三〇円)、『グリーンライフ』(八九五円)、『野菜』(九一〇円)、『畜産』(一五三〇円)などがある。

農文協 > 食農教育 > 2006年3月号 >
お問い合わせはrural@mail.ruralnet.or.jp まで
事務局:社団法人 農山漁村文化協会
〒107-8668 東京都港区赤坂7-6-12005 Rural Culture Association (c)
All Rights Reserved