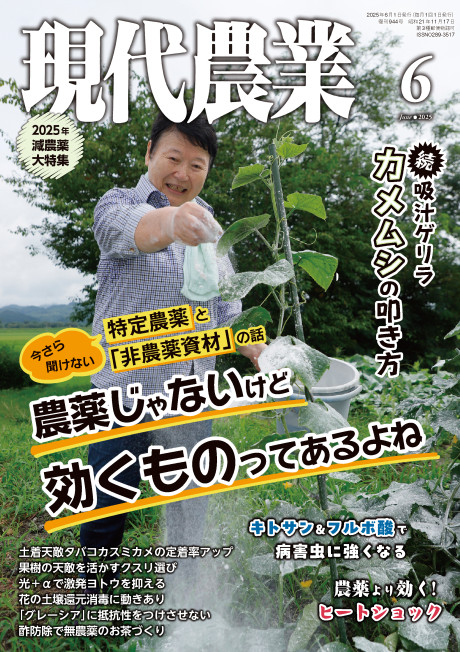主張
百姓国の今を、知りたい人と伝えたい人
目次
◆消費者のママ立ち上がる
◆JA青壮年部から、地元に根差す2人の農家
◆百姓国との距離を少しずつ埋める
◆耕作放棄地は絶望ではない
◆長靴の百姓とスーツの百姓
◆未来にタネをまく
映画『百姓の百の声』のことは、当「主張」欄でも何度か紹介したことがあるが、その後もずっと各地で自主上映会が続いている。農家の世界(映画では「百姓国」と表現)を消費者に届ける役割を持つ映画で、農文協も撮影・制作に全面協力。草の根で次々広がる自主上映会活動も応援している。今回は、3月8日に岡山市で開催された上映会の様子を報告したい。岡山では、県内他地域でこれまで何度か上映の機会があったのだが、県庁所在地・岡山市内での開催は初めてだった。
消費者のママ立ち上がる
「毎日あたりまえに口にする『食べ物』、それを支える農業の現実やその未来を一緒に考える時間を作りませんか?」――こんなチラシの誘い文句で、岡山市東区百花プラザでの上映会に、消費者・生産者およそ260人が集まった。主催は「岡山まごころ給食審議会」。持続可能な地域づくりと地元米の学校給食を推進する子育て中のママたちだ。
ママたちが活動の拠点にしている岡山市は、政令指定都市でありながら、米収穫量が全国約1700の市町村中16位と、じつは結構な米産地。おかげでまわりにたくさん田んぼはある。しかし実際にそこでどんな農業が営まれているのかは、じつはまるでわかっていない。そこでまずは自分たちの農の理解を深めようと、ママたちは2023年から無農薬・無化学肥料の稲作を始めた。もちろん農家に助けてもらいながらの作業だが、収穫した米やワラで、こうじ調味料や納豆作りのワークショップも開催してきた。
代表の荘司かおりさんは、岡山市内の新興住宅地で小学2年生の子どもを育てる一児の母だ。もともとは県内総社市の出身で、子どもの頃は家に田んぼがあり、田植えやイネ刈りを手伝った原体験が強く残っている。1年半前、備前市で開かれた自主上映会で初めて『百姓の百の声』を観たときに、「ストレートに映画に感動した。農業を守りたい。生産者でなくても、私たち一人ひとりにできることはきっとあるはず」という気持ちが芽生えたという。「この映画をどうしても市内の多くの人に観てもらいたい。できれば子育て中の親に観てもらって、毎日当たり前に口にする食べ物の現状を一緒に考えてもらいたい。映画の後にはディスカッションの時間も持ちたい」と、荘司さんは「岡山まごころ給食審議会」有志のママたちと今回の上映会を企画。生協や財団などからの助成、県や市、教育委員会らの後援も取得し、チラシ1万8000枚を印刷すると、親世代に届くよう、学校の子ども達を介して広く配布した。
JA青壮年部から、地元に根差す2人の農家
上映後のパネルディスカッションには農家と消費者を2人ずつ呼ぼうということになった。だが会では消費者のパネラー以外は見当がつかないということで、パネルディスカッションの進行役や農家の登壇者は農文協から紹介することになった。
そこで進行役は、岡山大学・松村圭一郎先生にお願いした。松村さんは、2年前にいち早く真庭市で開催された上映会でこの映画を観て、「百姓国は唯一戦争を起こさない国だ。だから国家もその強さを恐れているはず」というコメントを残してくれた先生だ。
農家の登壇者は、やはり市内の子育て世代がいいかなと考え、JA青壮年部のメンバーにお願いした。一人は非農家から新規就農し、米麦露地野菜を生産している一所懸命農園の岩本英隆さん(50歳)。もう一人も同じく非農家からの新規就農者で、ブドウ狩りやイチゴ狩りの観光農園と直売所を大規模に経営しながら、最近は古民家カフェも始めた岡山フルーツ農園代表の高原弘雅さん(42歳)。この2人、予想外に、なかなかの役者だった......。
百姓国との距離を少しずつ埋める
まず、進行役の松村さんから映画の印象を問われた岩本さんは、「就農してもう20年たちましたんで、我々もどっぷり百姓国のほうの人間になっていてですね。映画を観てて『もう、そうそうその通りなんじゃ』ということばっかりでした」。
驚いた松村さんが、「私ら消費者から見ると、えっこんなことが......とか、そういう考え方するんだーって結構発見が多かったんですけど、生産者から見ると『うん、知ってる』みたいな感じだったんですか?」と聞くと、今度は高原さんが、「そうですね。『百姓国』っていう、日本にいながらもちょっと違う、近いけどわかりづらい国って設定になってるのもまさにそういうことで、やっぱりここに通訳が必要ってことが今日のテーマかと思います」と答えた。
農家には「日常の当たり前」が、消費者には異国の出来事。離れてしまったその距離をお互いに少しずつ埋める......。そのための映画だし、そのためのディスカッションだったのだとたしかに思う。
話題は消費者パネラー・久本絵里さんの家周囲の耕作放棄地から展開していった。農家の高齢化が進み、手つかずの田んぼに太い木が生えてきて、心を痛めているという。
耕作放棄地は絶望ではない
岩本さんは映画に出てくる横田農場と同じように、周辺の農家ができなくなった農地を引き受けていくうちに67haまでの規模になってしまったという。松村さんが「映画の中では、ある程度大きいほうが生産性はいいけど、際限なくいいわけじゃない、みたいな話がありましたが、その辺はどうですか?」と聞くと、「もうその通り。たとえば1人でできる面積がこのくらいとしたら、それを超えると機械がいるし、また人もいります。するとそのためにお金がいるんで利益がなくなります」。
そう言いながらも岩本さんは、「今、圃場のあるところは、どんなに小さい条件の悪い田だろうが、どんなに面積増えようが、それは受けて、地域を守るというのは、やっていこうと思っています」と話してくれた。
果樹農家の高原さんは、岡山の本業のブドウ農家の栽培面積は、50年前から1軒あたり50aでずっと変わらないという。米と違って、できなくなった人の園地を引き受けて規模拡大する人はあまりおらず、農家数が減った分の果樹園は、荒れて山に戻っているのが大半だそうだ。
だがそんななか、高原さんは耕作放棄の段々の田んぼをなだらかな傾斜地に戻し、果樹園として活用していると話した。「耕作放棄地は、じつは田んぼの状態のままだから耕作放棄されてるってこともあるんですよ。水が入りにくかったり、コンバインが行って帰ったら終わり、みたいな段々の棚田は、アゼ草管理だってコストが高くて大変。でもそういう段々をつなげて畑に戻して、たとえば牧草地にする。輸入飼料が高騰して大変な畜産農家がそこで牧草をつくれば耕作放棄地にならない。アプローチを変えれば解決策はあるよ、という明るいニュースです」
そういうやり方で、どんと切り拓いただだっ広い果樹園で、高原さんはレーズン用や果汁原料用のブドウを手をかけずに栽培する。岡山のブドウ農家の面積が50a以上に増えない理由は、高級なものをつくるために手数をかけるから。アプローチを変えると、意外と「身近に買えて国産でおいしい果物」も見えてくる、というのが高原さんの考えで、「耕作放棄地は絶望ではない」という話をしてくれた。
長靴の百姓とスーツの百姓
「ところでちょっといいですか?」と2人がおもむろに立ち上がった。作業着に長靴姿の岩本さんと、スーツを着こなした経営者風の高原さん。「僕たち今日はドレスコードを決めてきたんです」。じつは2人で相談して、正反対の服装で登壇したのだという。
ザ・百姓の出で立ちの岩本さんが「僕はいつも通りの格好で来させてもらいました。そうですね、寝る時もこの格好です」と笑いをとったあと、スーツの高原さんが語った。「今、百姓国の人たちって、ふるいにかけられているんですよ。百姓を選び抜く人と、農業経営者になる人に。僕らもものすごくふるいにかけられていて、今日はそのあたりを話のヒントにしてもらったら、ということです。僕もマインドは百姓国の人間なんですが、今日は経営者の格好してこいって、岩本さんに指示されまして(笑)」
これには消費者パネラーの久本さんが思わず、「すみません。ふるいをかけられるっていうのは、つまりどういうことなんですかね? 選択を迫られるってことなんですか?」と口を挟んだ。
「えっとこれは......、つまりビジネスに乗るのか乗らないのかということで、国の施策でも、要は担い手っていうのがかなり優遇されてるんです。その担い手の中でも規模をどんどん広げてくれるか現状維持かで差がつけられてきてて、そういうふるいなんです。だからもう中堅がない。小か大かどっちかにって施策で、大を優遇するようになっているので、若い人は規模をやる人が多いのが現状。本当は小と大、どっちが正しいということは全然ないです」
そういう高原さんは企業体として生き抜く道を選んでやってきており、従業員も40人雇用。家族農業的な「農家」のイメージではない経営だが、百姓国のマインドは共通して持っている。ディスカッション後半、「消費者は今後何をしていったらいいか?」という質問が出た際、「ちっちゃい農家が減って、大きい農家が地域で生まれてくるこの時代に、なんで僕が直売所を作ったかっていうと、声を上げたくても上げられん人の代わりに販売したいから。それが地域の直売所ということ。百姓国に近づきたかったら、地産地消マルシェとか農業関係のイベントにぜひ足を運んでほしい。架け橋となる場所は必ずあるし、そうやっているうちに通訳の声も聞こえてくるんで」と答えた。
今の時代を生きる若い農家の等身大の言葉を聞いた気がした。
未来にタネをまく
じつは映画『百姓の百の声』の柴田昌平監督が、続編『未来にタネをまく』を制作中だ。レジェンドたちが多く登場した1作目とは変わって、登場するのは岩本さんや高原さんらの世代の若い農家だそうだ。公開は2026年度予定で、現在サポーターを募集している。
次作の完成を待ちながらも、消費者が農業を自分事としてとらえ、向き合えるための場づくりには、農文協もスピードをあげて取り組まなければいけないと思っている。
(農文協論説委員会)