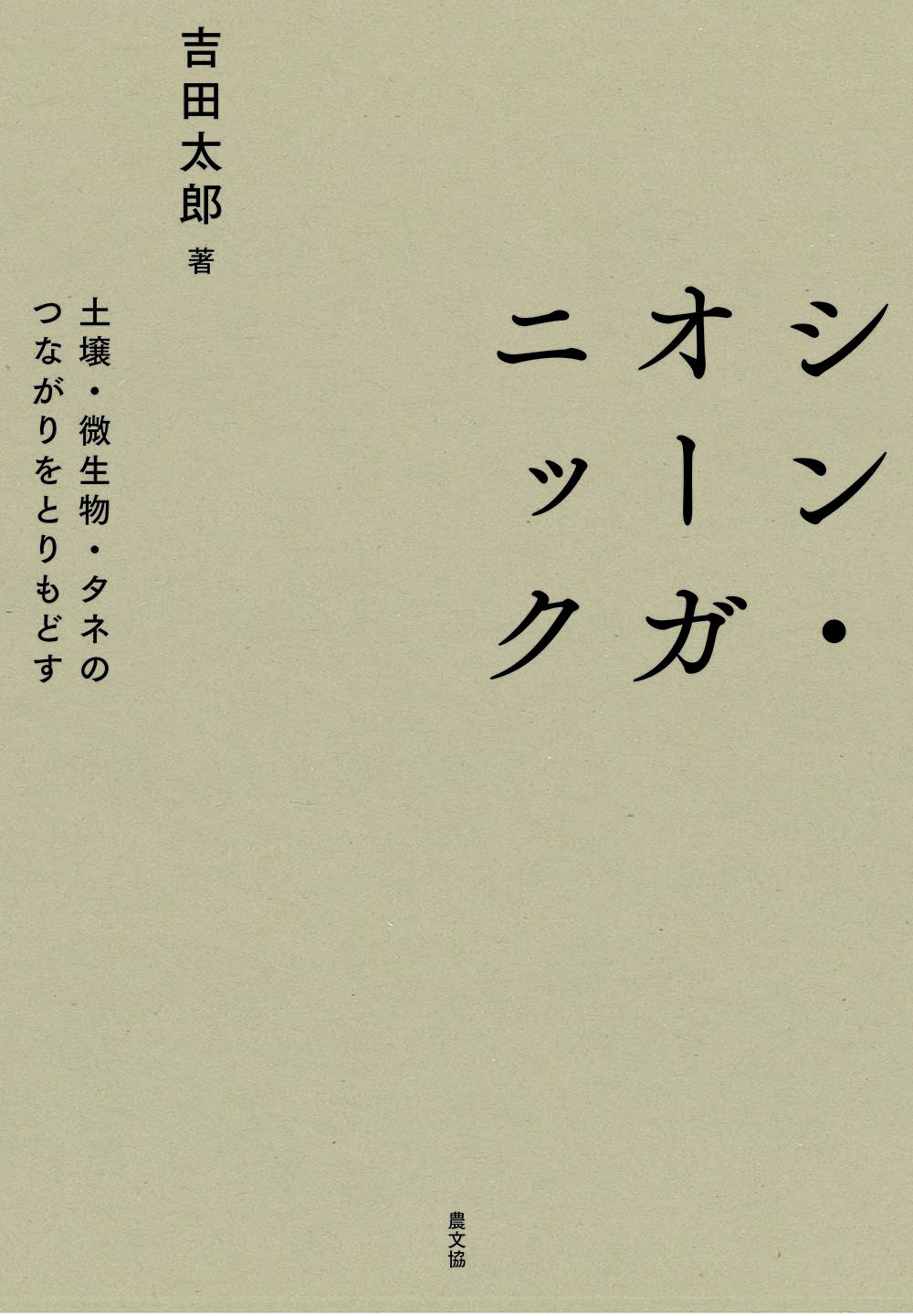主張
なぜ「自然に学び、模倣する」ことが大事なのか
目次
◆食と農をめぐる難題
◆原初の土とは? 菌根菌の誕生とは?
◆健康な植物だと害虫は飢える 有機物の分解と腐植の合成
◆タネの中には微生物群が棲んでいて、次世代へ受け継がれる
◆完熟堆肥は土の中、未熟堆肥は土の上
◆自然はレジリアンスに満ちている
先日都内で「全国オーガニック給食協議会」の年次総会が開かれた。参加者は全国から約130名。会員自治体による取り組み報告のなかで、有機給食に取り組んだきっかけについて長野県松川町の北沢秀公町長は「有機給食で育った子どもたちは将来まちを出ても、その味を思い出して帰ろうと思ってくれるのでは」、茨城県常陸大宮市の鈴木定幸市長は「子どもたちによい未来を残したい」からと言う。
みどりの食料システム戦略でのオーガニックビレッジ構想の後押しもあり、各地で有機農業への取り組みがすすんでいる。有機給食の広がりもその延長線上にある。
しかし「無化学肥料、無農薬、ほんとうにできるの?」という疑問は根強い。その疑問に答える本が、今夏出版される。
食と農をめぐる難題
書名は『シン・オーガニック――土壌・微生物・タネのつながりをとりもどす』。著者は有機農業関連の著作で知られるフリージャーナリストの吉田太郎氏だ。
世界の食料需給の逼迫が懸念される一方で、カーボンゼロや生物多様性の保全を達成しなければならない。さらにカリやリンも有限で、ウクライナ危機もあって価格も高騰している。「地球沸騰」を回避し、同時に世界飢餓も防ぐという難題を、同時に解決しなくてはならない――これが食と農をめぐる現代的な状況だ。
こうした前提については世界的にコンセンサスが得られている。しかしそれを実現する手法となると、まさに百花繚乱だ。AIやドローン、人工肉や細胞培養等の先端技術のフードテックがもてはやされる一方で、有機農業や自然農法、リジェネラティブ農業などの広がりがある。
本書が探っていくのは、「農民の主体性を伸ばしながら、ローカルな解決策を目指す方向」だ。そしてそのためには「生産の仕組みを土に重点をおいて、なぜ自然に学び、模倣することが重要なのかを原理から紐解いていくこと」が重要なのだという。
原初の土とは? 菌根菌の誕生とは?
本書の第Ⅰ部は「地球史からみた植物と土とのつながり」である。「地球史」などと言うとなんと大袈裟な……と思われるかもしれない。しかし農業に寄与する微生物は、生命の誕生・進化と深くかかわる。農業には土と微生物が大事―ならば、土がどのようにしてできたのか、そこに微生物がどのように関わったのかを知ることは欠かせないはずだ。30億年以上前に遡ることが可能な地球生命史から考えれば、人間は超新参者である。だからこそ、自然に学び模倣することが重要なのだと言ってもよい。
6億年ほど前、原初の土はシアノバクテリアと菌類の共生体「地衣類」によってつくりだされた。地衣類は有機酸を分泌することで岩石を溶かし、生存に必要なリン、カルシウム、カリウム等の養分を獲得していた。地衣類は収縮と膨張を繰り返し岩石を砕く。この地衣類の遺骸と砂や粘土が混ざり合ったものが地球上に現われた最初の土だ。
農業との関係で重要な微生物のひとつが「菌根菌」だ。菌根菌の誕生は植物が上陸した4億年前より古い。菌根菌は植物が自前の根を進化させるまでの数千万年間、植物の根の役割を果たしてきた。根ができた後もこの関係は今日に至るまで延々と続いている。ところが土にチッソやリンが豊富にあると、菌根菌と植物の協働は止まってしまう。それは、養分が少ない時代から菌根菌は植物と共に生きてきた微生物だからなのである。
健康な植物だと害虫は飢える 有機物の分解と腐植の合成
本書の特徴は、日本・海外問わず、すぐれた研究を収集・検討し、生きものたちの実相=生きざまに迫っていることだ。何人かを紹介してみる。
作物は体内での養分代謝が乱れているときに病害虫の被害を受けるとの「栄養好転説(Trophobiosis Theory)」を提唱したのは、フランス国立農業研究所のフランシス・シャブスー(1908~1985)。「Trophobiosis」とは、「トロフィコス(栄養)」と「ビオシス(生命)」という二つのギリシャ語に由来する言葉だが、「害虫は健康な植物では飢える…。毒(農薬)は使えば使うほど、病害虫が増える」「どの植物も病害虫にやられるわけではない。健康な植物は病害虫には侵されない。害虫が必要とする養分、すなわち、アミノ酸が体内にあるものだけが被害を受ける」とシャブスーは述べた。
作物の養分代謝が乱れると可溶性化合物が蓄積され、それが病害虫のエサになるが、「健康な」作物ではデンプンやタンパク質へと合成がすすむ。だから健康な作物では害虫は飢える、のである。
健康とは調和がとれている状態であって、その調和が破れたときに不健康となると考えたのは、ドイツの有機農家で土壌学者のエアハルト・ヘニッヒ(1906~1998)。ヘニッヒは、土壌は分解層に属する「細胞熟土」と合成層(構築層)に属する「プラズマ熟土」という二層構造から成り立っていて、上層の分解層では分解が主であるが、この下の合成層では、微生物の分解の影響を受けにくい腐植へと合成されているとも述べている。
そして、排水処理に取り組むなかで土壌がどのようにしてできるのかに気づいた地質学者の内水護(1934~2005)。内水は、有機物の分解では反応が進むにしたがって分子量が低下していくのに対して、土壌(腐植)の形成においては有機物の分子量が増えていくことから、両者はまったく異なる反応であると指摘した。
微生物は植物の根から滲出液を受け取り、その見返りとして土中の養分やミネラルを植物に引き渡すが、肥料を与えれば働かなくなるというオーストラリアの土壌学者、クリスティン・ジョーンズの発言も刺激的だ。酸素が乏しい状態で分解が進む発酵や、同じく酸素が乏しいミミズの腸内でつくられるミミズの液肥といった、低酸素状態での化学反応の重要性もジョーンズは指摘している。
いずれの研究者の発言も示唆に富んでいるが、それは、これら碩学たちが自然のありようを丸ごととらえ、そこから農のあり方を再考しているからだと言ってよいだろう。
タネの中には微生物群が棲んでいて、次世代へ受け継がれる
近年「タネ」への関心が高まっている。しかしその多くは「タネは誰のものか」といったいわゆる権利論からの見方である。本書はタネを微生物との関係からとらえようとするのが特徴だ。
タネの中には多数の微生物が棲息し、その微生物のDNAが作物の生育に大きな影響を及ぼしている。植物は親から遺伝子を取得するが、同時に、タネを介してマイクロバイオーム(微生物コミュニティ)をも受け継ぐ。タネには、植物種を決定するDNAだけでなく、植物の一生を通じて共生するマイクロバイオームも含まれているのだ。こうしたことが、ゲノム解析技術の進歩でわかってきた。
植物を健康にする微生物は土壌からタネを介して親から子へと継承されていて、そうした健全な植物を食べる動物も健康となる。東洋医学でいう「医食同源」や「身土不二」の科学的な根拠が明らかにされつつあるのだ。
著者の吉田氏は、有機農業が盛んな埼玉県小川町の金子
完熟堆肥は土の中、未熟堆肥は土の上
日本の有機農業運動の展開を語るうえで欠かすことのできない人物の一人が奈良県の医師、
「私はしゃがんで落葉を掴んでみた。腐植した小枝や白い菌糸がでてきた。その時、パッと私の心に閃いたことがある。この時、私は、無農薬有機農法解決の端緒を得たのである。……中略……今まで私は生の有機質を土の中へ埋めていた。それでは空気が十分通わない。すなわち、腐敗が起こり、植物の生命力を弱らせる。だから病害虫が発生するのだ。篤農家が教えてくれた『土から出たものは土へ返せ』は一言足りなかったのだ」
「『土から出たものは土にしてから土に返せ』だ。『完熟堆肥は土の中、未熟堆肥は土の上』。大声で叫びたいような衝動に駆られて、私は香ばしい大気を深く深く吸い込んだ。緑の木々は讃歌をうたって祝福してくれるようだった」
一樂も次のように述べている。
「有機物は土壌中の腐植質となって微生物の繁殖を盛んにするとともに土壌を団粒化し、通気や保水をよくし、作物のための物理的条件を向上させ地力を培養する。土壌中の腐植質の増加に応じて微生物や昆虫が繁殖する。ミミズ自身が土地改良をして沃土を造成する。クモは偉大な天敵であって、害虫駆除に最もよく貢献する。そこで、有機農業は、ミミズやクモを重視する農業であると表現することもできる」
自然はレジリアンスに満ちている
本書の副題は「土壌・微生物・タネのつながりをとりもどす」である。それは「土壌」「微生物」「タネ」の三者をばらばらにとらえるのでなく、本来その三者がもっていたつながりが取りもどされるとき、無化学肥料・無農薬栽培も可能になるのではないかと述べているのだ。
本書は最後に「レジリアンス」について論じている。ここでレジリアンスとは「しなやかな復元力」を意味する。農家の暮らしも本来このレジリアンス志向であったはずだ。自然は、そして生きものたちの共生する様は、まさにレジリアンスに満ちている。「自然に学び、模倣する」ことで、「食と農をめぐる難題」の解決の糸口に近づける。
(農文協論説委員会)
- 以下のリンクから、記事の本文を読み上げる音声配信サービスにつながります。
 現代農業VOICE(YouTubeに移動します)
現代農業VOICE(YouTubeに移動します)
【主張】なぜ「自然に学び、模倣する」ことが大事なのか【現代農業VOICE】