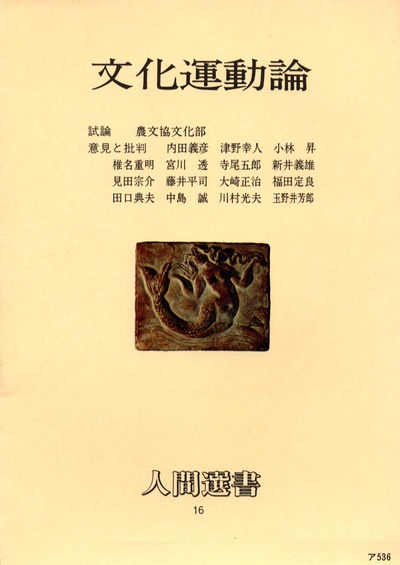主張
農家・農村の〝主体形成〞とともに
『現代農業』創刊100年にあたって(上)
目次
◆大正期は、農家・農村にとってどんな時代だったか
◆小作争議と農家小組合という二つの小農運動
◆「むらと結合した協同組合」から新生農協へ
◆集落営農の原点 農家小組合
◆農文協の再建 自主自立と直接普及方式
1940年に設立された農文協は一昨年・2020年3月に創立80周年を迎えたが、農文協の基幹雑誌である『現代農業』の前身の誕生は、さらに20年さかのぼって100年前。大正11年(1922年)3月創刊の『
この二つの雑誌が誕生した大正期は、日本の資本主義、近代工業と近代都市の形成が本格的に進展し、農村から都市への「向都熱」が高まる一方、繁栄から置き去りにされた農村をめぐる「農村問題」が最大の社会問題として浮上し、小作争議など農村が動いた時代であった。
それ以降今日まで、統制経済の戦時は別として、農家・農村は資本主義・市場経済の浸透や近代化の波にさらされ、そして戦後の高度経済成長期には、小さい農家の脱農と企業的農業の育成をめざす構造改革農政、近代化路線が進められた。しかし、構造改革は国が目論んだようには進まず、小農家族農業もむらも生き続け、『現代農業』もそんな農家、地域とともに生きてきた。そこには、それを可能とする〝主体形成〞があったのだろう。
そんな主体形成のエポックを、今号次号の2回に分けてたどり、これから100年への糧にしたいと思う。
大正期は、農家・農村にとってどんな時代だったか
農業青年のための『清明心』、小作争議など農政課題を議論する『農政研究』。この二つの雑誌の発行経緯や内容については240ページからの記事をご覧いただくとして、ここではこれらの雑誌が生まれた大正期はどんな時代だったか。農家・農村(いえとむら)の主体形成の側から近現代史を研究してきた野田公夫さん(京都大学名誉教授)の著書『日本農業の発展論理』(農文協刊)の指摘をもとに見てみよう。
野田さんによると、「農村問題」が浮上した大正時代は、近現代日本において農業・農村現場が最も自己主張しえた時期であり、多様な農村社会運動が巻き起こり、それらを農村振興へと結実させる努力が重ねられた時代だった。野田さんは「問題を当事者として引き受ける自覚をもった人々」、そして彼らの影響を受け広い意味での「運動」に参加した人々を「主体」としている。『清明心』誕生の背景には、そんな主体形成をめざす農業青年がいた。
当時の農業青年たちの状況について野田さんはこう述べている。「次三男や娘たちがこぞって都会へ流出するという事態(向都熱)は、残された長男(後継者)に独特の心性をもたらした。家督相続者という特権的身分を誇れたかつてとは違い、今や次三男や姉妹たちのほうがしばしば都会の富や刺激を享受できる『恵まれた』存在になったからである。当事の長男(後継者)たちはその複雑な思いを農業と家・ムラの改革に向けた」
『清明心』はそんな、自らの生き方を模索し、農村生活の改善・向上を実現しようという、理想に燃えた青年たちの雑誌だった。
『農政研究』もまた、大正期の農村社会運動を背景に生まれた。創刊者は古瀬伝蔵。長野県の農学校の先生をしていた古瀬は、折から第一次世界大戦後の不況で繭の価格が暴落、米騒動、小作争議の頻発など農業問題が社会を揺るがすなか、生産農民の生活安定のための農政の確立が急務だと痛感し、教職を辞して上京。「地方の声を中央に」という強い気持ちのもと、小作争議などの社会問題を議論する場として国会議員、農政記者、学者たちによる大日本農政学会を組織し、機関誌『農政研究』を創刊。私財を投げうって発行を継続した。
大正期という農村が動いた時代の要請に、雑誌という、編集・発行者の意志のもと広くアピールすることが可能な媒体で応える。その精神は『現代農業』を軸とした農文協の「出版物による文化運動」として引き継がれている。
小作争議と農家小組合という二つの小農運動
大正期の代表的な動きとして、野田さんは小作争議と農家小組合に注目。これを小農経営を発展させるための二つの小農運動として、その特徴を整理している。
まず、小作争議について。一般的には地主対小作の階級的な闘争と見られがちだが、野田さんの見方はおおかた次のようだ。
《大正期小作争議は、数年間の昂揚の後、ほぼ2割程度の小作料減免を実現して終息に向かったが、ここで注目すべきは、地主一般ではなく、農家から小作料をとって町場で暮らす不在地主(寄生地主)に照準を定める傾向が見られたこと。当時の不在地主とは、むらを捨て耕地管理と戸数割負担の義務を負わない存在。これと闘うことは「むらの平和を乱す」ことではなく「むらの再生をはかる」ことであると、争議に訴えた自らの正当性を主張しやすいからである。不在地主はむらにとってのみならず、在村地主にとってすら好まれざる存在であった。》
こうして大正期の小作争議は、明治期以降の市場原理に基づく「利用から離れた農地の私的所有・資産化傾向」に批判を加え、その後の「農地所有の耕作者主義」と「農地のむら的管理」へ、そして戦後の農地改革へとつながっていく。福島県の農家、菅野正寿さんは、農地改革当時の農地をめぐるやりとりの記録を紹介し、「戦後の農地改革は、『当事者行政』だから成功したんだと思う」と次のように述べている(『季刊地域』2019年2月号)
「『東和町史』から見える農地改革は、役場職員でなく、農業普及員でもなく、同じ村で耕作し生産と生活を共にしている『当事者としての農地委員』がやり遂げたものだった。だからこそ画一的ではなく、強制的でもなく、小作人・地主の事情に寄り添って、的確に民主的に審査が行なわれ、わずか2年という期間に農地改革を進めることができたのだと考える。耕作者の家族農業と経営の自立のために、力を合わせて地域農業を発展させるという『農地改革の精神』が、ここから十分に伝わってくる」
野田さんも、「日本の農地改革は、戦前来の小農運動が積み上げて到達した、例外的かつ貴重な歴史的結論であった」と述べている。「例外的」というのは、農地改革という農地所有の改編が、大きな争いを招くことなく、むらの自治のもと平和的に行なわれた例が、世界的にはほとんど見られないからである。
「むらと結合した協同組合」から新生農協へ
もう一つ、この時代の農家小組合について。野田さんによると、大正期の農家小組合は「生産過程の共同」に取り組み、従来の「農事の改良」の機能に加えて「農業経営の改善」と「農家経済の向上」などに重点を置き、共同の力で農家経営の内延的拡大をめざした。明治期の小組合とは違い、資本主義の発展のもと強まってきた商品生産と市場への対応を課題とする機能集団という性格を持つ。また、自治的性格を確保しているという点では、昭和期の小組合=実行組合とも違っていたという。
活動内容は、共同作業などの労力調整、共同精米・精麦、品種改良、共同購入、耕地・水利改善、共同販売、農林産加工、養畜・養蚕、山林・竹林などの協同活動であり、さらに研究会・講和会、慰安会、娯楽慰安日の設定、視察など、「福利増進等」の活動もあった。農家小組合をつくる運動は大正期までに44府県で進められ、その数は、近世藩政村の6万3000を超える約8万組合に及んだ。
農家小組合は府県農会のリーダーシップに基づいて組織されたものではあるが、基本的にはむらの結合力に立脚した組織化の動きであり、国の法律による強制力をもたず、戦時統制に入る前の「自主性」をもち得た時代のむらづくり運動であった。こうして「むらと結合した協同組合」という、西欧とは違った「日本的協同組合」が形づくられた。
これが戦後の新生農協につながり、また農家の共同的な組織である「集落営農」につながっていく。
戦後まもなく、戦前の産業組合の流れを引き継ぐ形で、新生農協がむらむらに生まれた。しかし経営的基盤は弱体で、戦後のデフレのなか各農協は多額の欠損金を抱え、1951年から再建整備運動が始まった。『新明日の農協』(農文協刊)で太田原高昭さん(北海道大学名誉教授)は、この運動により、組合員農家の力によって農協が再建されたことを高く評価し、こう述べている。
「単位農協の再建整備は、組合員の出資金増強によってかなりの成果を挙げた。この増資は集落組織を動員した集落座談会や戸別訪問などあらゆる方法を使って推進され、多くは均等割りや反別割りなどで一律に決められたようだ。こうした負担によって5カ年計画の最終年には欠損金総額123億円に対して174億円の増資を達成している。これに対して国の奨励金の総額は30億円であったから、増資の83%は組合員農民が負担したことになる」
「再建整備は国の財政で農協を救ったもののように誤解されているが、救ったのは組合員の増資であった。このことが組合員の中にようやく『おらが農協』という担い手意識と責任感を育てたと言えないだろうか。そうだとすれば再建整備は農協への官僚支配だけでなく、農民の組合員としての自覚と主体性をも生み出したということになる」
ここに、「むらと結合した協同組合」という農家小組合の精神が引き継がれているのだろう。
集落営農の原点 農家小組合
農家小組合は集落営農にもつながっていく。「集落営農」の推進に尽力してきた楠本雅弘さん(農山村地域経済研究所)は、土地利用調整や維持管理などむらの自治機能を1階とし、直売所など収益事業部門を2階とする「2階建て方式」を提唱してきたが、これはむらの自治+機能集団という大正期の農家小組合と共通するしくみだ。楠本さんはその後、地域の困りごとが増えるなかで広がる集落営農の取り組みと課題を『進化する集落営農―新しい「社会的協同経営体」と農協の役割』(「シリーズ地域の再生」第7巻、農文協刊)としてまとめている。
「社会的協同経営体」とは、地域的営農組織としての活動だけではなく、それを土台にしながら、地域住民の暮らしを支え地域を再生する活動を展開する協同組織のこと。その例として東広島市河内町小田地区の「1階部分は、市町村合併で消滅した役場機能を実質的に復活した手づくり自治活動組織」「2階部分は農協と商工会を復活した地域協同経営体(コミュニティビジネス)」という「新2階建て方式」や、島根県出雲市・(有)グリーンワークの、営農活動に加えて、合併前の旧町から引き継いだ高齢者の病院への送迎など外出支援サービスや、農協ガソリンスタンドの灯油戸配サービスなどの「地域貢献活動」を紹介している。
楠本さんは本書で、大正期の農家小組合の多様な活動にふれ、「先人たちの原点に還れ! それこそが集落営農をして地域再生の拠りどころにする唯一の方法である」と熱く語っている。
『現代農業』創刊100年にあたり、私たちも小農経営とこれを支えるむらの自治の確立に向かった先人たちに学び、「地域の再生」に貢献したいと思う。
農文協の再建 自主自立と直接普及方式
大正期の「小農運動」を引き継いで戦後、家族経営とむら、そして「おらが農協」という小農の世界が確立し、そのもとで農文協は出版による文化運動に取り組んでいく。
農文協の設立は昭和15年(1940年)。この年は日独伊三国軍事同盟が成立した年であり、既成の諸政党が相ついで解散し、大政翼賛会が生まれ、労働組合もすべて解散させられ、「大日本産業報国会」がつくられた。その翌年には「小学校」が「国民学校」と改称され、国家主義・忠君愛国主義の教育が強まった。
その昭和15年に、農文協は公益社団法人として設立認可された。活動の主要な財源は農商省からの助成金と、官庁及び関係団体からの委託費であった。農文協が活動できたのは、戦争推進、大政翼賛体制の一翼であったからである。主な活動は農村巡回による演劇、映画、スライドなどによる娯楽の提供だが、そこで求められたのは「銃後の守り」を固め戦意を高揚することであった。
敗戦後、占領軍によって農文協は戦争に協力した公職団体に指定され、当時の経営トップであった古瀬伝蔵副会長が公職追放となった。こうしてほとんど崩壊状態になった農文協の再建を担ったのは、新しい職員によってつくられた職員組合であった。戦争に協力したことをどうとらえるか、リーダーの岩渕直助(再建農文協の初代専務)は以下のように考えた。
「文化運動は人間の自由、平等を得るための運動であり、そのためには人間の自主的、自発的な精神を呼び起こすような働きかけが求められる。戦前の農文協はそもそも創立したときからほんとうの文化運動を行なうことは不可能だった。やむをえないといえばやむをえない。しかししかたないではすまされない。徹底的に自己批判をしなければならない。自己批判のうえに文化運動はできる」
こうして農文協のあり方をめぐる内部議論や内部闘争を経てたどりついたのは、「農文協は農民のものであり、農民の必要性から農民が資金を提供して農民のための文化運動団体をつくったのだ」という認識であり、自覚である。だから、国や特定団体による財政支援に頼らず、自主自立に徹する。再建農文協の主体形成の第一歩といえよう。
経営的困難を抱えて悪戦苦闘を続けた農文協にとって大きな転機になったのが、1949年(昭和24年)春から開始された、雑誌『農村文化』(現在の『現代農業』)の農家への直接普及方式であった。この方式によって農家の求めるものは、いわゆる文化評論ではなく、生産に関する「農業技術と経営」であることが明らかになり、『農村文化』誌は大きく変わった。化学肥料が広く普及するなかで、1950年新年号からは肥料の使い方についての連載講座が始まった。これをもとにした単行本『誰にもわかる肥料の知識』は、10万部という当時としては記録的売れ行き。その後、編集部は「現場主義」を強め、農家への直接取材記事を増やしていった。
バイクで農家を一軒一軒回る直接普及。農家にとって農文協職員は物売りであり、遠慮なくこんな雑誌では役にたたないとか、時には悩みや農作業の工夫、村うちの話をしてくれる。そんなやりとりを編集部に伝えて雑誌の内容に反映させる。農家と普及者・編集者の循環によって「農家がつくる雑誌」がつくられる。農家との循環的関係性が、農文協の主体形成を支えている。――次号へ続く。
(農文協論説委員会)