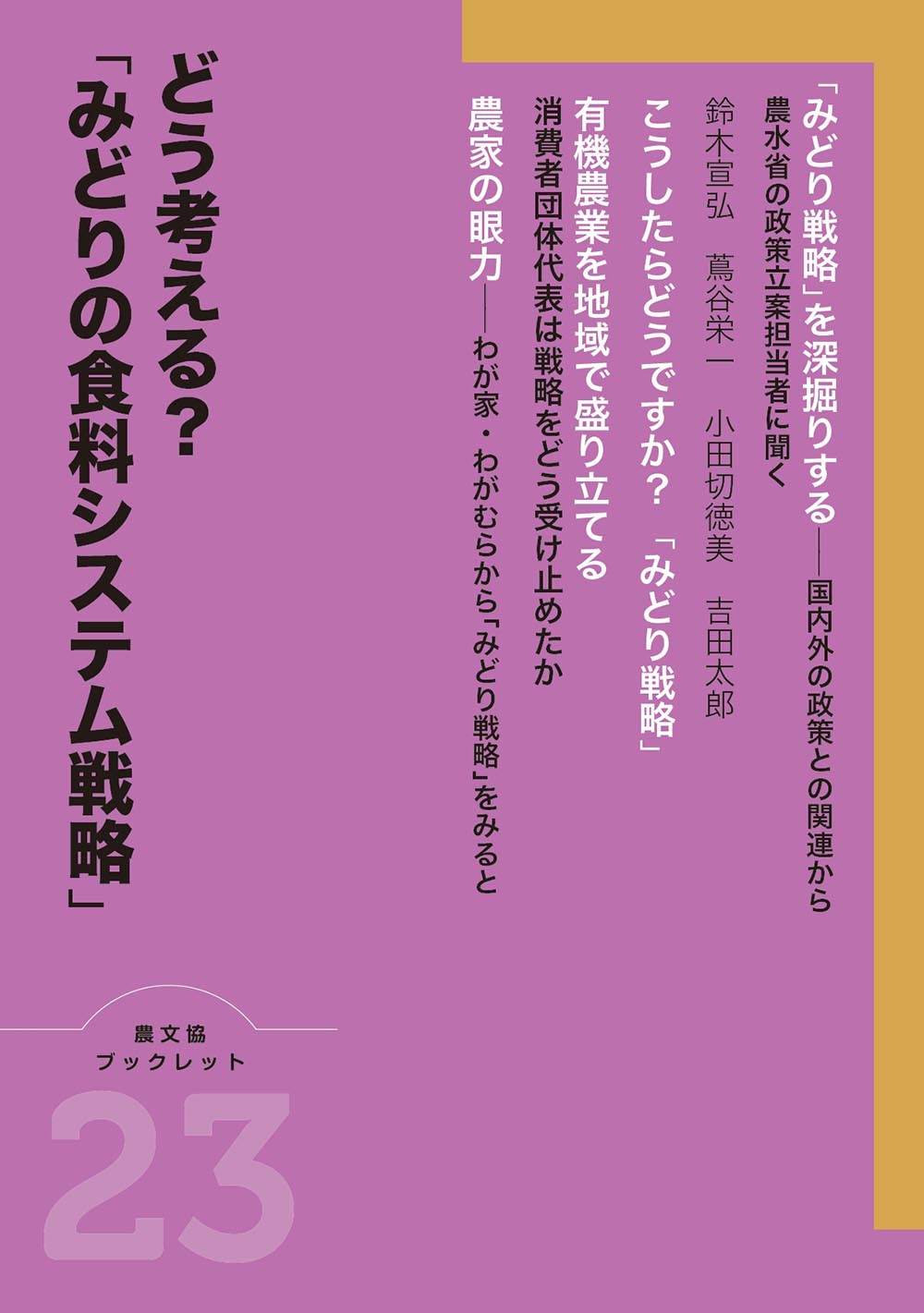主張
みどりの食料システム戦略 「絵に描いた餅」にしたくない
目次
◆有機農業100万haだけの問題ではない
◆ネオニコ系農薬禁止はすぐにもできる
◆ゲノム編集と表示制度に異議あり
◆トップダウンの戦略をボトムアップで展開するには
◆有機農業と環境保全型農業の二正面作戦
今年5月に農水省が発表した「みどりの食料システム戦略」(以下、みどり戦略)。本「主張」欄でも7月号、8月号、9月号と続けて取り上げてきたので、すでに内容をご存じの方も多いと思うが、ひと通りおさらいしておこう。
みどり戦略の目標年次は2050年。これは菅首相が昨年10月、カーボンニュートラルを目指すとした目標年次と同じである。この2050年に農林水産業のゼロエミッション化、化学農薬のリスク換算50%削減、化学肥料30%削減、有機農業の栽培面積を全体の25%(100万ha)に拡大など、林業や漁業を含めて14の目標が掲げられている。
農水省が急ピッチでみどり戦略を策定した背景には、農業の環境への負荷を下げようという国際的な動き、とりわけ昨年5月にEUが「Farm to Fork(農場から食卓まで)戦略」を打ち出したことが大きく影響しているといわれている。また、今年9月には国連食料システムサミットの開催が予定されており、世界の潮流に乗り遅れてはならないという思惑も、みどり戦略策定を後押ししたに違いない。
有機農業100万haだけの問題ではない
それにしても、なにごとにも慎重な農水省としては、考えられないような思い切った目標ではないか。それだけに、これまで有機農業に取り組んできた農家や団体、研究者を中心に大きな議論を巻き起こしている。その一方で、あまりに現実とかけ離れた目標だけに、農業の現場から遠い絵空事のようにとらえている方も多いのではなかろうか。
だが、みどり戦略は有機農業だけを射程においた政策ではない。今後30年の国内の食料・農業政策、ひいては農村政策全体とかかわりをもたずにはおかない。そこでは世代交代の波のなかで地域農業の担い手と農業生産をどう維持するか、農業の環境への負荷と食料自給力との兼ね合いをどうとっていくかといったことも大いにかかわってくるはずである。この戦略をどうとらえたらいいだろうか。
農文協は9月末に、ブックレット『どう考える?「みどりの食料システム戦略」』を発行する。ブックレットでは農水省の政策立案担当者に戦略の背景をインタビューしたうえで、農業・農村政策の専門家に内外の諸政策と関連づけて、この戦略の課題を分析していただいた。さらに有機農業や環境保全型農業の実践者・研究者、消費者団体代表からの提言や、有機学校給食・自然栽培の先進地の取り組みを紹介し、最後に全国各地のツワモノの農家たちから、この戦略をどうとらえたかを歯に衣着せずに開陳していただいた。筆者は25名で、うち10名が農家だ。「みどり戦略を、わが家・わがむらの今後30年のプランと結合するにはどうすればいいか」という問題意識をもって編集した。
今回はこのブックレットから、農家の意見を中心に紹介してみよう。
ネオニコ系農薬禁止はすぐにもできる
はっきり言って、有機農業や環境保全型農業に取り組んできた農家の「みどり戦略」への評価は辛口だ。「大辛」と言ってもよい。
新潟県佐渡市の齋藤真一郎さんは水稲32ha、おけさ柿250a、その他果樹、ハウスイチゴや大豆を(有)齋藤農園として経営している。大規模経営だが、農薬、化学肥料はできるだけ減らし、水稲2.5haと果樹の一部は自然栽培も試験的に実施している。
齋藤さんは先輩農家とともに、佐渡で一度絶滅したトキの野生復帰を農家の立場から支援する「佐渡トキの田んぼを守る会」を2001年に立ち上げ、生きもの調査や減農薬、無農薬のイネつくりを進めてきた。2008年にトキの放鳥がはじまると、鳥類の繁殖に大きな影響を与えるという報告もあるネオニコチノイド系農薬が大きな障害となると考えた。そこで、JA佐渡と相談し、ネオニコ系農薬と非ネオニコ農薬の比較圃場を設け、生きもの調査や赤トンボの抜け殻調査などを実施した。その後、JAは予約注文書からネオニコ系農薬を除外、2017年にはJA米要件としてネオニコ使用禁止を打ち出し、水稲栽培においては佐渡全島で脱ネオニコを実現している。齋藤さんがネオニコ系農薬を避けたいと考えるのはトキの繁殖への影響だけでなく、次代を担う子どもの健康被害を危惧しているからだ。
そんな齋藤さんにとってみどり戦略に「ネオニコ系農薬削減」という文字が載ったことは驚きだった。というのも、海外でのネオニコ系農薬の規制が厳しくなるなか、日本では残留基準を緩和し、むしろ使用を促してきたという経緯があったからだ。
「でも(脱ネオニコの)目標年次は2040年、世界は現時点で禁止や規制の方向に動いているのに、日本はまだ20年は使い放題の状況が続くというわけです。また、化学農薬を50%削減し、新規開発剤に移行するということは、ネオニコ系や代替新規化学農薬が40年以降も残ることを意味しているとも読み取れるので、よくよく考えると、玉虫色の目標だとわかります。
実際、現場ではやはり殺虫効果が高いネオニコ系農薬を、JAも農家も手放したくないというのが本音であることはよくわかりますが、この戦略を機に考え直すことが求められているのではないでしょうか」
齋藤さんは自らの実践から「脱ネオニコはいますぐできる」という。
農水省は齋藤さんのように、地元のJAと一緒になって地域で着実に減農薬・無農薬農業を進めてきた人のアイデアを真っ先に取り入れるべきではないだろうか。
ゲノム編集と表示制度に異議あり
50年近く前から、茨城県石岡市で有機農業に取り組んできた魚住道郎さんの意見も手厳しい。
魚住さんがとりわけ問題にするのは、品種改良におけるゲノム編集技術を容認し、スマート農業とともに研究の中心に据えているように読めることだ。魚住さんは言う。
「ゲノム編集された作物は、有機無農薬で育てたところで、はたして有機農産物と世界共通で認められるのだろうか。せめて表示義務を設け、有機農家には、ゲノム編集された品種を栽培しない自由が認められるべきだ。農水省のみどり戦略は、そうした有機農家の心情と逆行している」
日本の有機農業を牽引してきた日本有機農業研究会(1971年設立)の現理事長でもある魚住さんは、さらに表示制度についても注文をつける。消費者と農家の「提携」を長年築いてきた立場から、有機JAS認証をとった者にしか「有機」「オーガニック」の表示が許されていない現状を改めるべきだというのである。
「有機農業を広げるには、有機農業で栽培を行なう誰もが、自由に『有機栽培』と表示できるように許可すべきだ」
魚住さんは本気で30年後までに有機農業100万haを目指すなら、これまで有機農家が就農希望者の研修を受け入れてきた仕組みを公的な教育の場として保証し、47都道府県すべてに「有機農学校」を設立すべきだと提案する。
「有機農業は総合学問である。多品目による輪作や田畑輪換、緑肥活用や有機物マルチ、堆肥やボカシづくりや踏み込み温床、農薬に頼らない病害虫や雑草対策、耕起か不耕起か、直播きか育苗か、タネ採り、収穫物の保存や加工、家畜の飼料自給、土木や建築、農具作り、エネルギー自給や気候変動対策など、先人が多様な課題を克服し遺してくれた伝統技術と、農家自らの工夫を積み重ねた技術の結晶といえる。実践的有機農学校では、消費者との連帯や、腐植が繋ぐ森・里・海のいのちの連携、有機農業の哲学も学び、身につけなければならない。
講師陣は、その地域で活躍する有機農家や研究者、消費者など、有機農業を実際にリードしてきた人たちを中心に据える。また、既存の農業高校や農業大学校、専門学校の講師にも受講してもらい、新規就農希望の学生を一体となって養成する。森・里・海の視点から、林業や漁業の人々にも教えを乞いたい」
トップダウンの戦略をボトムアップで展開するには
みどり戦略には、「KPI」(目標達成度の評価)や「社会実装」「横展開」といった今はやりのビジネス用語がちりばめられ、AIなどの情報技術や遺伝子工学を含む「イノベーション」への高い期待が寄せられている。
ブックレットにはみどり戦略の政策立案担当者である農水省の岩間浩さん(現・農林水産技術会議事務局研究調整課長)のインタビューも収められているが、そのなかで、岩間さんはみどり戦略の基本姿勢についてこう述べている。
「本戦略では、現在の取り組みの延長というフォアキャストではなく、2050年に目指す姿、すなわちバックキャストとしての目標を掲げ、その実現に向けて、①生産だけでなく、その前の調達から始まり、加工・流通・消費の各段階で意欲的な取り組みを引き出すとともに、②将来に向けて、既存の優れた技術の横展開・持続的な改良と、革新的な技術・生産体系の開発・社会実装を進めていくこと、これがみどり戦略の考え方です」
バックキャスト(バックキャスティング)とは最近、環境対策がらみでよく使われるビジネス用語の一つで、目標を最初に設定して、それに向けて手法や工程を集中していく手法をさす。地球環境問題のような大きくて困難な課題に対処するために、このような飛躍が必要なことはある程度理解できる。だが、こういう発想でつくられる戦略は必然的にトップダウン型にならざるを得ない。
岩間さんが「既存の優れた技術の横展開・持続的な改良」と述べているように、「みどり戦略」がボトムアップを意識していないわけではない。それは、戦略の本文に「本戦略の推進に当たっては、(中略)意欲的な取り組みを引き出すことを基本に社会実装を進める」と書かれていることからもわかる。ただ、そのための具体的な方策は示されていない。必要なのは、魚住さんの有機農学校のような、「既存の優れた技術の横展開・持続的な改良」を進める具体的方策ではないか。
また、「こうした(内発的な)視点を、技術開発だけでなく、『戦略』全体で捉え直すこと」(明治大学教授・小田切徳美さん)も求められる。小田切さんは、ブックレットのなかで、新しい発想を得るためにバックキャスティング法にも意味はあろうとしながらも、こう注文をつける。
「『戦略』を実現するのが、地域に住み活動する農林水産業の担い手であれば、このような人々の内発的な力に接続するプロセスが必要になる。この過程がなければ、イノベーションは常に、他者から与えられた外来型のもの、別の言葉で言えばトップダウン型のものとなる。
これとは対照的位置にあるのは、2020年に制定された食料・農業・農村基本計画(新基本計画)で提起された新しい仕事づくり『農山漁村発イノベーション』である。ここで『農山漁村イノベーション』ではなく『農山漁村
小田切さんはイノベーションの本義は「技術革新」ではなく「新結合」だと言う。求められるのは「新技術」よりも、地域の資源と課題の「新結合」なのである。
たとえば、滋賀県近江八幡市の松村務さんは市役所を早期退職し、大型ハウスでトマト栽培に取り組んできた。松村さんは、家庭から出た使用済み天ぷら油をハウス内の暖房にすることで、ゼロカーボンを目指している。導入のきっかけは重油価格が100円/l近くに高騰したときの燃料経費削減が目的だった。2014年に廃食油でも使える温風加温機を導入、バイオディーゼル燃料の精製・販売を手掛ける業者と組み、燃料をリサイクルする仕組みをつくった。農園敷地の一角に天ぷら油回収ステーションを設置、トマトを買いにくるお客さんや料理店など、天ぷら油の処理に困った人たちがクチコミでどんどん持ち込んでくるようになった。
地域の人たちにとっては、ゴミとして捨てていた廃食油がトマト栽培に役立つという満足感が得られる。精製業者にとっては新たな回収ステーションができる。農園にとっては、新たな顧客開発ができる。
「『三方よし』に『地球よし』が加わり、地域資源循環サイクルができつつある」
みどり戦略に求められるのは、全国各地で行なわれているこのような「農山漁村発イノベーション」=「新結合」を発掘し、横に広めていくこと(=横展開)ではなかろうか。
有機農業と環境保全型農業の二正面作戦
このような農・食・環境を全体として前進させる取り組みを、地域という「面」に広げるにはどうしたらよいだろうか。ブックレットには、わずか4年で学校給食の全量有機米使用を実現した千葉県いすみ市や、行政とJAがタッグを組んだ自然栽培聖地化プロジェクトで、多くの新規就農者を迎え入れている石川県羽咋市などの事例が紹介されている。
これらは、有機農業・自然栽培を急拡大させた取り組みだが、農的社会デザイン研究所代表の蔦谷栄一さんは、みどり戦略の目標実現には「展開戦略」が不可欠であり、それには有機農業の振興と環境保全型農業によるボトムアップの「二正面作戦」が有効だと説く。有機農業でいくか、環境保全型農業でいくか、生産者の意向をもとに、地域性、生産品目等を勘案して、現場の判断にまかせるものとする。
「そして、環境保全型農業は地域・集落レベルで地域営農計画にしっかり落とし込んで取り組みを推進していくことがポイントで、有機農業比率25%に対し、残り75%を対象に期待は大きい。このためにはJAグループの役割発揮が不可欠だ」
農業者・消費者・行政が一体となった「持続農業会議」を全国・地方・地域に各々設けて、協議・調整を重ねていく。そこでは農業のあり方だけでなく、担い手確保や自然エネルギー利用についても地域ぐるみで取り組み、成果を「見える化」していくことになるだろう。
岩間さんによれば、農水省は新基本計画を策定したのち、昨年7月から、事務レベルでみどり戦略のもととなる検討をすすめてきたという。政府のゼロカーボン宣言が出されたからではなく、「農水省自らの問題意識でこの戦略の検討がスタートした」とのこと。
農水省のその意気やよし。ただ、もし、この戦略を各地の農(林漁)家それぞれが今後30年のプランとして、言い換えれば「自分事」としてとらえることがなければ、戦略はまったくの「絵に描いた餅」に終わってしまうことだろう。そうした農家の思いと蓄積された知恵と技術を結集し、農山漁村発イノベーション=新結合を起こすほかに、戦略に魂を吹き込む道はない。
(農文協論説委員会)