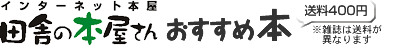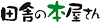農山村からの脱原発
山も人も蘇る「コミュニティ・エネルギー」
目次
◆�「原発に代わる電源」は本当に必要なのか
◆�熱を電気でまかなうのはバカバカしい
◆エネルギー源としての利用で山が蘇る
◆農山村にはエネルギー自給の条件がある
◆コミュニティ・エネルギーは手間・ヒマ・技術を求める
◆「人の意見」に依らず「物に問ふ」地域再生
▲目次へ戻る
�「原発に代わる電源」は本当に必要なのか
「喉元過ぎれば熱さを忘れる」とはよく言ったものだ。
東京電力福島第一原発の事故後、原発はもうこりごりだ、原発はすぐ止めようという機運があれだけ高まったにもかかわらず、少なくとも2030年代まで原発を存続させることは既成事実となり、新政権によってそれすら反故にされそうな勢いである。その理由は経済成長や貿易赤字削減だが、もう一つは原発に代わる電源を開発するのには時間がかかるというものだ。
本当にそうだろうか。
「良識派」と呼ばれる人でも、よくこんな言い方をする。
「原発を止めるためには、それに代わる電源を開発しなければならない。そのために再生可能な電源開発を推進する固定価格買取制度を活用しよう」と。しかし、本当に原発に代わる「電源」ができないかぎり、原発を止めることはできないのか。
ここに大きな落とし穴がある。
エネルギーは電気だけでまかなわれるものではない。むしろエネルギーをすべて電気に頼るような生活こそが原発抜きではいられない状況をつくってきた元凶ではないか。
そのことを、本誌の姉妹誌『季刊地域』12号(「特集 薪で元気になる!」)で東北芸術工科大学准教授の三浦秀一さんが、オール電化住宅に象徴される熱の電化という視点から鋭く指摘している(注1)。
▲目次へ戻る
�熱を電気でまかなうのはバカバカしい
それはこういうことだ。オール電化住宅では照明や家電だけでなく、風呂などの給湯、暖房、コンロ(厨房施設)までも電化し、家庭で使うすべてのエネルギーを電力会社から購入するように仕向けられる。給湯、暖房、コンロ……これらはすべて熱エネルギーだ。
じつは家庭で消費するエネルギーのうち、熱エネルギーが占める割合は照明や家電などに使うエネルギーよりはるかに大きい。そのため、オール電化住宅では通常の住宅の約3倍の電気を消費する。暖房費のかさむ、東北電力管内では4倍にもなるという。
石油やガスといった燃料を直接暖房や給油に使うとその効率は80%を超える。しかし火力発電所の発電効率は40%程度。本来給湯や暖房を電気でまかなうのは非常に効率が悪いことだ。オール電化住宅は快適なようで、エネルギー効率からすれば非常にロスが多いのだ。
ではなぜそんなばかばかしいことをすすめるかと言えば、電気の需要を伸ばしたいからである。日本では人口の減少や省エネの進展によって電気需要が構造的に減少することが見込まれている。そのなかでオール電化住宅による熱の電化は、電力の大きな新規需要を生み出してくれる期待の星なのである。大きな電力需要を生み出すことができれば、まだまだ電気が足りないから原発を推進する、という論理にもつながる。
そのオール電化住宅がこのたびの東日本大震災でたちまち機能不全に陥ったことは記憶に新しい。
脱原発を目指すなら、この逆を行けばいい。熱と電気を分けて考え、もっとも無駄な熱の電化をまずやめ、ついで熱源として石油やガスに頼る度合いを減らして再生可能エネルギーに置き換えていく。次に、いまのところ電力でしかまかなえない照明や家電などを再生可能な電源から供給する。
熱源となる再生可能エネルギーとしてもっとも有望なのが、備蓄型の自然エネルギーであり、太陽エネルギーをため込んだともいえる木であり、薪なのである。
▲目次へ戻る
�エネルギー源としての利用で山が蘇る
日本では木とか薪のエネルギー利用と言えば、なにか昔の話のように思われている。しかしヨーロッパでは再生可能エネルギーのうち森林(木質)バイオマスが約半分を占める。
ヨーロッパの再生可能エネルギーの中心は森林バイオマスであり、そのベースはいまでも薪なのだ。森林バイオマスについて言えば、日本は非常に条件に恵まれた国といえる。国土の3分の2を森林に覆われているような国は、先進国では日本のほか、フィンランドとスウェーデンぐらいしか見当たらない。しかし薪の生産量をみると日本はフィンランドのわずか1000分の1なのである。
ヨーロッパでは薪をベースとしながら、大きな薪ボイラーやチップやペレットの利用、地域熱供給システムも含めて森林バイオマス活用の仕組みが日々進化している。日本もせっかくの恵まれた資源をもっと生かしたい。
そもそも日本の山の木は、戦前までは建築などの用材よりも薪炭材として伐採されることが圧倒的に多かった。日本の山は「エネルギーのための山」であり、日本の林業とは「エネルギー産業」だったのである。
1955(昭和30)年頃、家庭で使われるエネルギーの約70%は薪や炭でまかなわれていたのだ。
その後、「エネルギー革命」が起こり、薪や炭によっていた風呂、暖房、炊事は石油やガスに置き換わっていった。相前後して拡大造林によって山にはスギ、ヒノキなどの針葉樹が一斉に植林され、それもその後の木材の輸入自由化によって、経済的に合わなくなり、間伐もされずに荒れていったのは周知の通りである。
全国に広がりつつあるナラ枯れ。これも山がエネルギー源として利用されなくなったことと大いに関係があるという。ナラ枯れの原因はカシノナガキクイムシが木の孔に菌を持ち込むことが原因で起こるといわれているが、この虫は太い老木に多く侵入し、細くて若い木にはあまり侵入しない。薪炭林は広葉樹を20〜30年くらいで伐採し、萌芽更新するサイクルで利用されていたから、老木は少なく、カシノナガキクイムシがはびこることもあまりなかったわけである。
逆にいえば、里山をエネルギー源として積極的に活用していくことはナラ枯れ対策にもつながるということだ。
エネルギー利用で山は豊かに蘇る。
エネルギーの供給地であった農山村がエネルギーの消費地にかわったことは、農山村の経済的衰退の一因でもあった。エネルギーを生産する条件がなくなったのではない。農山村には木(バイオマス)はいまでも豊富にある。いや森林の蓄積量は昔より増えているかもしれない。資源がなくなったのではなく、顧みられなくなっただけなのだ。
▲目次へ戻る
�農山村にはエネルギー自給の条件がある
農山村がエネルギーの消費地になったことで、日本のエネルギーは大規模集中型となった。
電気について言えば、原発や火力発電所、大規模水力発電所で生産された電気が系統電力網によって全国津々浦々に供給される。その生産と供給は電力会社によって一元的に管理されているが、電気はためておくことが難しく、広範囲を調整するとなると、いきおい電力消費量のピークに合わせて多めに生産することになる。そのため原発が必要になり、電気が余れば、オール電化住宅をつくってまでも無理矢理需要を創出するという流れになってしまうのだ。
石油やガスについても同じことがいえる。
考えてみれば、ずいぶん無駄な話ではないか。
この大規模集中電力(エネルギー)システムを分散型エネルギーシステムに転換すれば、もっと無駄を省くことができるのだ。
茨城大学教授の小林久氏は、こう述べる(注2)。
「電力の需要が少ない場所は、一般的に農山村地域でバイオマスが多く、小水力発電に適している。そうであれば、農山村は、まずバイオマスや小水力発電によってエネルギーを生産供給し、需要をまかなったらどうだろうか。自給以上の多くのエネルギーを生産できる地域は、エネルギーを外に湧出させ、国産エネルギーの供給を増やせばいい。水源地の山間地域は、とくに水力やバイオマスに恵まれているので、自然エネルギーを湧出するエネルギー供給地になれる可能性がかなり高い。」
「大規模生産のエネルギーを幹(本流)から枝(支流)を経て、葉(末端)に配るという現行システムを、自然のエネルギーフローと同じようにたくさんの一つ一つの葉で生産し、まず葉自身(末端需給)の需要をまかなったうえで枝(支流)を経由して幹(本流)に余剰を集めるというシステムに変えようというわけだ。
その定着プロセスとして、わたしは以前から流域の上流の水源域から下流に向かって自然エネルギーの自給・湧出地が増え、一つ一つの自給・湧出地が複合するエネルギー供給区が末端から幹に向かって拡大してゆくようなイメージをもっている。」
ここで一枚一枚の葉とはエネルギーを生産し、消費する小さなコミュニティ(むら)のことである。それを木と水を中心とした自前のエネルギー(=地エネ)でまかなっていく。
それではいったいどれだけの資源があれば、コミュニティのエネルギー自給が可能になるのだろうか。
小林氏によって、まず熱から見ていこう。一世帯が暖房に使う熱量は年間約9500MJ。これをすべて薪でまかなうとすれば必要な薪の量約500kg(約100束)、仮に効率を50%としても1000kgあれば間に合う(もちろん木質チップやペレットでも構わない。太陽熱なら、5〜10m2の集熱施設があれば足りる)。給湯もほぼ同じくらいの薪でまかなえる。
薪1000kg/年はおおむね0.2haの森林の1年当たりの木材蓄積量に相当するという。暖房と給湯を合わせれば2000kg/年、0.4ha分だ。平均的な30戸の集落であれば12haの森林があれば、その毎年の蓄積量でまかなうことができるというわけだ。
一方、30戸の集落で必要な電力は、15〜20kW程度の小水力発電でまかなうことができる。これに農作業や輸送に必要なエネルギーを電力換算して加えても、その2倍くらいの施設容量があれば十分だという。
この程度の条件はどのむらにもありそうではないか。
昨年7月から施行された再生可能電力の固定価格買取制度(FIT)は、小水力発電などの地エネを導入した場合の初期投資を確実に回収する裏づけとなるだろう。ただし、FITは再生可能な「電源」に限った制度だし、当面3年間は価格的な優遇措置がとられるとはいうが、制度が長く続く保証はない。
基本的には自分たちの生産・生活をまかなう電気を含めたエネルギーを自給することを目標とし、余ったら系統に売電するという考え方をとるのが本筋であろう。
▲目次へ戻る
��コミュニティ・エネルギーは手間・ヒマ・技術を求める
農山村がエネルギーの大半を自給していた時代は、むらの老若男女が一日のうちの多くの時間をそのために費やして働いていた時代である。年配の方なら子どものころ、学校から帰ったあと山に行って背負子に薪や粗朶を背負ってきたとか、風呂焚きが日課だったという思い出をもつ方も多いだろう。
昔は木や葉だけでなくワラや菜種殻、豆殻といった作物残渣もけっして無駄にせず、焚きつけなどに利用していた。いまでいうバイオマスのフル活用である。
エネルギー自給時代というのはそういう厳しい労働に支えられていたことはまちがいない。
しかし、手間がかかるということは、それだけそこに仕事(稼ぎ)を生み出す余地が生まれることでもある。
たとえば、小水力発電では水車や水利施設の除塵(ゴミを取り除くこと)が欠かせない。しかし、考え方を変えれば発電所の管理のために新しい雇用が生まれるということでもある。除塵とか薪をくべるといった程度の労働であれば、かかりきりになる必要もなく、一日中むらの中にいる高齢者にぴったりの仕事なのだ。
山梨県道志村では2012年から村営温泉施設「道志の湯」の熱源を重油ボイラーから薪ボイラーとの併用に転換した。この薪ボイラー(ガシファイアー)は含水率が高い間伐材の太い生木でも、そのままガンガン燃やせるスグレモノだ。燃料となる薪は村内の自伐林家などから用材として使えないスギのC材を買い取っている。
「道志の湯」では薪からの熱供給を全体の8割にすることによって、年間1700万円かかっていた燃料費を1200万円(重油代700万円+薪代500万円)に減らすことができた。それだけではない。「木の駅」(集材土場)に持ち込まれるC材には1m2当たり5000円が支払われる。うち1000円は地域振興券として支払われ、地元の商店やガソリンスタンド、理美容室など43店で利用することができる(注3)。
重油代は村から出ていくおカネだが、薪代は地域内で循環し、地域を潤すおカネになる。「地産地消」ならぬ「地産地焼」である。
薪ボイラーもそうだが、薪ストーブ、ペレットストーブも、小水力発電のための水車や発電機もどんどん進化している。その開発に参入する地方メーカーも多い。ガシファイアーを生産する(株)アークは新潟市の建築会社が出資してできたメーカーで、北欧の燃焼技術を導入し、5年前に薪ボイラーの国産化に成功したという。
全国津々浦々で地エネが伸びていけば、地方の企業もこぞって技術開発に参加し、機材ももっと進歩していくことだろう。
▲目次へ戻る
�「人の意見」に依らず「物に問ふ」地域再生
少々話は飛ぶが、ここで明治時代に移植大工業ではなく、地方の産業振興優先を唱えた前田正名について紹介したい。松方財政と言われる、農村を収奪し、移植大工業を発展させる経済政策によって、地方の疲弊が頂点に達した明治17年、農商務省大書記官であった前田は地方の実態をつぶさに調査して『興業意見』としてまとめ、農工商の調和的発展の重要性を指摘した。
前田は「『一己の意見、学者の論、実際家の説、外国の参考』いずれも偏重することなく、『日本の事実、実物に基づきて方針を定める』こと、『物に問ふ』ことが先決である」と主張していた(注4)。『興業意見』は松方正義大蔵卿のクレームにより、大幅に改変され、前田は罷免される。その後一時農商務省に返り咲いて「農商務臨時調査」を進めようとするものの、陸奥宗光の農商務相就任によって、再び追放されることになる。野に下った前田正名は草履、脚絆姿で全国を行脚し、地方の資源を掘り起こし、地域振興を図る「町村是」づくりを説いて回った。
格差拡大と地方の疲弊を顧みず、新自由主義の経済理論にしたがって少数の輸出大企業やゼネコンを優遇し、成長路線を突き進む――まさに今日の政治は松方財政と重なるところがある。
成長のおこぼれを期待するのか、それとも足元の資源を見直しながら地方にエネルギーや食料を中心とした小さな産業と仕事をおこし、自立したコミュニティを築いていくのか。われわれは「物に問ふ」ことを通して、前田正名が勧めた町村是をいまこそつくらなくてはならないのではないか(注5)。地エネ、コミュニティ・エネルギーによる脱原発はそのような「平成の町村是」運動への第一歩になるではないだろうか。
*
本稿でも紹介した、小水力発電研究の第一人者である小林久氏や国内外の森林バイオマスに詳しい三浦秀一氏ら八人の研究者が共同執筆した『コミュニティ・エネルギー』が「シリーズ地域の再生」第13巻として、3月に刊行される。農山村がエネルギー自給力を回復するための具体的指針としてぜひお役立ていただきたい。
(農文協論説委員会)
(注1) �三浦秀一「熱を電気でまかなうのは効率が悪い」『季刊地域』12号、農文協
(注2) �小林久「コミュニティ・エネルギーに挑む農山村――小水力発電を中心に」『コミュニティ・エネルギー』(仮題・三月発行予定)未定稿、農文協
(注3) �「C材の地産地焼で地域のフトコロもあったまる」『季刊地域』12号、農文協
(注4) �祖田修「解題」前田正名『興業意見・所見』(『明治大正農政経済名著集1』)農文協
(注5) �玉真之介「『平成の町村是』は可能か?」『季刊地域』12号、農文協
▲目次へ戻る
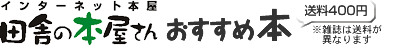
 |
この記事の掲載号
『現代農業 2013年3月号』
特集:発芽名人になる!(2)
元肥一発肥料に動きあり/野菜産地ですすむ 不耕起栽培/巨大化した樹をコンパクトに 低樹高への道/簡単、ヘルシー 野菜寿司/新規就農は「加工」がねらいめ/大震災をバネに夢を実現 米粉麺にピーンッときた/放射性セシウム吸収の実態と要因 ほか。
[本を詳しく見る]
|
 |
『季刊地域2013冬』農文協 編 特集:薪で元気になる!
地産地焼のしくみをつくれ/熱を電気でまかなうのは効率が悪い/買い物不便なむらが立ち上がる/住民で支える地域限定“タクシー”/「猿新聞」で心を一つに/マイクロ発電も固定価格で勢いがついた ほか。
[本を詳しく見る]
|
 |
『季刊地域2012秋』農文協 編 特集:地エネ時代 農村力発電いよいよ
[本を詳しく見る]
|
 |
『現代農業 2011年12月号』農文協 編 特集:燃料自給 なんでも薪に!
[本を詳しく見る]
|
 |
『農家が教える自給エネルギーとことん活用読本』農文協 編 3.11の大震災・原発事故以来,「節電」がアピールされて巨大かつ集中的管理の脆さが露見し,自然エネルギーに対する社会の態度は変わりつつある。しかし,大方の議論は国家的なエネルギー政策という観点から,「電力」を中心に再び新たな巨大インフラが話題に上る。しかし,そこからだけでは未来は拓けない。本書は,身の回りに眠っているエネルギーを暮らしに活かす,小さなエネルギー自給のさまざまな面を楽しく描き出す。人任せのエネルギー議論から一歩先に進むための,エネルギー自給実践の書。
[本を詳しく見る]
|
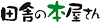
|