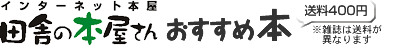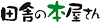「家とムラ」の存続のための「地域営農ビジョン」を
目次
◆TPP農政として立案された「人・農地プラン」
◆JAは支店を核に「次世代へつなぐ協同」を実践
◆「次世代へつなぐ協同」は「強い経済」の対抗概念
◆農協はムラの組織原理を根底にもつ二階建て組織である
◆グローバル化時代の〈世界標準〉からの脱却
◆「家とムラ」の存続のための「地域営農ビジョン」を
▲目次へ戻る
TPP農政として立案された「人・農地プラン」
「人・農地プラン」は、政府の「我が国の食と農林漁業の再生のための基本方針・行動計画」(平成23年10月25日決定)を地域で実際に進めるための施策である。その基本方針・行動計画の「はじめに」で、その目的とするところを次のように述べている。
「我が国の食と農林漁業は、所得の減少、担い手不足の深刻化や高齢化といった厳しい状況に直面している。農山漁村も活力が低下しており、食と農林漁業の競争力・体質強化は待ったなしの課題である。同時に、我が国の貿易・投資環境が他国に劣後してしまうと、将来の雇用機会が喪失してしまうおそれがある。こうした認識に立って、食と農林漁業の再生会議は、『包括的経済連携に関する基本方針』(平成22年11月9日閣議決定)にあるとおり、『高いレベルの経済連携の推進と我が国の食料自給率の向上や国内農業・農村の振興とを両立させ、持続可能な力強い農業を育てるための対策を講じる』ことを目的として、これまで精力的に議論を積み重ねてきた」
ここで確認しておきたいことの一つは、「包括的経済連携に関する基本方針」が政府・財界・マスコミが至上命題とする「新成長戦略」、つまり「強い経済」の実現を目的としていることである。その意味で「人・農地プラン」はTPPや消費増税、原発再稼働と同根のものであり、そのどれもが「強い経済」を渇望する輸出大企業にとって欠かすことができないものなのである。
そしてもう一つ押さえておきたいことは、「人・農地プラン」の施策を通じて、集落や地域ごとに、話し合いによって担い手(中心となる経営体)を定め、そこに過半の農地が集積するように集落全体で協力することで、その担い手が実質的な規模拡大を図り、平地で20〜30ha、中山間地で10〜20haの規模の経営体が大宗を占める構造をめざしていることである。
戦後農業を支えてきた昭和一桁世代から次世代への大世代交代期を最後のチャンスとばかりに、半世紀にわたる失敗続きの「構造改革」についての反省もなく実施に移される究極の構造改革=「人・農地プラン」。だがこれによって、持続可能な「力強い農業」が実現できるのか。そもそも、競争力の強化などが問題ではなく、持続可能な「農家経営と地域社会」の再生こそが課題ではないのか。
事柄は単純に農業だけの問題ではなく、農家と農協など地域社会の存亡をかけた課題である。事柄が深刻であればあるほど、農家・農村の現場で「家」と「ムラ」の存続の原理に学び、日本と世界の農業・農村数百年、数千年の歴史に学ぶほかあるまい。
ここに、その「問い」と真摯に向き合う好著がある。農政が最大の課題としてきた構造改革路線が何故実現されなかったのか、また、それを阻んだ日本の農業・集落の個性とは何かを近現代史の中に求めた「名著に学ぶ地域の個性」のシリーズ5『〈歴史と社会〉日本農業の発展論理』(野田公夫著)である。それを参考にしながら上記の問いを考えてみたい。
▲目次へ戻る
JAは支店を核に「次世代へつなぐ協同」を実践
組合員と地域の課題に向き合う事業・運動を
JAグループは、昨年5月「東日本大震災の教訓をふまえた農業復権に向けたJAグループの提言」を発表した。それは第25回JA全国大会に掲げた「農業の復権」と「地域の再生」に向けた「新たな協同」の創造をより具体化させるもので、これを受けて、今年10月に開催される第26回JA全国大会の議案書・組織協議案では「次世代へつなぐ協同」を掲げている。全正組合員の42%、185万人を占める昭和10年代生まれまでの第1世代のリタイアが迫っているなかで、昭和20年代以降の第2・第3世代が中心になって地域住民をも結集し、地域とJAの新しい姿を作り上げていくという趣旨である。
この大会議案書では、JAグループの10年後のあるべき姿を実現するための3つの戦略を掲げている。第1の戦略「地域農業戦略」の柱は、集落で徹底的に話し合って組合員農家の営農の向上と地域農業・農地の継承を図る「地域営農ビジョン」の策定と実践。第2の戦略「地域暮らし戦略」は、「JA支店を拠点としたJA地域暮らし戦略の実践」が柱で、JAが総合事業を通じた地域のライフラインの一翼を担うかたちで、豊かで暮らしやすい地域社会の実現をめざす。そして第3の戦略「経営基盤戦略」では、JA経営改革のめざす方向として、(一)リストラ型経営から事業基盤強化・組合員の利用度伸張型経営への展開、(二)食と農・暮らしを基軸とした第2世代・準組合員・地域住民へのアプローチによる「協同」の拡大、(三)総合力を発揮する経営態勢の確立と役職員の意識・行動改革による協同の実践の3つを掲げた。
第26回協議案の最大の特徴は、この間の広域合併と支所統廃合というリストラ型経営に終止符をうち、JA支店を核に組合員と地域の課題に向き合う事業・運動の展開に軸足を移すことにある。農家経営や地域資源、集落の歴史など、集落や旧村ごとに異なる農家の生産・生活基盤に立脚した「地域営農ビジョン」づくりとその実践は、JA支店を核として進めなければならない。そうすることによってはじめて農家・集落主体のビジョン策定運動への展開とJAの新しい事業基盤確立とが可能になるからである。
▲目次へ戻る
「次世代へつなぐ協同」は「強い経済」の対抗概念
「自由と民主主義」の理念に基づき協同組合精神の実践組織をめざして1947年にスタートした新生農協は、戦時統制下で、農業会が完成させた事業における「総合主義」(各種の事業を兼営する)、同種の事業を行う組合への二重加入を禁止する「属地主義」「網羅主義」を引き継いだ。日本の農協は、移転不可能な農家と農地・自然、ムラに依拠する、世界でも稀な組織として誕生したのである。
JAグループがテーマに定めた「次世代へつなぐ協同」は、もともと農家の「家」としての家族周期(ライフサイクル)、それに伴う経営の伸縮を調整するムラの補完機能を基礎にしている。そうした有史以来連綿と続いてきた世代継承サイクルの断絶が問題になってきたのは、本質的には、戦後高度経済成長期以降の西欧的な近代化・都市化、経済のグローバル化等によって、農家の生産と暮らしの日常文化が変質させられたことによるものである。したがって、「次世代へつなぐ協同」のためにはポスト近代の新しい農家経営と地域経済の創出がなければならない。
現代は、世界市場を掌中に収めようとする「世界企業」と農林漁家・農村地域との敵対的矛盾が地域のすみずみまで入り込み、一方で、それが世界化する時代である。そういう意味で、「次世代へつなぐ協同」の実践は「強い経済」の対抗概念としてとらえる必要があるし、それ相応の覚悟が求められることなのである。
『〈歴史と社会〉日本農業の発展論理』の「はじめに」で野田氏は次のように述べている。
「現代世界すなわちグローバル化世界においては、『可動性』こそが『新しいヒエラルヒー』であり『もっとも強力で、もっとも熱望される要素』であるというバウマンの卓抜な指摘がある。『可動性』(移動する自由)とは自らの利益を最大化できる地球上の場を自在に選びとる力のことである。世界市場を掌中に収めた『世界企業』と世界を舞台に活躍できる『世界的個人』(世界エリート)こそが、かかる『空間の戦争の勝利』者である。グローバル化は、これらの少数者に破格の富を集中させる一方、『移動する自由』を大幅に制約された圧倒的多数の人々を放置し、エンドレスな貧困化に陥れていく。そして、『移動する自由』をもたない最たるものが『大地のうえに営まれる小規模農業』であることは言うを待たない。
さらに東日本大震災・福島原発事故は、この『理不尽な対比』を極限的に否応なく明るみに出した」
JAは、言うまでもなく、この「移動する自由」をもたない「小規模農業」を生業にもつ農家の組織である。戦後の日本農業を背負ってきた戦前の第1世代の生涯現役を支えながら、彼らが拓いてきた直売農業、小力農業技術、そして地域資源活用の知恵(農家が創る日常文化の現代的再生)に学び、団塊を中心とする第2世代・青壮年の第3世代に引き継いでいく役割がJAの最重要な課題になったということである。JAがこれを担う意味は大変大きい。
▲目次へ戻る
農協はムラの組織原理を根底にもつ二階建て組織である
大正期「農家小組合」運動に学ぶ
本誌2012年8月号の主張「『人・農地プラン』を農家減らしのプランにしない」では、『季刊地域』10号の取材の中で、人・担い手と農地の問題に格闘してこられた方々の考え方を聞く機会を得、その代表的な事例を掲載した。島根県・農事組合法人おくがの村代表・糸賀盛人さん、山口県・農事組合法人うもれ木の郷事務局長・田中敏雄さん、宮城県・農事組合法人KAMIX代表・近田俊樹さんである。3人ともに、農村集落全体の暮らしが立ち行くように、そこに住み続けられるように、むらと地域を守るための組織を考え実践してきた。JAが掲げる「個々の農家の及ばない部分を補い、地域内外の多様な諸団体と連携する新たな協同の実践」でもある。
ここで『〈歴史と社会〉日本農業の発展論理』の第3章「社会の規定性」を参照したい。そこには大正期農家小組合の歴史的性格とそれの新生農協への編入の経過が詳述されている。その概要は以下のようだ。
近現代日本において農業・農村現場が最も自己主張しえた大正時代、つまり、国家が前面化する「1940年体制」(戦時総力戦体制)以前は、国・社会・文明のあり方を問う多様な農村社会運動が巻き起こり、それらを農村振興へと結実させる努力が重ねられた時代であった。代表的には小作争議と農家小組合の運動で、農会が特に熱心にすすめていた農家小組合は、ほぼ流通過程の共同に特化した産業組合とは異なり「生産過程の共同」(生産創造)にとりくんだという点で注目すべき組織であった。市場対応を課題とした機能集団としての性格を帯びているという点では明治期の小組合と異なり、また自治的性格を確保しているという点では昭和期の小組合=実行組合とも異なっている。従来の「農事の改良」の機能に加えて「農業経営の改善」と「農家経済の向上」などに重点が置かれ、共同の力で農家経営の内延的拡大(現代の六次産業化)をめざしたものなのである。
その農家小組合の事業内容を見ると、共同作業などの労力調整、共同精米・精麦、品種改良、共同購入、耕地・水利改善、共同販売、農林産加工、養畜・養蚕、山林・竹林、福利増進など12事業にわたる協同活動が組織され、何らかの事業に取り組む農家小組合は滋賀県では1930年のはじめにはほぼ農業集落数に達するほどであった。
この農家小組合は、府県農会のリーダーシップに基づいて組織されたものではあるが、基本的にはムラの結合力に立脚しムラを単位とした農業組織化の動きであった。国の法律による強制力をもたず、戦時統制に入る前の「自主性」をもち得た時代のムラづくり運動ということができる。
この運動は鹿児島県農会が1896年(明治29年)に奨励策をとったのをさきがけとし、大正期までに44府県で進められ、農家小組合数は、近世藩政村の6万3000を超える約8万組合に及んだ。
その後、昭和恐慌期には農山漁村経済更生運動の実動部隊として動員されることになり、さらに1932年の産業組合法の改正によって、農家小組合は法人化されて農事実行組合となり、まるごと産業組合に編入されることになった。しかしそこでは農家小組合の自治的性格が強く生き続け、その結果「ムラと結合した協同組合」という、西欧とは違った「日本的協同組合」が形づくられることになった。
この農家小組合を源とする自主的なムラづくり運動こそ、「地域営農ビジョン」が受け継ぎ、手本とすべきものではないだろうか。
▲目次へ戻る
グローバル化時代の〈世界標準〉からの脱却
先に挙げた「JAグループの提言」の「提言の概要」では「(1)わが国がめざす持続的発展が可能な農業のあり方」を次のように描いている。
「わが国は、国土面積が狭く中山間地域が多いことから、米国など大陸型農業のように数百・数千ha規模の大規模経営は不可能である。わが国が目指すべき持続的発展が可能な農業とは、規模拡大や価格競争力のみを追求することではなく、各地域の集落や農地の実態に応じて、資源を最大限に活用する形態の農業を持続的に発展させていくことである。そして安心・安全な国産農産物に対する消費者・国民の信頼関係のうえに、農業・農村の価値観を共有することである」
これに対し、「(2)集落ごとの『担い手経営体』を中心とした水田農業の将来像のあり方」の項では「人・農地プラン」と同じ担い手像が描かれ、(1)項と両論併記のようになっている。しかしこれには、疑問を呈せざるをえない。上掲書の第1章「現代農業革命と世界農業類型」のなかで野田氏は概要、次のように述べている。
農業構造改革とは、多数の零細経営を淘汰し一部の大規模経営に置き換えること、創出された少数の経営体に政策的支援を集中しこれらの企業的経営体に産業としての農業をゆだねることである。二十世紀最後の四半世紀においてヨーロッパ(西欧旧開地)は食糧輸入地域から米豪(西欧新開地)に次ぐ巨大輸出地域へと復活した。その大転換をもたらしたものが、18世紀輪栽式農法による近代農業革命の成果のうえに、機械化・化学化(脱自然・工業化)を徹底させた農業構造改革(現代農業革命)であり、それが〈世界標準〉となって農業をめぐる世界政治を一新することになった。
その西欧型構造改革(現代農業革命)への適応力から世界農業をみると次の4つに区分できる。第I類型は「構造改革不要地域=西欧新開地型農業」、第II類型は「構造改革達成地域=西欧旧開地型農業」、第III類型は「構造改革不能地域=アジア地域型農業」、第IV類型は「構造改革未然地域=アフリカ地域型農業」である。
先住民を追い出し広大な耕地で新大陸型農業を展開してきたアメリカやオーストラリア(第I類型)、小農を早くから淘汰し、畜産、畑作を軸に規模拡大・企業的農業を進めた西欧(第II類型)に対し、日本そしてアジアは「構造改革不能地域」であり、それを認識しようとしない“思考停止”にこそ、1960年以降半世紀にわたる構造改革の試みが失敗してきた根本原因がある、ということだ。
構造改革「不能」とは、グローバル化時代に流布されている安直かつ傲慢な〈世界標準〉を正当に拒否するための宣言であり、先にみた「JAグループの提言」の(1)もその表明である。当然、提言(2)の「担い手経営体」もTPP推進派の「強い農業」論とは根本的に違ったものになるべきであろう。
▲目次へ戻る
「家とムラ」の存続のための「地域営農ビジョン」を
人と農地の問題は農政課題である前に、農家・家と農村・ムラの問題である。日本の「家」と「ムラ」がどのように成立しどんな特徴をもっているのか、そこから人と農地の問題を考えないと当事者不在のものになってしまう。
日本の伝統的な「家」や「ムラ」=共同体は、戦後西欧近代の理念的価値を基準に、「民主化」「近代化」の障害物として解体・克服の対象とみなされてきた。そしていま、「人・農地プラン」によって改めて問われていることは、日本の社会の基層にある「家」と「ムラ」=共同体を、グローバル化によってさらに徹底して解体する方向に未来を展望するのか、逆に、「家」と「ムラ」の復権、現代的に地域を再生する方向に新しい社会・経済を展望するのかの選択である。農家と農村に立脚するJAの「あらたな協同」「次世代へつなぐ協同」は後者でなければならない。
日本の伝統的な「家」と「ムラ」、家族経営(家族と家産)と村落共同体(コミュニティと地域資源)に深く刻まれたDNA・原理を復権させ、新しく現代的によみがえらせることこそが、JAグループの「地域営農ビジョン」策定運動でなければならない。�
(農文協論説委員会)
▲目次へ戻る
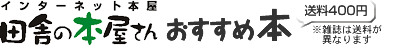
 |
この記事の掲載号
『現代農業 2012年10月号』
特集:畑の耕盤攻める守る
ヤマカワプログラムの現場/土ごと発酵で耕盤はどうなか/液肥を自分で作る2/苗に亜リン酸/太陽熱処理/ミミズ糞/緑肥活用でここまで減肥/肥料をうまくまく機械・道具/小ウネ立て播種/共生菌で、病気に強くなる、増収する/家畜糞+αで売れる堆肥・肥料/放射性セシウムとカリ肥料 ほか。
[本を詳しく見る]
|
 |
『季刊地域10号 2012年夏号』農文協 編 特集:「人・農地プラン」を農家減らしのプランにしない 季刊地域ホームページ
[本を詳しく見る]
|
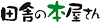
|