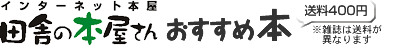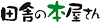反TPP これからの闘い方
新しい共同 新しい経営をつくる
目次
◆国際的な連帯も視野に入れて
◆闘いの主戦場は地域、新しい経営をつくること
◆むらの財産を守り継承する農業――新しい経営の基礎
◆二つの連携によって直売所の可能性をさらに広げる
去る11月13日、ハワイで開かれたアジア太平洋経済協力会議(APEC)首脳会議で、野田首相はTPPへの「交渉参加に向けて関係国との協議に入る」と表明し、究極の貿易自由化へ大きく舵を切った。反対派への配慮と低姿勢ばかりが報じられる首相だが、1987年、千葉県議時代に、「私は牛肉・オレンジの輸入自由化への反対決議に一人だけ反対した」という筋金入りの貿易自由論者であることを忘れてはならない。
▲目次へ戻る
国際的な連帯も視野に入れて
ギリシャ、イタリアばかりでなく先進国が共通に抱える金融と財政の危機、政治の混迷と民主主義的統治能力の喪失、メディアの翼賛的退廃は、第二次大戦後の、さらに言えば産業革命以後の近代的な国家・市場・社会の三位一体的枠組みが修復不可能なほど劣化していることを表している。TPPの中心にいるアメリカの強い意志は、日本市場の開放を足がかりに、最終的には中国を「国際ルール」に従わせる形で、アメリカ主導の「アジア太平洋自由貿易圏」を実現し、三位一体的劣化がもたらす景気と雇用悪化の回復を図ろうとするものである。
しかし、その道は国家間、地域間の、そして富める者と飢える者との一層の格差拡大と自然環境の破壊を進め、年金など社会保障の後退と増税によって地域と暮らしを疲弊させる道である。そして何より、東日本大震災・福島原発事故で被災された多くの方々の暮らしと地域の復旧・復興を妨げ意欲を削ぎ、被災者の尊厳を踏みにじるものである。
世界的な大激動・動乱の時代にすすめられるTPP問題、これは2012年の国会審議の最重要課題となるだろう。野田首相は11月15日の参院予算委員会で、「何が何でも、国益を損ねてまで交渉参加することはない」と答弁したが、何が「国益」かを明確にせず、反対派を適度にかわしながら、TPP参加を進めようとするにちがいない。これに対し、TPP不参加の政治決断を促すべく、今後は、米・牛肉・砂糖、保険(共済)、医療など、何を守るべきかを巡って、国会では批准阻止をも視野に入れて闘われる。しかし、この闘いを国会など政治の舞台だけにゆだねることができないのも、この間充分すぎるほど経験してきたことである。この新たな事態に対し、今後どのように闘いを進めていくか。
第一にTPPの反国民的・反国益の本質をいっそう明らかにしながら、TPP反対と大震災・福島原発事故からの復旧・復興支援、そして脱原発の闘いを連携して展開することである。直売所や地場産給食、グリーンツーリズムなど、これまで築いてきた消費者、都市民とのつながりも生かし、国民への働きかけを強めることである。
アメリカの目論みを鮮明にし、これを阻止するには、国際的な視点、国際的な連帯も必要になる。お隣韓国では米韓FTA反対運動が大変大きく盛り上がっている。「韓国は義務を負うが、アメリカは負わない」、「韓国の法律より韓米FTAを優先適用」など、いわゆる「毒素条項」といわれているものがしだいに明らかになってきたからである。
北米自由貿易協定(NAFTA)によってアメリカの新自由主義に翻弄され続けているメキシコでは、輸出補助金で不当に安いアメリカからの輸入トウモロコシへの依存を深めてきた結果、最近の値上がりが庶民の台所を直撃している。また、この輸入トウモロコシには遺伝子組み換え種が混在し、トウモロコシの発祥地・メキシコが誇る品種の多様性を破壊する遺伝子汚染が大問題になっている。そして農家は、輸出作物を生産する農業起業家か、さもなければ安価な労働力となるか、という二者択一を迫られている。
日本のためだけでなく、海外の農民を苦しめるアメリカに日本が手を貸す道は何としても阻止しなければならない。アメリカと多国籍企業による世界的な農業・地域破壊を阻止し、世界の地域・農民と連帯する闘い方が求められている。
その農家ならでは闘い方の核心は、担い手を企業的経営に絞り込み国内外の競争に駆り立てる「強い農業論」に惑わされず、各地に芽生えている地域の共同の力を活かした新しい経営を創出することにある。
▲目次へ戻る
闘いの主戦場は地域、新しい経営をつくること
新自由主義、グローバリズムの害悪の極限は地域と共同、そしてこれを根源から支える自給的世界の解体にある。自給的世界の解体によってあらゆるものを商品化・市場化し、経済活動(資本)の極大化を図るのがその本質的衝動である。自給的世界の解体は地域の自然と暮らしのつながりを断ち、労働力を地域から奪い、都市一極集中をすすめ、地域を衰退させ、格差だけが拡大する。
TPP反対の闘いは、わが国と山河、そして我々一人一人の仕事と暮らしを守るためのものであり、前述の三位一体的劣化による災厄を「地域の再生」によってはね返す道を切り拓く闘いである。自給的世界を回復し、それを基礎に生産と消費、産業と暮らし、自然と人間が調和する社会を蘇生し、創りだす闘いである。それを牽引する新しい地域の経営を創出しなければならない。
その新しい経営の萌芽は、すでに各地の農家の取り組みのなかに芽吹いている。「現代農業」に登場する三つの取り組み事例を次に掲げ、その実践のなかからどういう新しい経営が求められているのかを考えてみたい。
事例(1) 震災の教訓 輸入飼料依存畜産からの脱皮
�「飼料米自給でニワトリを一羽も殺さずにすんだ」(2011年 9月号)
青森県で、採卵鶏45万羽、養豚一貫生産の母豚550頭、そのほか果樹・野菜などの有畜複合農業を営む常盤村養鶏農協。3・11の大震災で、、太平洋側に集中していた飼料工場(八戸、石巻、塩釜)からの飼料の供給が1週間完全にストップした。飼料ばかりか停電で水を飲ませることもできず、これが続けばニワトリを殺すしかなく、しかも、それを処理する湯を沸かすボイラーも運搬するトラックも燃料がなければ動かず、という事態に遭遇した。
しかし、飼料供給が途絶え多くの家畜が犠牲になった中で、常盤村養鶏農協ではニワトリを1羽も、豚を1頭も殺すことなく、県内のスーパーや県外の各取引先への供給をストップさせずにすんだ。「今までの経営方針に大きな確信を持つことができた」と専務の石澤直士さん。この経営方針とは、輸入飼料依存の加工畜産からの脱皮をめざして、6年前から取り組んだ飼料米生産のことで、今では800haまで広がった。新たな発見もした。当初の玄米給餌を、塩2%添加のモミ米100%給餌に変えられる見通しが立ったことだ。生存率が高まることもわかった。
輸入穀物を飼料に使うことで日本の加工型畜産が成立してきた。その穀物は、輸出補助金によって黒字を保障された欧米の農業によってつくられてきた。
しかし、地球は人口70億人時代を迎えた。途上国の畜産製品の需要増、バイオ燃料化との競合、そして近年の気象災害や土壌劣化による不作など、輸入飼料の価格は高止まりすることはあっても今後下がることは見込めない。また、穀類の国際市場価格の低下を輸出補助金でカバーしている欧米諸国の財政赤字がそれを許さないだろう。
飼料イネの地域的生産・利用が広がってきた。飼料自給は、新しい経営の欠かせない課題になっている。
事例(2) むらの財産(田畑)を守り継承する農業
�「『集落内自給構想』を立ち上げた集落営農」(2011年 9月号)
集落内で自給自足構想を掲げ、地域の力を強めながら、災害時の備えまでしている集落がある。滋賀県米原市にある飯集落だ。その活動の牽引力となっているのが、「むらの財産(田畑)を守り継承する農業」を選択した農事組合法人・近江飯ファームである。飯集落は滋賀県東北部、琵琶湖のほとりに広がる田んぼ地帯にある、全110軒の小さなむらだ。京都まで電車で50分、大阪まで1時間半という立地で、ほとんどが兼業農家。田んぼの平均面積は3反ほどだが、最近は土日に気軽に田んぼをやるという人もめっきり減った。
このままでは集落の農業が崩壊するという危機感から六年前に集落営農組合が生まれ、2010年に法人化して、農事組合法人・近江飯ファームが誕生した。構成員は43名、耕作面積は28ha。
「集落営農やってると、自分たちのことは自分たちで守ろうっていう気持ちが強くなるんです」
代表を務める川崎源一さん(60歳)は、集落営農で何ができるのか、どこまでできるのか、その可能性に日々ワクワクしている。
そのひとつが集落内での米販売。「歳だからもうつくれない」という集落の人に「田んぼを守る代わりに、集落でできた米を買ってくれ」と頼んだのがはじまりで、今では飯集落の7割以上の80軒ほどが購入。520俵、金額にして860万円、販売総額の半分を占める米が地元需要にまわっている。年間一人当たり米の消費量が1俵の時代に一軒平均実に6.5俵を購入しているのだから驚きだ。親戚や友人に分けるほどの評判の米は、今は、むらの自治会に認められて備蓄米にも回されている。
もう一つの特徴はみんなで働けるための仕組みづくりだ。減農薬・減化学肥料のこだわり米は一回の除草剤のあと、女性たちが手取り除草する。イネの育苗ハウスを利用してメロン、トマト、イチゴをつくる。ジャムや漬物などの加工もする。それらはお盆に里帰りした人たちの手土産であったり、法事やむらの人の御遣い物に使われたりする。むら人の多様な需要に応える仕事興しによって、むら人がそれぞれに活躍できる集落をめざしているのである。
事例(3) 自給的世界に欠かせない山を取り戻す
「三本巣植えの森作り」� (2011年8、9、11月号)
「自分で製材、木の産直は楽しかよ〜」(10年11月号)
いち早く進められた木材の自由化、木材価格の低下で山の荒廃が進んだが、山をフル活用した暮らしづくりの新しい経営もあちこちで始まっている。
秋田市の佐藤清太郎さんは、天然林の植生をヒントに「三本巣植え」に取り組んできた。広葉樹を半分は切らずに残し、その間にポツポツとスギを3本ずつ植えていく方法で、経費3割減、労働力6割減。「農家は年間200万円あれば生きていける」というのが佐藤さんの口癖。目先の収入のために働くより、自分の森を市民や子どもたちに開放して森や木に親しんでもらう活動に燃え、野菜はわが家でつくるし、スギ林のなかでキノコや山菜を育てる立体栽培もお手のもの。自給自足と物々交換で金のかからない生活を楽しんでいる。
福岡県八女市の大橋鉄雄さん。「山は儲からない」などの声が渦巻くこの業界で、ちゃんと毎年黒字を出している。秘訣は、自分で製材し自分で売ること。これで売り上げ価格が丸太市場出荷の4〜5倍にも跳ね上がる。売り先は基本的には地元。本職の大工さんもいれば、倉庫を修理したい人、床を自分で張り替えたい人など、個人のお客さんもいる。買うほうからしても、大橋さんの木材は一般流通価格より安いので助かる。
山菜など食べものから薪、落ち葉、材木まで、自給的世界には、山が重要な役割を担っていた。50年、100年を見据えた森づくり、製材と販売の工夫、山を活かした交流活動、ここでも新しい経営が生まれている。
▲目次へ戻る
むらの財産を守り継承する農業――新しい経営の基礎
これらの事例に共通するのは、「利益追求型」ではなく、「むらの財産を守り継承する農業」である。
作物、家畜を育て、調理加工して食べ、廃棄物は土に還す。木を植え、森を育て、下草を刈り、間伐をし、薪を採り、炭をやき、山菜を採り山の恵みをフルに活用する。かつてあたり前にあったことを取り戻す農業。暮らしに必要なお金も稼ぎながら、そこにみんなで暮らし続けるための新しい経営づくりを進める。集落の暮らしの需要を掘り起こし、それに応える生産を興し、みんなで働く仕組みをつくる。「利益追求型」ではリストラが常套手段だが、「むらの財産を守り継承する農業」では多様なむらの人材が生きてくる。これを運営の基本におく集落営農は「社会的協同経営体」である。「社会的協同経営体」のもと、自然に働きかけ働きかけ返される労働によって、地域の自然・風土の個性もまた磨かれる。
新しい経営をつくるうえで助けになる新たな条件が生まれている。それは、大震災が生活者の心理を変えたことである。消費するだけの空虚な存在から確かな暮らしを自分の手でつかもうとする思いが都市の若者をボランティアに駆り立てる。震災以後、家族や地域の絆の大切さを感じ、むらにもどろうかと考える家族持ちの息子、娘が増えている、という話も聞いた。いろんな可能性が生まれている。
▲目次へ戻る
二つの連携によって直売所の可能性をさらに広げる
1970年代、50万円自給運動から始まった多品目の直売農業はまさに地域内需要に応える農業の筆頭である。
4半世紀前、直売所がこれだけ隆盛を誇るとは誰も想像していなかった。減反政策はあっても今日のように六次産業化を進める事業はなかった。戦後急速に進む農業の近代化の中で失われたもの、それは農家の自給であった。1966年、農家一戸あたりの自給率はすでに18%を切っていた。中央市場(外需)に向けた農産物販売で稼いだ金で買う生活が奨励され、味噌・醤油つくりはやめ、その代わりインスタント食品・保存料で長持ちする加工食品が食卓を占めた。その結果が米は九七%だが、野菜やダイズなどその他は数%という自給率の低下である。その取り戻しに農村女性が立ち上がり、これを土台に広がった直売所は、いまやセブンイレブンを凌ぐ17000カ所、1兆円産業に育っている。
この直売所は、以下の二つの連携によって、さらに大きな役割を担うようになるだろう。直売所の過当競争を心配するむきもあるが、直売所のもつ可能性は広く大きい。
一つは、「むらの財産を守り継承する農業」を実践する集落営農=新しい「社会的共同経営体」との連携である。地域内需要を掘り起こす基礎エリアは集落(自治会)であり、販売農家だけでなく自給農家・土地持ち非農家が混住しているのが今の集落である。一般家庭の年間食料需要90万円のうち米・パン・麺類など穀類と野菜・果物で30万ほど、つまり乳肉を入れないで100世帯エリアで3000万円ほどの潜在需要がある。この地域内の需要に応える生産創造を集落営農が担い、集落内自給を基礎に産直、直売所を一層盛り上げていく。
もう一つは地域の商店街との連携である。日米構造協議による改正大店法の成立した1991年以降、従業員50人以上の大規模店が急速に増え、24時間営業のコンビニも着実に増えていった。それと裏腹に商店街のシャッター通り化がすすみ、旧中心市街部の空洞化は全国の中小都市に拡大した。その商店街の持つ施設・機能の活用・再生に農家や集落営農が一緒になって取り組む。直売所、産直による地元商工業の活性化である。
この新しい連携によって地元に雇用、仕事を増やす。こうして、先に述べた田舎暮らし志向の若者が活躍する場、都市で暮らす地元出身者がもどれるような仕事、地域産業を興す。「地域の再生」の中心的な課題がここにある。
*
繰り返すが、TPPは人類の生存環境、いのちと暮らしの基盤をことごとく破壊するところにその本質がある。これを許すことはできない。
2012年は闘いの年になる。闘いの年にしなければならない。自給的世界を基礎にした農業、新しい経営、新しい共同、地域づくりの豊かなイメージを膨らませ、歩みを進め、国民的な理解を広げながら、闘い抜きたいと思う。福島や被災地の農家・農業、漁家・漁業を「食べることで支えていく」消費者を巻き込んだ取り組みも大きく広げなければならない。そこから未来が拓ける。
(農文協論説委員会)
▲目次へ戻る
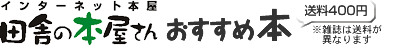
 |
この記事の掲載号
『現代農業 2012年1月号』
特集:農の仕事は刃が命
包丁・ナイフ/ハサミ/刈り払い機/チェンソー/ケイ酸で超多収/挿し木苗の不定根を活かす/果樹の夢のような仕立て/直売所が後継者を育てるしくみ ほか。
[本を詳しく見る]
|
 |
『TPPと日本の論点』農文協 編 特設サイト
[本を詳しく見る]
|
 |
『TPP反対の大義』農文協 編 本書では、TPPへの参加がとりわけ暮らしを支える農林水産業や地方経済に大きな打撃を与え、日本社会の土台を根底からくつがえす無謀な選択であることを明らかにし、TPPに反対する全国民的な大義を明らかにします。
特設サイト
[本を詳しく見る]
|
 |
『異常な契約』農文協 編 オークランド大学教授ジェーン・ケルシー氏による『No Ordinary Deal』の邦訳『異常な契約 TPPの仮面を剥ぐ』
[本を詳しく見る]
|
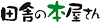
|