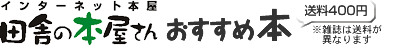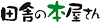「強い農業」論を批判する
世界に広がる「食料主権確立運動」と日本農業、農家の大義
目次
◆『TPP反対の大義』の健闘が示すもの
◆“開国と農業の両立”の歴史的ウソ(または無知)
◆“強い農業”の源は他人の不幸
◆農業強国アメリカの“不都合な真実”
◆食料の国家主権と国民主権を統一する
▲目次へ戻る
『TPP反対の大義』の健闘が示すもの
先月号の当欄でも紹介したブックレット『TPP反対の大義』(農文協刊、840円)の売れ行きが好調だ。昨年末に発行した初刷り1万部はあっというまに在庫が払底、急遽2刷り7千部を増し刷りしたが、毎日押し寄せる注文に間に合わず、2刷りが出来上る前にさらに1万部を増刷、それでも足りず4刷を刷り、計3万2千部に達した。
TPP(環太平洋経済連携協定)をめぐっては政府首脳と大メディアが連日「バスに乗り遅れるな」の大合唱をくり広げ、今もそうしているが、民主党内非主流派や自民党の一部を含む少なくない野党の「慎重に」という声はほとんど無視されたも同然だった。TPPのような国の将来を左右する重大問題は、たとえ自社の社説と見解が違っても多様な意見を幅広く収集し、少数意見も含め可能な限り公平に論点提示し、もって国民的議論の俎上に乗せるのが言論、報道機関の役割のはずだが、この国の大メディアは総じて時の権力の翼賛機関と成り下がったようだ。
このブックレットが、「硬い」本の割に発売20日足らずで3万部を超えた勢いなのは、このような、この国の偏った情報流通に対する人びとの健全な批判精神が健在であることを示している。同時に、その当否は別として、焦点に据えられている食料農業の行く末に農家以外の人びとも幅広い関心を寄せていることが窺えることを示している。
TPPは、農業に限定してひとことで言えばわが国食料農業を米豪に差し出すものであり、さらに先にはWTOのTPP化、即ち全世界の農業強国に自国の農業を明け渡すものに他ならない。そんな危険な事態を冷静にみる眼と批判精神が失われていないことを、本書の健闘は示している。
▲目次へ戻る
“開国と農業の両立”の歴史的ウソ(または無知)
こう書いてくると、「だから強い農業で開国と両立を」という菅直人首相や取り巻きの声が聞こえてくるが、――例によって“キャッチフレーズ先行”で中身を言わない (じつは無い?)ので推測するに――首相のいう「強い農業」とは、象徴的、究極的にはアメリカやオーストラリアの農業を指すのであろう。TPPが事実上、日米、日豪のFTA/EPAである以上、論理的にはそれ以外ありえないからだ。09年農地法改正にもまだご不満で、一般法人への農地所有権が解禁されていないのが日本農業のネックだと公言し(昨年11月14日、APEC終了後の議長記者会見)、家族経営やその協同経営体たる集落営農への冷たい視線を隠そうとしない姿勢からもそれは明らかだ。
かくして、開国しても米豪に負けない、輸出できるような農業になれればなんの問題もないではないか、というのが菅首相の言い分になる。しかしここには、歴史に学ぶことを知らない2つのウソ、ないしは無知がある。
第1に、開国、開国と首相は言うが、明治の開国は、こと貿易と関税に関していえば幕末以降の不平等条約を粘り強い交渉によって廃棄・改正し、関税自主権を勝ち取った開国だったことをお忘れか?(1907年「日露新通商航海条約」、1911年「日米通商航海条約」など)。関税自主権を放棄させられるTPPとは真逆のことをやったのだ。それを「第3の開国」と言い立てるのは歴史に対する不遜というものである。
そもそも関税とは、自然的、歴史的、社会的諸条件を異にする各国各地域が貿易を通じて交易する際も一方が他方を押しつぶすのでなく、共にその便益を享受できるよう工夫された人類の叡智の一つである。著名な経済学者であり上記ブックレットの著者の一人でもある宇沢弘文氏(日本学士院会員・東大名誉教授)は次のように述べている。
「ベトナム戦争の全期間を通じてアメリカ軍がベトナムに投下した爆薬量は、第2次世界大戦中を通じて全世界で使用された量のじつに3倍を超えている。その上、ダイオキシンを大量に散布して森林を破壊し、すべての生物の生存を脅かす枯れ葉剤作戦を全面的に展開した。30年以上経った現在でも農の営みに不可欠な役割を果たす森林という大切な社会的共通資本の破壊は深刻な傷跡を残している。
(中略)他方アメリカは、イギリス植民地時代から何世紀にも亘って、先住民族の自然、歴史、社会、文化、そしていのちを破壊しつづけた。アメリカの農業は先住民族から強奪した土地を利用して行なわれている。(中略)しかも一方では巨額に上る公的資金が、農業に関わる社会的共通資本の形成、維持に年々投下されている。
このような極端な対照を示すベトナムとアメリカが農産物の取引について、同じルールで競争することをよしとする考え方ほど社会正義の感覚に反するものはない。
アメリカとベトナムほど極端ではないが、同じような状況が世界の多くの国について存在する。このことが、現行の平均関税の格差になって現れている。各国は、それぞれの自然的、歴史的、社会的、そして文化的諸条件を充分考慮して、社会的安定性と持続的な経済発展を求めて、みずからの政策的判断に基づいて関税体系を決めているからである。理念的にも、理論的にも全く根拠をもたない自由貿易の命題を適用して、すべての商品に対する関税の実質的撤廃を『平成の開国』という虚しい言葉で声高に叫ぶことほど虚しいことはない」(宇沢「TPPは社会的共通資本を破壊する」『TPP反対の大義』所収)。
かくして農業の場合、関税撤廃=開国に反対することはいわゆる「業界エゴ」などではないことをハッキリと確認しておきたい。農業が、それなくしては成り立たない各国各地域の気候、風土、土壌条件、総じて自然というものは、絶対に輸入も輸出もできないからである(できるのだったら“開国”しても良いが、そうなったら貿易する必要がそもそもなくなる)。
▲目次へ戻る
“強い農業”の源は他人の不幸
菅内閣の第二のウソまたは無知=強い農業論に移ろう。
米豪のような、輸出もできる強い農業にということの非現実性、どころか反倫理性は、右に引用した宇沢氏の論述ですでに半分答えが出されている。米豪の、日本やアジアと異なる隔絶的大経営は、その出発点からして「先住民族から強奪した土地を利用して」成り立ったものだった。国じゅう地平線が見える広大な大平原という自然、地形条件がそれを後押しした。対して日本はどうか――。
「子供のころにならった小学校唱歌の『汽車』(作者不詳)の第一節は、
今は山中、今は浜 今は鉄橋渡るぞと
思う間も無くトンネルの 闇を通って広野原
であった。
日本の風景が、山と海と川、そしてなにがしかの山麓の平坦地で構成されていること、それらが繊細に入り組んでいることがよくわかる。そして日本の水田稲作は、この海と山と川の恵みを享受しているのである」(育種学者の故角田重三郎東北大学名誉教授『新みずほの国構想』1991年、農文協)。
ここには、小学校唱歌を引きあいに出しながら、日本の水田稲作農業が、日本の地形や自然総体と関係をもちながら〈場〉として成り立った状況が見事に描かれている。
「思う間も無く」次々変わる風景。それは、地形が急峻で大平原もなければ巨大な川もなく、地形、したがってまた土壌も「繊細に入り組ん」だ複雑多様な日本の自然の特徴をひとことで表わしている。このような自然条件のもとで、日本のそして大部分のアジア諸国の、水田稲作を土台に据えたむら(集落)と家族小農経営は成立した。それは土地生産性よりも労働生産性、したがって絶えず粗放的・外延的拡大を求めずには発展できない「小麦(ないしトウモロコシ)+牧畜」農業とは根本的に違う、山川海と調和的依存関係をもった循環的農業であり、小力を生かした精耕細作、園地的精農主義農業であった。
ひるがえって米豪、とりわけアメリカの農業はどうか。その「強さ」は宇沢氏も指摘する、出発点における「強奪」によって成立しただけではない。戦後の圧倒的政治、経済、軍事力をバックに多くの国々、とりわけ途上国の食文化と農業を侵略的に改造、変質させたことによってもたらされた「歴史的所業」の所産である。
戦後冷戦体制のもとアメリカは、食料援助をてこに被援助国の食料消費・生産構造をアメリカ依存型につくりかえた。1960年代、途上国が食料危機に見舞われると世界銀行やロックフェラー、フォードなどの財団資金を動員し「緑の革命」を推進。途上国農業を化学肥料、農薬、単一作物の品種・種子に依存する農業につくりかえ、危険分散、内部循環性の高い持続的農業を破壊した。それら資材を買える農家とそうでない農家の貧富の格差を拡大、かつ病害虫に弱いため農家経済全般を不安定化した。80年代以降グローバリゼーションの時代になると緑の革命の借金を含む累積債務を返済させるために、世界銀行やIMFの管理下、経済社会全般にわたって「構造調整プログラム」を強要、農業においては自給的穀物生産の農業から外貨獲得のための輸出換金作物への特化=モノカルチャー農業への転換を押しつけ、それらの国々を事実上多国籍アグリビジネスの支配下におさめた……。
今や途上国とはいえないメキシコでさえ、「NAFTAで主食のトウモロコシ生産農家が潰れ、米国から安く買えばいいと思っていたら、こんどは価格暴騰で輸入も困難な事態に追い込まれてしまった」(鈴木宣弘・木下順子「真の国益とは何か」、前掲『TPP反対の大義』所収)。
このようなアメリカの「強い農業」のもと、96年、FAOが途上国を中心とする当時の飢餓人口八億人を2015年までに半減させると採択した「ローマ宣言」から15年、飢餓人口は減るどころか 9億2500万人になると予測されている(FAO、2010年9月14日発表)。
かくしてアメリカの「強い農業」とは、第1に 「新天地」で先住民から強奪した“呪われた出生の秘密”をもち、したがって第2に純粋に農業の力そのものによるものではない、いわば経済外強制によって手に入れたものであり、第3に途上国の不幸をつくり、あまつさえそれを踏み台にして獲得してきたものにほかならない。かかる「強い農業」は、菅首相の願う「最小不幸社会」の政治哲学とどう「両立」するのだろうか。
▲目次へ戻る
農業強国アメリカの“不都合な真実”
アメリカの「強い農業」の負の側面は、ほかならぬアメリカ自身の問題としても暗い影を落としている。農村政策無き農業政策にアメリカ農民も呻吟しているのだ。
直近の米国農業センサスである07年農務省報告によると、年間100万ドル(当時約1億1300万円)以上の農産物を販売する超大規模企業農場数は全農家戸数の2.6%にすぎないがその販売額は全体の59%を占めている。片や5万ドル(560万円)未満の農家は総農家数の78%を占めるがその販売額は全体のわずか4%を占めるにすぎない。極小農家ともいうべき販売額1千ドル未満農家は全農家数の31%に達し、その割合は前回02年センサスより21%も増えた。ほとんどの農家は兼業収入と政府の補助金がなければやっていけない実状にある。こうして「アメリカ農業の二極化は極端な水準にまで達している」(薄井寛『2つの油が世界を変える―新たなステージに突入した世界穀物市場』2010年、農文協)。
アメリカの農家戸数は1935年681万戸をピークに07年には220万戸まで減ったが、右の二極化と農家総人口の減少により地域コミュニティは衰退、家族経営を母体にした古き良き農村社会は風前のともしびにある。農村政策無き農業政策、産業としての輸出農業=独占的アグリビジネス大企業栄えて農家滅ぶアメリカ農業農村の苦悩がここにある。
農村部だけではない。超農業大国でありながら日々の食事に事欠く人びとが都市に大勢いるのも、アメリカのもう一つの姿である。アメリカ農務省の予算のじつに67%、891億ドル(約7兆4千億円)ものお金が低所得者向けの「フードスタンプ」(食料購入費補助制度)や学校給食費補助に充てられており、その対象人口はフードスタンプ4030万人(10年度)、給食補助を受ける子3100万人(09年度、上記薄井氏「世界の窓」JC総研)、あわせて全人口のじつに23%に及んでいる。農業強国アメリカの"不都合な真実"とでもいえようか。
かくしてアメリカの「強い農業」とは“貿易のための貿易、そのための強い農業”に他ならず、国内低所得者や多数の農村農民を置き去りにした、一握りの多国籍アグリビジネス巨大企業の横暴の別表現にすぎない。このような「強い農業」は、「最小不幸社会」の実現と到底相いれない。
▲目次へ戻る
食料の国家主権と国民主権を統一する
――世界の農民組織「ビア・カンペシーナ」の運動
内外に不幸と軋轢をまきちらす「強い農業」の横暴に、各国、各地域民衆の「食料主権」を対置、確立しようという運動がおこっている。
そもそも、アメリカを中心とした多国籍・超国籍アグリビジネス巨大企業が「強い農業」の論理を“合法的に”世界に押しつけるべく創設したのがWTOでありその農業協定だったが、この協定は、輸入国には国境措置の開放と生産刺激策を禁じる一方、輸出国には不作時や国内穀物価格の抑制を優先するための輸出禁止は認めるという「二重原則」を特徴としている。
しかし、そもそも食料不足の時に自国民の食料確保を優先するために輸出を制限、禁止するのは輸出国といえど当前のことで、その国の食料主権というものだ。であるならば輸入国も、輸出国の主権の行使で不測の事態に陥らぬよう日頃から食料自給率を高めるよう努力するのもこれまた当然の主権の行使である。しかるにWTO農業協定は輸入国がとる自給率向上策をことごとく市場・貿易歪曲的として退ける。かくして国家間の食料主権はWTOを前提としては目詰まりを起こし、機能不全に陥っているのが現状だ。
このような状況を打破すべく登場したのが「ビア・カンペシーナ」を中心とする、下からの食料主権確立運動である。「ビア・カンペシーナ」(農民の道)とは、世界68カ国、148組織、2億5千万人の小農を結集する世界的農民組織で、ガットURが大詰めを迎えていた1993年に創立された。
その基本目標は「農業の工業化と輸出に重点をおいた新自由主義的モデルに抵抗するため、各国農村組織の多様性を尊重しつつ連帯と団結を強めること」であり、「食料主権」を、「すべての国と民衆が自分たち自身の食料・農業政策を決定する権利である」と定義し、(1)地域の農業生産を優先し、国内生産と消費者を保護するため輸入をコントロールする、(2)生産コストとリンクした農産物価格を保障する、(3)貿易よりも国内・地域への食料供給を優先する、(4)輸出補助金付きのダンピング輸出を禁止する、(5)伝統的な種子を大事にし遺伝子組換えや工業的農業から食品の安全を守る、(6)土地改革の徹底、女性の権利の確立、等々の実現をめざしている(真嶋良孝「食料危機・食料主権と『ビア・カンペシーナ』」村田武編著『食料主権のグランドデザイン』[シリーズ地域の再生第4巻]農文協)。
これは、多国籍企業や大国、国際機関の横暴を各国が規制する国家主権と、国民が自国の食料・農業政策を決定する国民主権を統一した概念であり、また、どこで、誰が、どのように生産した食料かを問わずに、とにかく食料をあてがえばいいという方向を打ち出したFAOの食料主権を超えたものである。世界の農家が大同団結して国を動かし、国際機関を動かし、多国籍アグリビジネスの「強い農業」の横暴に歯止めをかける運動に、大いに期待したい。
折しも米豪、カナダ、ロシア、ウクライナ、アルゼンチンなど世界の穀倉地帯が軒並み豪雨、干ばつに襲われ穀物・食料価格が高騰し始めている。08年に続くこの高騰は単に天候不順による一時的なものでなく、需給の構造的逼迫が背後にあることを多くの識者が指摘しており、穀物価格高騰から穀物・食料危機へ転化する可能性は決して低くはない。そして大量の食料、飼料輸入を担保した日本の貿易黒字は1986年をピークにじりじりと減り続けている。威勢のいい「強い農業」論に惑わされず、世界の農家と連帯し水田活用新時代、自給と直売を土台に据えた地域コミュニティ再建の年にしたい。�
(農文協論説委員会)
▲目次へ戻る
こちらもご覧ください
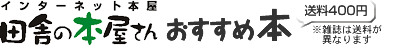
 |
この記事の掲載号
『現代農業 2011年3月号』
農家の必需品 軽トラ活用術
今年は一等米を!/「日本のパン」が焼きたい/TPP反対特集 第二弾/モミガラくん炭覆土/スイートコーン・エダマメ発芽名人になる/ジャガイモの種イモの切り方と株間/茶園の霜対策/草で搾る/初めての溶接 ほか。
[本を詳しく見る]
|
 |
『TPP反対の大義』農文協 編 本書では、TPPへの参加がとりわけ暮らしを支える農林水産業や地方経済に大きな打撃を与え、日本社会の土台を根底からくつがえす無謀な選択であることを明らかにし、TPPに反対する全国民的な大義を明らかにします。
[本を詳しく見る]
|
 |
『2つの「油」が世界を変える』薄井寛 著 穀物貿易に迫る規模へ成長した燃料生産農業と中国など新興国の食用大豆油の需要急増で世界の食料貿易は全く新しいステージに移行した。その最新動向とそれに対峙する市民と農業の再接近、食のローカル化の潮流を描く。
[本を詳しく見る]
|
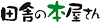
|