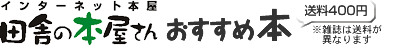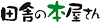どうみる 米の「生産調整廃止」論議
縮小路線を排し、「水田フル活用」を
目次
◆言い古された農業攻撃=「朝日」の俗論
◆生産調整廃止は、財界が農業に送り込んだトロイの木馬だ
◆直接支払いは農家経営を守るか
◆生産調整の大義
◆穀物消費の長期的視野に立って
◆「減反廃止論議」が無視する3つのこと
米の生産調整をめぐる議論が沸騰する中、またも大マスコミの不見識な論調が出始めている。「朝日新聞」6月9日付社説は「農政改革 先送りする余裕はない」と題して次のようにのべている。
「日本の農業は崖っぷちにある。総生産額は縮小を続け、いまは年間8兆円余り。パナソニック1社の売上高と肩を並べる程度しかない。食糧自給率は40%と、主要先進国の中でも際だって低い。日本の農業をここまで弱らせた最大の原因は米価を維持する目的で政府が続けてきた減反政策にある。生産者保護の名の下に計7兆円もの税金をつぎ込んで生産を減らし、消費者に高いコメを買わせる一方、コメ作りへの意欲と工夫を農家から奪った」。その結果、「1ha未満の稲作では最低賃金の半分以下の時給300円程度しか稼げない」農業になってしまった。だから「処方箋ははっきりしている。減反政策をやめることだ。コメの生産量が増えて米価が下がれば、需要を上向かせる機会となろう。農家所得は減るが、減反につぎ込んできた予算を所得補償制度に回せば解決の道は開ける」と締めくくっている。
農業の総生産額とパナソニックの売上高を並べて前者の「低生産性」を嘆いてみせる手法は「日経」5月19日付「経済教室」山下一仁氏の「農業ビッグバン 今こそ」の書き出しと全く同じで、その「わかりやすさ」は朝日の社説氏もよほど気に入るところだったのだろう。だが、「わかりやすさ」と「俗論」は紙一重。断片的、象徴的なことがらを脈絡なしにつなぎあわせ、俗耳に入りやすい「理論」に仕立て上げた謬論であることが少なくない。
▲目次へ戻る
言い古された農業攻撃=「朝日」の俗論
まず、「家電」と「食糧・農産物」という、使用価値も生産のされ方も全く異なる2つのものを同じ土俵に乗せてその生産額や売上高の多寡を比べるのはいかなる意味があるというのか。命の糧であり自然、気候、風土の制約を免れない食糧=生命生産と、安い土地と労働力を求めて自由に移動できる家電=無機生産とを比べその優劣を論じるのは、ナンセンスというほかない。
このように、ほんらい比較すべきでないものを比較して意味のない小理屈を立てるのは、それぞれの国の歴史や風土、文化を無視し、お互い自分の国で高くつく産業はやめにして、安くあがる国にまかせましょうという、かの有名な比較生産費説の最も粗雑な理解に基づく謬論であり、こうした経済合理主義・市場原理至上主義の誤りは今時の金融・経済危機、グローバリズムの破綻という形で余すところなく実証されたところである。
減反に「7兆円もの税金をつぎ込んで」「消費者に高いコメを買わせ」て「日本の農業をここ(自給率40%に)まで弱らせた」というのも難癖だ。「7兆円もの税金」と鬼の首でもとったようにいうが、この金額は減反39年間では1年当たり1800億円、1億2800万人の国民1人1日当たり3円85銭にすぎない。わずか4円足らずの費用で暴落から米生産を守り、むらと水田、技術の継承も守り、もって、せめて米だけは100%自給できてきたのである。安い国民皆保険料といわず何と言おう。しかもここ数年は、米価の下落で「時給300円」で提供していただいているとしたら、「申し訳ない」と思うのが普通の人間の感覚というものだ。
「高いコメを買わせて」というのでついでに付言すれば、現在日本国民は1人当たり年間消費量61.4kg(2007年度確定値)の米を60kg当たり平均1万4000円で農家から買っていることになる。その1年当たり金額は1万4327円、1日当たり39円25銭にすぎない。4円に満たない「保険料」と合わせ43円で日々の主食が確保できているわけで、その支出構成比は格差社会の底辺で暮らす例えば年収200万円の単身者にとっても年0.8%、比較的裕福な?年収600万円の4人家族でも1.05%でしかない。農家の懐には入らない流通マージン等を入れた現在の実勢店頭価格平均2万2000円(10kg3670円)からみても、上記数字はそれぞれ62円、66円、1.2%、1.6%である(公租公課控除前)。
このような米価を「高い」と難じるのは、不効率な米作農業は白旗を掲げて安い外米に明け渡せと言うに等しい。いや、言外にそう言っているのである。「減反をやめ」「生産量が増えて米価が下がれば」、次項で述べるように輸入拡大の道はおのずと開けてくる。そのとき「上向」いた需要の少なくない部分がより安い外米志向となって顕在化し、輸入増大やむなしの世論形成に利用される危険は、都市勤労者所得の低迷ないし下方圧力が強まっている現在、容易に察せられるところである。コスト削減を追求する食品・外食業界や、「高関税の逓減による内外価格差の縮小を求め」、事実上日本農業への決別宣言を出した日生協(日本生活協同組合連合会)の動向はその危険をより現実のものにするに違いない(日生協「日本の農業に関する提言」2005年5月)。
▲目次へ戻る
生産調整廃止は、財界が農業に送り込んだトロイの木馬だ
このような事態が危惧される今、生産調整廃止とそれに伴う農家所得減の万全な代替策であるかのように喧伝される「直接所得補償」に過大な期待を抱くのは危険だ。それは07年から08年末にかけておこなわれたWTO交渉の経緯を、生産調整廃止→直接支払いとの関連で見てみれば明らかである。
日本はインドや中国を始めとする新興工業国の工業分野の関税引き下げを主要な獲得目標に設定し、それがかなえられ、あるいは見通しが立つなら、自国の農業関税を引き下げるのもやむを得ない、という姿勢で臨んだ。
そのため関税を高く設定できる「重要品目8%」(最初は10%だった)という「譲れない線」をさしたる交渉努力もせず原則から外し、「原則4%+代償付き上乗せ2%」というラミー事務局長裁定案に、「ないし4%」という“上乗せの上積み”を図る線に主張を切り下げ、もって「8%は守った」と胸を張った。しかし、これは国内向けの強がりでしかなく、実際はインド、中国の、想定を超える工業関税分野の引き下げへの抵抗をまのあたりに見て、日本の主目的を達成するには農業で「譲歩」するしかない、農業関税の引き下げとミニマムアクセス米の増大は避けがたいと「観念」したことをあらわしている。
かくして日本政府は日本の農業を守るより、それを犠牲にして財界主導の、クルマを始めとする輸出依存型殴り込み的経済構造の懲りない拡大再生産路線を選んだ。
中断した交渉はこの秋から再開される見通しとされているが、以上の延長線上で関税が引き下げられていけば外米の輸入増大は必至で、いくら生産調整をつづけても国産米が減った分は外国産が埋め、下がった米価にサヤ寄せして関税も下げやすくなるのでさらに外米が増えていく。
つまりは、もう今までのような高率の関税で米を守ることはできない。生産調整は効果がなくなっていく。ならばいっそのこと生産調整は廃止し、米価が下がった分は直接補償すればいいではないか――。
02年「米政策改革大綱」時から目標にされ、ここへきていよいよ実施に向けての動きが強まった生産調整廃止・直接支払いへのお膳立てと筋立てはおおよそ以上のようなものだ。まさに、財界が農業農村に送り込んだトロイの木馬である。だからこれは、生産調整のやり方仕方やそれに伴う農林予算の組み替え等、農政内部の技術的レベルの問題ではなく、世界と関わる日本のあり方、その中で自国の、ひいてはそれぞれの国の農業をどう位置づけるのかが問われる、「この国のかたち」(司馬遼太郎)にかかわる基本問題なのである。
▲目次へ戻る
直接支払いは農家経営を守るか
生産調整廃止・直接支払いはそのような文脈に位置づけられているが故に、農家経営と水田農業を守る道ではない。
第1に、当たり前のことだが国内生産縮小の道である。
第2に、そのように縮小していくプロセスの中では、直接支払いといってもその水準や絶対額は年々切り下げられていく恐れが十分ある。下がった分の補償といってもスタート時の米価や総生産量を基準にした差額が将来にわたって補償される保証はないのである。
第3に、そもそも直接支払いには生産費のような客観的な根拠がなく「恩恵的」であり、かつ担い手経営安定対策や産地づくり推進交付金のように過去3年平均の下落幅の8割とか5割を補填するにすぎない、所得補償とは名ばかりの「激変緩和策」にとどまる可能性もある。
第4に、すべての稲作農家に補償されるのかも定かでない。新基本法第30条は「農産物の価格の形成と経営の安定」を定めたものだが、その第2項には次のように書かれている。
「2 国は、農産物の価格の著しい変動が育成すべき農業経営に及ぼす影響を緩和するために必要な施策を講ずるものとする。」(傍点引用者)
国が施策を講ずるのは「育成すべき農業経営」、すなわち「望ましい農業構造」(21条)を担う「効率的かつ安定的な農業経営」(同)であって、すべての農業経営ではない。そしてこれは、ほんらい全販売農家のセーフティネットであるべき価格変動対策が構造政策の手段にすり替わってしまったものといわざるを得ないのである。
また、関税引き下げは避けられないという前提に立つ限り、「効率的かつ安定的な農業経営」そのものも危ういのは明白だ。あるいはまた、もし仮に輸入だらけになり農業で働く場が大幅に減った状況でなお「恩恵的」な所得補償を受け続けるのは、それを潔しとする人はいないだろう。
▲目次へ戻る
生産調整の大義
問題の出発点は減反・生産調整を100%年々達成しても「過剰」が解消しないことだった。しかし生産調整を廃止すれば事態はもっと悪化する。需要と供給が食い違う可能性は、生命と天候を相手にする農業においてとりわけ高く、いくら緻密な計画を立ててもピタリいくものではない。農業生産とはそういうものなのである。その上、一つの商品の生産に200万近くもの経営主体が携わっている商品は米をおいて他にはない。だからこそ過剰基調のときは入り口と出口双方での調整が欠かせず、その全体的な大枠は公共的な視野に立ったマクロな立場(一国レベル→←むらレベル)で行なうほかない。生産調整のこのような役割を軽視し過剰→暴落→関税引き下げをより容易にし、結果、不足しているわけでもない米やその他農産物の輸入を増やし世界食糧危機の悪化に手を貸すのは人の道に反する。
稲作農家の「76%が生産調整の役割を評価」し(「日本農業新聞」6月3日付)、JA全中が「生産調整は今後も必要不可欠」(同5日付)としたのは、かかる生産調整の大義に立った、高い立場からの判断なのである。国はこのような声に謙虚に耳を傾け、輸入拡大に途を開く愚策・悪政=生産調整廃止の模索をきっぱりやめるべきである。
関税引き下げ合戦で互いの農業や産業をつぶし合うのが能ではない。多様な農業の存在を認めあうこと、がそれぞれの「国のかたち」をつくる基本なのである。
▲目次へ戻る
穀物消費の長期的視野に立って
主食用米の「過剰」で、減反が水田面積の四割にも達しているが、「世界史的にみれば穀物需要は増える方向に向かっている」という東京大学大学院教授の谷口信和氏の興味深い研究を紹介しよう。
谷口氏は、1800年代半ば以降今日までの長期にわたるアメリカ、ドイツ、日本、およびそれら3国を含む21カ国の最近40年間の穀物と肉類の国民1人当たり年間消費量の推移を詳細に分析し、大要つぎのように述べている。
1920年代(昭和初期)にピークを迎え20世紀末に50%台に低下した日本人の穀物消費量は下げ止まりのきざしを見せており、先行した米独同様、21世紀には増大局面に入ることが予想される。それは、動物性たんぱく質摂取増加からその飽和に接近し、遅くない将来に再び食用米を中心とするでんぷん質の1人当たり消費量が増加する局面に入る可能性があることを示唆している。
ところでアメリカとドイツを始めとする欧米先進国は、食用と同時に、自らの風土的条件に見合った穀物の飼料化にも成功し、そうした両面からなる総合的な穀物自給基盤の上に20世紀食料問題の解決に成功した国である。日本でそれに当たるのは水田?転作?作物たる飼料米しかなく、また輸入飼料チッソ負荷の軽減や農地の過半を占める水田維持・多面的機能の発揮という観点からも湛水栽培できる飼料米が最適だ。食用と飼料用を合わせた米生産全体の飛躍的拡大とその棲み分けが今後の最重要課題である。(谷口信和「農業生産構造の変化と政策転換―米政策改革をめぐって」2004年度農業経済学会報告2、ほか)。
実際、低落の一途を辿ってきた日本の米消費量だが、それを1965年(昭和40年)以降10年ごとの減少量平均で見てみると、2.2kg、1.3kg、0.8kg、0.6kgと漸次下げ方をゆるやかにし、直近3年はゼロである。03年以降5年間は61kg台を底割れせず、07年にはわずかながらも増加に転じ、08年も堅調だ(農水省「食料需給表」各年、総務省「家計調査報告速報」)。
いま必要なのは、基調転換ともとれるこの動向を視野におきながら、水田という優れた機能を主食用米だけに発揮させるのでなく、「穀物の日本的総合活用=水稲の食用+飼料化」の確立に向けた「水田フル活用」の展望を地域から拓いていくことである。
07年度補正予算で手当てされた米粉・飼料用米助成金は3年契約で反5万円だったが、09年度予算では年5.5万円に引き上げられた。それ自体はいいのだが、先駆的に取り組んだ農家は反当たり11.5万円も「不利益」を被ることになった。このようなネコの目で農家に「様子見」を強いる場当たり政策では1500万トンにものぼる輸入飼料穀物の自給化への途は遠くなるばかりである。
農家は自給率を上げるために経営を営んでいるわけではない。しかし、両者が一致しベクトルが同じ方向を向くのが望ましいのはいうまでもない。世界的、長期的視野に立ったしっかりした制度政策設計が望まれる。
▲目次へ戻る
「減反廃止論議」が無視する3つのこと
ところで、「朝日」の社説に象徴される米に関する議論には一面的な、あるいは意図的に無視していることが3つある。一つは、「食料」のみを問題にし、農業農村、それを担っている農家はどうでもよいという発想であり、2つめは、規模の大小にかかわらずこの間農家がさまざまに進めている工夫や取り組みを無視していること、そして3つめに、「イネ+兼業」という形で多くの農家が米つくりと田んぼを守ってきたことの軽視である。
農家の米つくりへの情熱と村うちでの助け合いによって日本の米も田んぼも守られてきた。むらとむらの田んぼを守るために減反を受け入れるという「大義ある妥協」もしながら、米つくりへの意欲と工夫を維持してきた。
90年代以降は、新食糧法やWTO発足という新たな環境のもと、米の産直や直売所による販売、地場産米給食などを次々広げ、あるいは麦、大豆、米粉利用による「地産地商」の動きをつくり出してきた。耕畜連携による「堆肥栽培」でおいしい米をつくり、フル活用する水田の地力を維持する取り組みも進んでいる。飼料米も、こうした農家の工夫と連携があってこそ定着する。兼業農家が助け合う集落営農も各地につくられた。
大きい農家も小さい農家も含む、あるいは連携したこれら総体の農村の営みがあってこそ安心安全な食料の確保につながり、多面的機能の発揮にもつながる(注)。国籍を問わない、モノとしての食料が確保できればいいというものではないのである(注:その意味で新基本法の基本理念を列記した第2条から5条は順番が転倒していると言わざるをえない)。
いま農村は、長らく続いた「安定兼業」の社会的条件が揺らぐなか、地域から産業を興し新たな雇用と定住条件を創造すべき新しいステージに立っている。農家農村の資源と経験を生かし、定年帰農組や新たに農村をめざす若者の新しい感覚も結合し地域の産業・仕事興しに取り組む。視野狭窄の生産調整廃止論議にかまっている暇はない。
(農文協論説委員会)
▲目次へ戻る
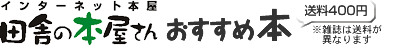
 |
『むらを楽しくする生きもの田んぼづくり』 3年目に入る「農地水環境保全向上対策」は正念場を迎える。本書は先進的な取り組み事例はもちろんだが、実践していくうえでの具体的な技術(草刈り、アゼ管理に、田んぼを豊かにする魚道づくり、水路補修など)に重点をおきながら、農業の基盤となる田んぼや水路や用水などの維持・管理や環境保全、そこから始まる新たな地域づくりへの技術も紹介する。美しい景観も含めて、豊かな田んぼは地域の宝物に変身し、「食農教育」の場ともなって、子どもにも親にも元気が戻ってくる。
[本を詳しく見る]
|
 |
『転作全書 第4巻 水田の多面的利用』農文協 編 産直・加工、市民との連携・・新しい水田利用の具体例を詳しく紹介。
[本を詳しく見る]
|
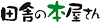
|