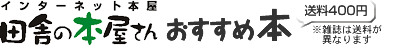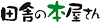「地エネ」時代がはじまった
農家がエネルギーの主になるとき
目次
◆電気を自分で生み出す楽しみ
◆電気は「遠くからやってくるもの」か
◆固定価格買取制度は誰のために
◆地エネにぴったり、小水力発電
◆地域のおカネが回っていくしくみを
◆農家が「エネルギーの主」となることから
7月1日に固定価格買取制度がスタートし、再生可能エネルギーによる発電が俄然脚光を浴びている。メガソーラーや洋上風力発電など、大規模な再エネ発電事業に大手企業が目の色を変えて参入している。固定価格買取制度では、太陽光発電なら42円(1kWh当たり)、風力なら23.1円といった高単価で電力会社が電気を買い取ることが義務づけられており、しかもその価格は一度契約すれば10年とか20年といった決まった期間保証される。企業にとっては確実に投資を回収し、収益を上げることが見込める「おいしい事業」だ。血眼になるのは無理もない。
そうした大企業の派手な動きの一方で、この制度を機に各地の農家や地域の団体がコツコツと再エネ発電をはじめている。「農地・水・環境向上対策事業」を担ってきた集落の任意組織や土地改良区が農業用水路を使って小水力発電をはじめたり、田んぼの法面にパネルを並べて太陽光発電をしたり……。
本誌の兄弟誌である『季刊地域』11号はこうした地域(地元)のエネルギー=「地エネ」の動きに注目し、特集を組んだ。そこには、大企業の再エネ発電とはちがって、電気を売ることはもちろんだが、「自分たちが使う電気(エネルギー)は自分たちでなんとかしたい」という農家ならではの発想がある。
▲目次へ戻る
電気を自分で生み出す楽しみ
岐阜県中津川市付知町に住む口田哲郎さん(78歳)は自分の家で小水力発電をはじめて、かれこれ10年以上になる。会社を退職した2001年に親戚の倉庫に眠っていた小さな水車をもらってきて増速機やバッテリー、インバーターを接続、屋敷内を流れる水路に据えつけ、20Wの電灯をともすのに成功したのがそのはじまりだ。
もう少し本格的な水力発電をやってみたいと思っていたところ、本誌2002年3月号、4月号に石田正さんの「小型小水力発電入門」という記事が掲載された(注)。さっそく連絡をとり、協力を快諾した石田さんと二人三脚で「口田水力発電所」の建設がはじまった。愛知県在住の石田さんは電気の保守管理が本業で、そのかたわら小水力発電を各地に普及するために発電施設の製作実験を精力的にすすめてきた人だ。一方、下水道工事を仕事にしていた口田さんは土木工事はお手のもので、農業用水路から発電用に取水するタンクや発電機を据えつける建屋の敷地をユンボで整地したり、岩を砕いたり、タンクと建屋をつなぐ水圧管(塩ビ管)を据えつけたりといったことはすべて自分でこなした。2002年12月には早くも水力発電機1号機が稼働。落差は15m、塩ビ管の総延長は70mにもなった。現在は、石田さんが改良を重ねた発電機が2機稼働していて、出力は合わせて600Wくらい。建屋には太陽光発電用のパワーコンディショナーを備えつけて、2機が発電した電力を直流から家庭用の交流の電力に変換し、品質を調整している。
口田さんはさらに2005年に5kWの太陽光パネルも自宅の屋根に設置。こちらは家庭用で消費して余った電気を中部電力に売っている。ついでに、水力発電の電気も余った分を買い取ってもらおうと思ったのだが、いまのところそれは認められていない。だから「口田水力発電所」で起こす電気はすべて自家消費用として使われている。
わざわざパワコンまで設置して水力発電の電気の品質を調整しているのに、その電気を電力会社に買ってもらえないというのは傍目には不本意な状態だとも思うが、口田さんはさほど意に介していない。口田さんの家では観光ブルーベリー園を経営しており、3台あるストッカーや観光客のためのトイレなどを含めて、電気の使用量が多い。家族も高校生、中学生の孫3人を含む7人の大家族だ。こうした電気のかなりの部分を水力・太陽光発電でまかなって節約しているうえに、太陽光発電の余った電力を月2万円程度売っている。消費分を差し引いても月6000円程度のプラスになる。
そして、なにより「発電所」は口田さんに毎日の張り合いをもたらしている。毎朝農業用水からの取水口にごみがたまっていないか見回り、発電機が調子よく動いているか、その音に耳を澄ます。保守管理を怠らないだけでなく、「取水タンクの防塵装置をどう改良しようか」といった工夫を重ねるのが、楽しいのだという。
電気をつくるのは、同じ「つくる」といっても農家が米や野菜、漬物や味噌などをつくるのとはわけがちがうかもしれない。しかし、ちょっとした気象の変化や川の増水、川を流れてくるものの変化に気を配り、自然にいつも問いかけているという意味では、水力発電も日々の農家の営みに通じるものがあるのではないだろうか。「地エネ」とは地域、地元のエネルギーであるとともに、農家の日常感覚の延長にある「地に足のついた発電」といえるかもしれない。
▲目次へ戻る
電気は「遠くからやってくるもの」か
いま、ほとんどの人にとって電気は、どこか遠いところで生み出され、勝手に流れてくるものになっている。電気との関係は月々届く「電気使用料のお知らせ」に印字された数字だけ。「電気を自分でどうにかできるなんてとんでもない」とすっかり思いこまされている。しかし、かつては、とくに農村では、そうではなかったのだ。
口田さんのむらでも戦前、戦中のころ集落に小さな水力発電所があり、当番の家が見回りに行くきまりになっていた。幼い口田さんも父親に連れられて、水車にごみがつまっていないか、提灯を下げて見に行った。口田さんが自力でミニ発電所をつくろうと思ったのも、その記憶が残っていて、家で使う電気は自分でまかなう――せっかく山の中に住んでいるのだからそんな暮らしをもう一度復活できないかと思ったからだという。
明治から大正にかけての電力の黎明期には農山村に小水力発電所がさかんにつくられたし、戦後も高度経済成長期の前半までは、大都市や工業地帯の大電力需要は別として、農村の小電力需要は地元で供給しようという動きがあった。1952年には議員立法によって「農山漁村電気導入促進法」が成立、通産省は売電方式による小水力発電の規制を緩和し、農林省は農林漁業金融公庫から元利均等償還25年の優遇措置で、農村に対し建設費の80%を貸しだすことになった。以降、1967年までに建設された小水力発電所は、全国約200カ所にのぼった。その半数が中国地方であり、建築ラッシュの中心となったのは各地の農協であった。しかしその後は、石油による大規模火力発電が電力事業の中心となり、小水力発電は下火になっていく(『季刊地域』7号「60年前から農協発電を支える水力発電メーカー・イームル工業」)。
とはいえ、現在でも中国地方では農協などが経営する70kWから600kWの小水力発電所が54機も動いている。
固定価格買取制度を機に、こうした地域に密着した発電の歴史にもっと学ぶべきではないか。
▲目次へ戻る
固定価格買取制度は誰のために
というのも、固定価格買取制度のメリットを大企業だけが享受しているようでは、たとえ電源の比率が火力・原子力から再エネに多少シフトしたとしても、電気を一部の企業が握るしくみそのものは変わらないからだ。
固定価格買取制度で対象となる電源は太陽光、風力、地熱、中小水力、バイオマスの5種類。買取価格(1kWh当たりの単価)と期間は国によって毎年見直されるが、契約時点の価格が適用され続ける。また、少なくともこの3年間は現状程度の高い価格が維持される見通しだ。どうせはじめるならいまのうち。ソフトバンクや丸紅など、これまでエネルギーと直接縁がなかった大企業がこぞって再エネ発電に乗り出したのは、そのためである。
再エネ発電に急速にシフトするために大企業の参入を促すことは必要なことではある。しかし、そもそも東京電力福島第一原子力発電所の事故の被害があれだけ拡大した根本原因のひとつは、大規模集中型のエネルギーシステムであり、電気を専門家まかせにしてきたことではなかったか。大企業だけに電源開発を頼っていたのでは、「電気はどこか遠くにあって、知らないうちに届けられるもの」という関係そのものは変わらない。
固定価格買取制度を大規模集中型エネルギーから地域分散型エネルギーへの転換のきっかけにしていくためには、地域の資源を集落や地域に密着した組織が生かして発電する「地エネ」がもっともっと伸びていかなければならない。
▲目次へ戻る
地エネにぴったり、小水力発電
そうした「地エネ」のなかで、どの地域にも可能性があって、もっと注目されていいのが小水力発電である。小水力発電は太陽光発電に比べてハードルが高い印象がある。たしかに太陽光発電ではすでに太陽光パネル、パワコンなど、メーカー製の汎用品が普及しており、それらの設備をセットで購入すれば、技術的にも手続き的にも系統連系(発電設備を電力会社の配電線に接続して運用すること)して余剰電力を売電するところまで、わりあいスムーズにすすめることができる。小水力発電の電力を売るのはそれほど簡単ではない。系統連系に際して、配電線につないだときのリスクを極力なくすという理由で、電力会社が発電者に対してさまざまな設備を求めるからだ。しかも太陽光発電や風力発電の設備に合わせて技術要件がつくられているため、小水力発電の専門家から見ると不合理な点も多いという。
では太陽光発電や風力発電にくらべて小水力発電が割に合わないかといえば、そんなことはけっしてない。晴天の日中以外は効率がぐんと落ちる太陽光発電や、風が吹かなければ電気が起きない風力発電の設備利用率は12%前後といわれる。これに対して小水力発電なら年間の水量の変化を加味しても65%程度の設備利用率を見込むことができる。年間の発電量に換算すると小水力発電は太陽光発電の約5倍。固定価格買取制度の単価を当てはめて70kW規模の発電所で試算すれば、太陽光発電の売電収入が年間約300万円に対して、小水力発電では約1400万円と、約4.6倍になる。小水力発電はたしかに最初はおカネがかかり、手続きも少々面倒だが、建てるところまでもっていけば断然有利なのだ。
豊富な水量と落差をもつ河川が流れ、各地に農業用水路がはりめぐらされた日本には、小水力発電所をつくる可能性がまだまだある。日本とドイツを比較すると、3万kW以上の大水力発電所は日本がドイツの4倍あるのに、1000kW以下の小水力発電所はドイツの約5000カ所に対して日本は約500カ所と10分の1しかない。可能性がありながら開発が進んでいないのが、日本の小水力発電なのだ。
▲目次へ戻る
地域のおカネが回っていくしくみを
集落単位で小水力発電をはじめるなら、最初から大きくやるよりも、まずは外灯や電気牧柵などの小規模な利用で試験してみて、農産物直売所や加工施設への電力供給(20kW程度)へ、さらに売電(50〜70kW以上)へというような段階を踏んでいくといい。九州大学の島谷幸宏氏はこうした3段階のステップアップを提唱している。
そうなると問題は初期投資をどうするかだ。小水力発電の設備投資は1kW当たり150万円が目安といわれている。かりに50〜70kWの小水力発電所をつくるとなると数千万円〜1億円程度のおカネが必要だ。首長による公益性の担保、固定資産税の減免などの行政の支援を受けるとともに、市民ファンドの創設や信用金庫、第二地銀などの地域の金融機関との連携によって、できるだけ地元から資金を調達したい。金融機関の側から見ても、再エネ発電事業は単価が保証され、初期投資の回収の見込みがはっきりしているのだから、しっかりした事業計画さえあれば担保なしでも融資は可能であるはずだ。そうすれば、発電事業で得られた売電収入は地域にとどまり、さらに再投資されることで、地域経済の発展に寄与することができる。地域に密着した金融機関の代表であるJAにはぜひ、ひと肌脱いでほしいところだ。
『季刊地域』11号では京都大学の諸富徹氏が、みずからかかわっている長野県飯田市の例を紹介している。飯田市では市民出資による太陽光市民共同発電の仕組みを軌道に乗せ、中心市街地再生と熱供給、バイオマスエネルギーの地産地消、小水力発電の可能性についても調査研究をすすめているという。
固定価格買取制度では、電力会社にとって割高な価格を維持するためのおカネは、電気消費量に応じて月々の電気使用料金に加算する形で利用者から徴収される(「再生可能エネルギー発電促進賦課金」)。国民から広く浅くおカネを集める一方で、そこで得られる利益を広く地域に行きわたらせる仕組みは制度として担保されていない。資本力のない地域の個人や小さな組織が事業に参加でき、エネルギーとともに地域のおカネが地域内で回っていく仕組みを、自治体や、JAを含む地元金融機関に働きかけながら、自分たちでつくっていかなければならない。そういう動きはいま各地で起こっている。
▲目次へ戻る
農家が「エネルギーの主」となることから
ここまで小水力発電を例に見てきたが、農家が中心となる「地エネ」は小水力発電にかぎるものではないし、発電にかぎるわけでもない。電気を自分たちの手で生み出すことをきっかけに、動力や熱供給を含むエネルギー全体の地域自給を見直したい。
もともと日本の農家は水車を利用して粉をひき、用水路の水を田んぼに揚げ、山の木から薪や木炭を生み出し(木質バイオマス利用)、堆肥の熱で温床をこしらえていた(バイオ熱利用)。いまこそ、そういう「地エネ」の伝統を、現代の技術水準を取り入れて生かすときではないか。
ドイツでは畜産農家が家畜糞尿と飼料の残りでバイオガス発電を行ない、肥料や熱としても利用したり、林地残材をチップ化してボイラーで燃焼させたり、牧草地に市民風車を設置したりといったことが、いまさかんに行なわれている。2000年に固定価格買取制度が施行され、再エネ発電が伸びるとともに、電気や熱エネルギーの主権を再び地域が取り戻しつつあるというのだ(『季刊地域』7号のドイツ在住の池田憲昭氏のレポートによる)。その中心となっているのが、もともとドイツで「土地の主」と呼ばれ、最近では「エネルギーの主」とも呼ばれるようになった農家である。
日本の農家にも「エネルギーの主」となる資格は十分にある。まずは自分の家、むらのエネルギー資源を見直してみたい。
そこでは今のようすだけでなくかつての姿――古い発電所はなかったか、といったことも、大いに役立つ情報になる。ひょっとして、まだ使える導水路や水圧管だって残っているかもしれないのだ。
むらを流れる河川や用水路の、どの箇所に年中水が流れていて、どこに落差がとれるか、農家であればすぐにわかるはずだ。さらにむらの年寄りから、かつて水車がどこに設置されていたかを聞きとってみると、よい情報が得られるだろう。まずは、水や林地残材、オガクズ、モミガラ、家畜糞といった地域の資源を見直すことから、「エネルギーの主」への第一歩がはじまる。
それは相変わらず電気を「遠いもの」にしておき、自分たちの都合で原発再稼働を言いなりにできるといまだに信じている、巨大な電力会社から自由になる第一歩でもある。
(農文協論説委員会)
(注)�このときの石田正さんの記事「小型小水力発電入門」は、『農家が教える自給エネルギー とことん活用読本』(農文協)に収録されている。
▲目次へ戻る
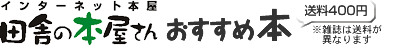
 |
この記事の掲載号
『現代農業 2012年11月号』
特集:無敵のマイハウス
痛快! 手作りマイハウス/風・雪に強くする/上手に補修する/ビニール張りをうまくやる/油代節約、ハウスの保温術/田んぼの菜の花の悩み解決/アスパラ茎枯病を秋冬管理で防ぐ/イチジクのびっくり新技術/初産牛を上手に搾乳に慣らす/身のまわりのもので農家エステ/集落営農の経営を考える ほか。
[本を詳しく見る]
|
 |
『季刊地域11号 2012年秋号』農文協 編 特集:地エネ時代 農村力発電いよいよ 季刊地域ホームページ
[本を詳しく見る]
|
 |
『季刊地域7号 2011年秋号』農文協 編 特集:いまこそ農村力発電 季刊地域ホームページ
[本を詳しく見る]
|
 |
『農家が教える自給エネルギーとことん活用読本』農文協 編 3.11の大震災・原発事故以来,「節電」がアピールされて巨大かつ集中的管理の脆さが露見し,自然エネルギーに対する社会の態度は変わりつつある。しかし,大方の議論は国家的なエネルギー政策という観点から,「電力」を中心に再び新たな巨大インフラが話題に上る。しかし,そこからだけでは未来は拓けない。本書は,身の回りに眠っているエネルギーを暮らしに活かす,小さなエネルギー自給のさまざまな面を楽しく描き出す。人任せのエネルギー議論から一歩先に進むための,エネルギー自給実践の書。
[本を詳しく見る]
|
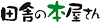
|