脱原発の大義
――地域破壊の歴史に終止符を
目次
◆美しい農山漁村に原発は無粋だ
◆事故の前から原発は地域を壊してきた
◆原発にしがみつかざるを得なくさせる財政構造への変質
◆昭和恐慌期「東北振興事業」にみる国家と財界の地域破壊
◆耕すことで農は復興への可能性を拓いた
▲目次へ戻る
美しい農山漁村に原発は無粋だ
「計画的避難区域となった荒れた農地を見ると心が痛む。耕して種を播き、豊かな稲穂を稔らせた水田を見ると、なんと美しい光景かと感じる。…春の山菜と鏡のような水田、初夏に羽化してひらひらと舞い、秋には黄金色の稲穂に番いで帰る赤とんぼ。紅葉に果物…。この美しい農村の原風景は農民の営農の連続によってつくられてきた。
美しい風景と環境をつくってきたのはまぎれもない、林業家であり、農民であり、漁民である。この第一次産業を守り育てることが環境を守り、持続可能な社会をつくることではないだろうか」。
本誌とほぼ同時に発売される農文協ブックレットの新刊『脱原発の大義』に、執筆者の一人である福島県の農家・菅野正寿さんはこのように書いてくださった。「耕して種を播き」「営農の連続」によって受け継ぎつくられてきた美しい風景と環境、それが「持続可能な社会」の土台であり、私たちの普通の暮らしの基盤でもあることを気負わない言葉でのべていて、すがすがしい。被災した、苦難の只中からの言葉であることを思うと、なおさらだ。
漁家や林家も含めた生業の連続とその結晶としての美しい風景と環境、持続可能な社会の土台=「地域」。それらを根底から破壊し、あまつさえ事故の検証も終わらぬうちに再稼働に踏み切ろうとする政府・財界、電力資本。清々しさとは対極の、なんと醜悪な光景であろうか。
当会は、このような原発推進勢力の邪な精神と強権的行為を断罪し、「原発の本質は地域の破壊」(本誌昨年6月号「主張」)であることをより明らかにするため上記ブックレットを発行、広く国民全体に訴えることにした。その企画趣意書は次のようにのべている。
1 �原発は地域社会、地方経済の破壊者であることを明らかにする。
そのすべてが貧しい海辺の寒村に建てられた原発は、その地域を電源三法交付金等「麻薬」に依存せざるを得ないアリ地獄の経済構造に変え、無機質で非自立的なむらまちに貶め、日本社会を宗主国(都市=政官財学原発複合体)と植民地(原発立地農漁村)に分けてしまった。その利益と繁栄は国家と都市、原発メーカー死の商人と電力資本がこれを享受し、そのいのちと暮らしの不安と危険、ふるさと喪失の無念は農山漁村がこれを請け負わされた。この不条理を満身の怒りを込めて明らかにする。
2 �“移動できない民”に寄り添ってふるさと再建、日本社会全体の再構築を展望する。
移動できない民=大地から離れては仕事にならない農家、海を汚されては“陸に上がった漁師”になるしかない漁家の立場に立って原発の地域破壊を根底から告発する。
この期に及んで、日本がダメなら輸出で稼ぐとうそぶく政府、財界・原発企業=“移動できる資本”の反国民性、天をも恐れぬ反人類史的不道徳を糾弾し、農林漁家が安心して生きいき働ける環境を取り戻すこと=脱原発こそすべての国民の安全、安寧の途であることを明らかにする。
消費者の不安は、農林漁家の、現実の甚大なる被害の従属関数であり、後者が根底から解消されることこそ真の解決の途であることを明らかにする。そしてその道づくりは、農漁家そのものがそろそろと、しかし確かに、気丈に取り組み始めていることを明らかにする。
3 安全性論議を超えて地域力への普遍的認識を!
原発そのものの安全性論議に巻き込まれず、地域の力、日本の豊かなエネルギー資源の再発見、利活用で危機を突破する道筋を明らかにする(それを忘れ、安全か安全でないかの議論にのみ「熱中」するのは危険だ)。――
こうした企画の趣旨に上記菅野さんを始め多くの学者、研究者、農家、生協関係者の賛意を頂き、それぞれの立場からその趣旨を具体化し、「脱原発の大義」を豊かに展開していただいた。以下、ごく一部だがそのエッセンスを紹介しながら“脱原発と農山漁村の大義”を明らかにしたい。
▲目次へ戻る
事故の前から原発は地域を壊してきた
第一に、なぜ原発の本質は地域破壊なのか。それは原子力発電所というものが、(安全性の問題を抜きにしても)そもそも地域では裾野の広がりをもたない「産業」であり、従って地元の雇用も少なく、それどころか立地地域の農商工、土建業などをさびれさせていくマイナスの作用と構造をもった産業だからである。原発に不安を覚えながらもその再稼働に地域経済の望みを託す関係者も少なくない中、これは、しかと確認しておきたい論点だ。京都大学大学院教授の諸富徹氏は次のようにのべている(以下、引用はすべて上記ブックレットより。一部圧縮、省略等している)。
「原発は燃料棒を他からもってきて、原子炉で発電し、さらに送電線で電気を県外に供給するための施設です。つまり地域の産業構造との連関性を全くもたないところに特徴がある。原発を誘致しても、そこから産業が広がるという方向性が展望しようがない施設なのです」。
しかも原発は、「点検業務その他である程度の雇用は発生しますが、運転そのものは中央制御室で少人数でなされます。稼働を止めて定期点検をする際には多くの人手が必要となりますが、定期的な雇用を生むものではありません。したがって同規模の投資をしたときに発生する雇用効果としては小さい」のである。そこで地元を納得させるために電源三法交付金などのお金をドンドン注ぎ込むのだが、それによって潤うのは後述する立地自治体の財政問題同様一瞬で、失うもののほうが非常に大きいのである。
「それは、地域経済がこの交付金に依存をしていく構図がほとんど不可避的に創り出されてしまうということです。
まず、農業サイクルと原発の建設サイクルが全く違う。農閑期に原発建設に従事し、農繁期にはそこから農業に戻ることができればいいのでしょうが、そうはならない。ですから、いったん人手として建設現場にかり出されると、労働力が原発に奪われてしまい、まず兼業農家が淘汰されてしまう。
それから原発建設とそれに伴う事業についても、地元には非常に専門化された高度な技術要求を請け負えるノウハウがないので外部から都市の企業がやってきて仕事をとるのですが、彼らは原発の建設が終わった後も地域に残り、地元の細かな建設事業も奪っていくそうです。さらには人の問題があります。原発が雇用する労働者は多くはないのですが、しかし比較的高給で商店街や地元企業の優秀な人材を奪っていく。こうしたことが複合して、地域経済は自立とは全く逆の方向へ曲げられてしまうのです」。
こうして、本来あったはずの地域の内発的発展の芽が摘み取られ、地域の人的物的資源が原発に総動員されることにより、地域経済が土台から崩されていくのである。
さらに追い打ちをかけるのが立地自治体の財政問題だ。
▲目次へ戻る
原発にしがみつかざるを得なくさせる財政構造への変質
「(電源三法など)こういった交付金を一度受けてしまうと、財政構造が強烈な依存型へと変わってしまうのです。交付金自体が外部から箱物投資のためにくるものですから、まずは色々な公共設備をつくっていく。例えばコミュニティーセンターやコンサートホールですね。どれも非常に立派で美しい建物ですが、年間数千万円の維持費がかかりますから、とても事業収入だけではペイできず、残りは全て一般会計からの持ち出しになってしまう。さらに下水道や道路建設などの公共事業も一挙に進め、その維持管理コストも跳ね上がってしまう。こうして歳出構造が硬直化し、高止まりしてしまうのです。
一方、収入のほうは…原発の完成によってこれらの事前交付金は廃止あるいは大幅に縮小され、その代わりに現れるのが固定資産税です。しかし一般のビルと同様に、償却をしていくのに従って不動産価値は減少していきますから、固定資産税も目減りしていく。約10年で半分以下に減ってしまいます。
ですから、歳出構造を原発の建設期、あるいは建設直後に合わせて固定化してしまうと、歳入が全く足りなくなってしまう。そこで、さらなる原発増設によって減ってしまった交付金と固定資産税収入を再び回復させ、高水準の歳出を賄うという選択を取ってしまうことになる」。
かくして原発は、ある種、依存の再生産構造であり、麻薬の常習を強制させられるようなものなのである。諸富氏はこのようにのべ、自転車操業のように次々に新たな歳入源を求めては見返りに原発を受けいれざるを得なくなっていく構造、いったん受けいれてしまうと抜け出せない原発は、地域発展の手段としては邪道であり逆効果であることを明らかにした。
同時にしかし氏は、こうした構図が「あたかも原発立地地域が自発的に原発依存を選んだ」結果であるかのように描く一部の軽薄な論調を批判し、「原発を受けいれた地域が、受けいれざるを得ないような状況にするインセンティブが様々に働いていた」こと、そうした構造を「都市に住む私たちがその半面を担っている」にもかかわらず「都市の側は責任を問われず、しかも生活の近くに原発があるというリスクを回避できる構図になっている」ことを指摘することも忘れてはいない。こうしたことに無自覚な都市民が少なくないことに自戒と反省を訴え、その上で、地域の力に依拠した脱原発の具体的方途を種々検討、提言、原発の、“終りの始まりが始まっている”ことに確信をもとうと呼びかけている。
▲目次へ戻る
昭和恐慌期「東北振興事業」にみる国家と財界の地域破壊
昭和30年代以降、国策民営ですすめられてきた日本の原発政策は、以上のようにして地域を破壊し続けてきた。しかし、国家と財界によるこうした地域破壊は今に始まったことではなく、歴史的にくり返されてきた根深いものであることに注意が必要だ。同じく京都大学大学院教授の岡田知弘氏は、次のような歴史上の事実を明らかにした。
時代は昭和初期、恐慌によって疲弊していた東北地方が昭和六年と九年に冷害凶作、8年には昭和三陸大津波に襲われ、自然災害が重くのしかかった時期である。
「東北振興会の陳情運動もあり東北救済の世論が高まるなかで、…東北振興事業が国策として推進され」ることになった。しかしその真因は、「東北の農漁民の救済や東北と他地域との格差是正にあったわけではなく、むしろ日中戦争が開始されるなかでの国家総動員資源政策の一環として位置付けられたことにあった」。これは、「国家総動員機関である内閣資源局の局長と東北振興事務局長を兼ねた松井春生が、率直に語っているところである。彼によれば、『東北振興は、単に東北の為の振興のみでなく、日本帝国の為の振興であ』るとし、『東北振興の要諦は、まさに、斯の如き其の域内に包蔵する人的・物的資源の利用開発を企図し、以て国力の開展に貢献するに在らねばならぬのである』と言い切っていた」。
事実、中央大資本が「金属鉱山開発から農畜水産加工業にいたる多方面の事業に参入する」が、戦況が悪化するに従い、軍需生産が優先されることになり、「当初理念として掲げられた東北農民に安価な化学肥料を配布することにはならなかった」。さらに、「東北興業株式会社の出資先の多くが三井系の重化学工業資本」であり、また、「東北振興電力には三井、三菱財閥が出資するとともに、東京電燈(現・東京電力)から複数の課長職が派遣された」が、その結果は、地元には仕事もこなければ電気の恩恵に浴することもできない、惨憺たるものだった。
「近時、奥入瀬発電所工事ニ関シ、東北各地業者ハ大イニ憤慨致居ル実例ヲ仄聞シ、東北振興ノ見地ヨリ甚ダ遺憾ニ存候、切ニ望クハ両会社工事施工ニ当リ、是非共地元業者ヲシテ御下命ノ恩恵ニ浴セラルル様、御詮議賜ハランコトヲ重ネテ要望候也」(福島商工会議所)。
「東北振電ガ出来テ以来開発サレタ電力ノ大部分ハ福島県デアルガ、其ノ三分ノ二ハ、東京地方ニ送電サレテ東北自体ニ使ワレルモノハ僅カダ。将来半分ダ何割トハ言ワナイガイクラカ地方ニ残シテ貰イタイトイウ希望ガアル」(川越丈雄東北興業株式会社総裁)。
かくして東北救済を名目に進められた「振興」事業は、「雇用効果は少なく、むしろ大量の労働力や物的資源、電力エネルギーが東京に向って流出する構造が形成され」た。ちなみに、1936年から42年の間に、東北各県から78万人の人口が他県に移動、流出したと岡田氏はのべている。
こうして、戦時期に形成された東北と中央との関係は戦後から現代に至るまでほとんど相似形で再生産され、再び電力、エネルギー、食糧、水、人の東京への供給地としての性格を強めていく。その延長線上に、福島県浜通り地域への原子力発電所の集中立地が位置したのである。こうした構造はなにも東北に限ったことではない。全国至る所の地方と中央、農山漁村と大都市の関係に当てはまることは言うまでもない。
だから、復興を目的に、あるいは一般的に地域振興を考える際、「外国や東京等の被災地外に本社機能をおく資本を誘致したとしても、あるいは原発に代わる大規模自然エネルギー生産拠点を誘致したとしても、それが直ちに被災地の持続的な復興・復旧に結びつくことにはならないことは、歴史が明らかにしている点であ」り、「被災者が主体として直接関わる地域内再投資力の再建」を「被災者の生活領域」すなわち「農山漁村では集落や昭和旧村の広がり、市街地では小学校区」を基本にしておこなうことが必要だ。岡田氏はそうした方向でチャレンジし始めた実際の例を各地に訪ね、紹介しつつ、その基盤となるインフラストラクチャの再建をバックアップすることこそ、国や地方自治体の本来の役割であることを強調している。
▲目次へ戻る
耕すことで農は復興への可能性を拓いた
原発による地域破壊の歴史と現状をみてきたが、そんな中にも一条の光明が見えてきた。「耕すことで農は復興への可能性を拓いた」――そう報告してくださったのは茨城大学名誉教授の中島紀一氏である。氏は冒頭に紹介した農家・菅野さんとも親交のある研究者だが、不安を覚えながらも耕すことをやめなかった農家の営みが希望をつないだと、大要つぎのようにのべている。
「収穫物に放射能がどの程度移行しているかは本当に心配だったが、実際に測定してみると放射能はほとんど検出されないことが判ってきた。各地のデータを集めてみるとND(検出下限値以下)かそれに近い低濃度の数値が並んだ。…昨年水稲の作付けが行政的に抑制された南相馬市で、作付け禁止の行政指示に納得せず、有機稲作を実行した安川昭雄さんという八五歳の老農家の田んぼの放射能は7月段階で8777ベクレル/kgだったが、収穫した米の放射能は54ベクレル/kg、移行率を計算すると0.006であった。…3月の原発事故による田畑の深刻な放射能汚染という事実の中で、これは信じられないような嬉しい事実だった」。
そして中島氏は、耕すことによって放射性セシウムは、容易には動かない状態になり、作物にはわずかしか移行しない状態がほぼ普遍的につくられ、それには科学的根拠があることがわかってきたことを紹介したうえで、「福島の復興を考えたとき、この事実の意味はたいへん大きい」とし、次のようにむすんでいる。
「不安の中で、道も見えないままに、それでも農の営みとして土を耕したのは農民だった。その多くは(強制避難地域以外で)避難しなかったお年寄りたちだった。…だから穫れた野菜を孫たちに食べさせても大丈夫なのかどうかは、耕すことをやめなかったお年寄りたちにとって、何より切実な関心事だった。…だから、測定して、農産物への放射能の移行がわずかに止まっていたという事実を知って誰よりも喜んだのは耕し続けたお年寄りたちだったのだ。そして一年を経た今、他所に避難していた家族が少しずつ戻り始め、お年寄りたちが作った農産物で家族の食事が作られ、食卓に和が少しずつ取り戻されつつあるようなのだ。
彼ら彼女らの耕すという行為が、深刻な放射能汚染という被害にもかかわらず、農作物には放射性セシウムがわずかしか移行していないという今の状態を、つくり、拓いた。私たちは今、福島の農が拓いた現在として、こうしたことをしっかりと受け止めるべきではないだろうか」。
脱原発・地域の再生は、土と作物の力を信じて耕し続ける農家の営みから始まる。 �
(農文協論説委員会)
▲目次へ戻る
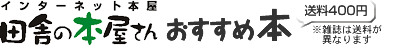
 |
この記事の掲載号
『現代農業 2012年6月号』
特集:農家が見る病害虫写真館
納豆&えひめAIで減農薬/酢・牛乳・重曹・水で減農薬/煙防除/天敵が住みつく畑をつくる/畑の除草剤 使い上手になる/苗箱施用殺虫剤どう使う? ほか。
[本を詳しく見る]
|
 |
『脱原発の大義』農文協編 地域を踏み台にした原発国家の形成と破綻 原発絶対体制の完成と崩壊/農山漁村の現場から 耕すことで農は復興への可能性を拓いた/未来へつなぐ 個人リスクと社会リスクを克服するために ほか
[本を詳しく見る]
|
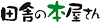
|

