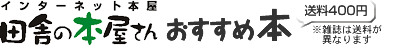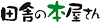農家に学び、地域とともに
農文協出版史で綴る農家力・地域力
目次
◆冷害、韓国米輸入、平成の大凶作のなかで
◆「直売所農家100万戸時代」の原点
◆「みんなでやる」農家の共同の方法・技術
◆庶民の“日常生活ブンガク”『日本の食生活全集』
◆「地域の再生」――地域に生きる一人ひとりが当事者に
編集を終えたいま、本書が描いた出版の歩みは、農家、地域の歩みそのものであると、改めて感じている。大震災・原発災害からの復興の原動力も、めまぐるしい変化のなかで守り、築いてきた農家力、地域力なのだと思う。
*
8月発行『農家に学び、地域とともに?農文協出版史で綴る農家力・地域力』の「まえがき」の一節である。
1940(昭和15)年に設立された農文協は2010年3月に70周年を迎え、これを機会に「出版史」を取りまとめることにした。「出版史」といっても「通史」的ではなく、テーマごとに、その時期時期に話題になり大きな影響力をもった作品を中心に記述。農家や地域の取り組みに学びながら進めてきた農文協の出版活動の歩みを、個々の作品をして語らしめるという方法をとることにした。
稲作・田んぼ活用に始まり、施肥改善・土つくり、減農薬・防除の工夫から女性の自給運動と直売所・地産地消、地元学による「地域の再生」など、20のテーマ(20章)で構成。農文協が農業の近代化路線批判・農家の自給の見直しを進めた1970年代(昭和45年)以降の40年間の作品に焦点をあてることにしたが、第1章の「稲作」一つとっても、それは激しく揺れ動く状況のなかで農家力を築いていく、うねりに満ちた歩みであった。
▲目次へ戻る
冷害、韓国米輸入、平成の大凶作のなかで
田植機が導入された昭和40年代は天候に恵まれ、米の在庫が増えて昭和45年には「減反政策」が開始された。しかし50年代に入り様相は一変、51年の冷害、そして55年は作況指数87(青森県47、岩手県60)の大冷害、その後も3年連続で「やや不良」が続いた。
この間、政府は一貫して米の過剰をアピールし続けたが、『現代農業』では編集部だけでなく、各地方支部の職員の力も総動員した米倉庫の調査から、「このままでは米が足りなくなる!」と訴え続けた。ひた隠しにしていた政府は昭和59年5月、電撃的に「韓国米輸入」を発表。これに対し『現代農業』8月号で緊急特集「主食の危機――何が起こっているか」を組んだ。一方では、密植の弊害が明らかになってきた田植え機稲作の改善技術を農家とともに追究し、スライド『安定イネつくりシリーズ』や単行本『あなたにもできるコメの増収』などを発行。井原豊さんの「への字イナ作」や疎植栽培、深水栽培など、農家の個性的な増収技術も花開き、農家を勇気づけた。
井原さんが『現代農業』に初めて登場したのは1980(昭和55)年9月号「平均年齢48歳の“4Hクラブ”」。「減反だ、米とるな」の政策に対して、「私ら中年のレジスタンス。米をたくさん穫るのは非国民だ、なんて言うのはパン食商工業民族であって、われわれと同じ民族ではない」と喝破した井原さん。ノーパンスケスケ稲、ゴリラのガッツポーズ稲…と、仲間との話合いから次々に新語を連発し、ついに「への字イナ作」という言葉が生まれた。「V字イナ作」に対し「への字」。もっとおおらかにイネを育てよう、イネの力を信じようとアピールした「への字イナ作」は、イネつくりのおもしろさを全国に広げていった。
そして、1993(平成5)年の「平成の大凶作」。米騒動が報道されるなか、農家は村を離れている親戚や友人・知人に、自家用米まで工面して米を送り、この経験は、農家による米の産直、直売へと向かった。消費者との直接的な関係づくりのなかで、イネつくりの自由な取り組みが広がり、不耕起稲作、アイガモ稲作、米ヌカ除草、菜の花稲作などの工夫も広がった。稲作だけでなく、土着菌利用、ボカシ肥、木酢などの自然農薬、混作・混植など「自分でやる・工夫する・捨てないで利用する・買わないでつくる・みんなでやる」農家の工夫は無限に広がり、農家力が花開いた。定年帰農などの新しい担い手も増え、「直売所農法」が多彩に展開されるようになった。
▲目次へ戻る
「直売所農家100万戸時代」の原点
この40年間で、最も大きな出来事を一つあげるとすれば、それは直売所の大きな広がりであろう。平成21年度の産地直売所調査結果(農水省)によれば、全国の産地直売所数は五年前より約3000増えて1万6816、コンビニ最大手のセブンイレブン店舗数1万3232を大幅に超えた。年間総販売金額は8767億円、一直売所当たり平均で5214万円。参加(登録)農家数は一直売所当たり平均で87戸、ダブリを無視して単純に掛け算すると全国で146万戸、「直売所農家100万戸時代」を迎えたのである。総従業者数は11万9000人で大きな雇用もつくりだしている。
これほどまでの広がりを予測した人は、どこにもいないだろう。そして直売所が単に有利に売る方法・売り場ということだけなら、これだけ裾野が広く元気にあふれる取り組みにはならなかっただろう。
直売所の原点は農家の自給にある。そして、直売所の直接的な推進力になったのは1980年代に各地で取り組まれるようになった農村女性による自給運動である。出版史では、その例として、秋田県仁賀保農協の生活指導員(当時)、渡辺広子さんが執筆した、1985(昭和60)年8月号「畑に出ない嫁っこたちから、畑大好きの嫁っこたちへ――共同畑の大きな波紋」を取り上げた。
仁賀保町には、カセットテープで有名なTDKの大工場があり、農家の若妻たちもご主人ともども勤めに出ていた。
「兼業でお金を稼ぎ、すべてを買うという生活の中では、健康、家族の和、農の心……が失われつつあった。
それではいけないと、農協が自給自足運動を呼びかけたのは昭和45年である。
金をとるよりも使わない工夫!
土を持つ農民こそ真の幸せを!
郷土の土から豊かな健康!
などを合言葉に「農家の自給自足運動」をすすめてきた。『共同畑』はその自給自足運動の一環として、昭和52年にはじまった。組合長(佐藤喜作)が、『勤めと家の仕事で忙しい主婦たちが、畑の中で井戸端会議ができるように』と婦人部に提案したのがきっかけである」
集落の嫁さん20人で始めたこの「共同畑」は、畑仕事の体験塾でもあった。
「嫁さんたちの共同畑には集落の姑さんも大喜び。『嫁っこがきて、3年も5年もたっても、畑サなんか一日もでたことねえ。こんなことで、オレたち畑仕事できなくなったらなんとするべ』と心配していた姑さんたち。さりとて『忙しい嫁っこつかまえて、畑サ連れていって一つ一つ教えるなんてとってもできなかったけど、共同畑でこうしてひととおりの仕事おぼえてきたら、自分でヒマみつけて畑サも行グようになった。ホント、エガッタモンダ』と」
嫁さんのほうも、「仲間といっしょに野菜つくりの技術を知り、心の交流ができ、なんといっても共同という絆が強く結ばれたことはすばらしいことと思っている」
「共同畑で収穫したメロン、スイカは、集落の集まりや盆踊りのとき、みんなに食べてもらう。青大豆のキナコもみんなで分けて、食べきれない分は農協の店で、地元特産として販売する」
農村女性の自給運動が原動力になって広がった直売所は、農家と地域住民・都市民との交流の場となり、さらには高齢者のための弁当づくりや学校給食、農村レストラン、子どもたちの加工体験など、地域の食とコミュニティの新たな拠点として展開していった。
▲目次へ戻る
「みんなでやる」農家の共同の方法・技術
直売所による新しい結びつきとともに、農家は村うちの共同も強めていった。進む高齢化や米価低迷・下落などの厳しい経営環境のなかで、「みんなでやる」農家力を発揮してきたのである。
共同の形の一つに「集落営農」がある。農文協の映像作品ではこの間、集落営農に力を入れてきたが、このさきがけとなったのが1990(平成2)年発行のスライド「水田農業確立シリーズ」第3集『水田営農編』である。この第1巻『集落営農を選んだ理由』では、事例の一つとして「一集落一農場」の協業経営に取り組む、富山県城端町(現南砺市)の「野口営農組合」を紹介。オール兼業集落で、「年配層には将来の安心を、若いひとには勤めを休まず農業ができる仕組みを」つくり出した経緯を追跡した。
2004年にはビデオ『ビジョンに魂を! JAいわて中央の集落ビジョンづくりと実践から』(企画JA全中)を発行した。生産調整推進のための奨励金(助成金)に代わる「産地づくり交付金」の交付要件として「地域水田農業ビジョン」の策定が求められるなかで、JA全中は農政と一線を画し、「現場実態に即した多様かつ幅広い担い手、地域が特定した担い手であるべき」だと主張し、この『ビジョンに魂を!』が生まれた。このビデオでは集落営農の促進にむけて集落単位の話し合いを徹底してすすめてきたJAいわて中央の取り組みを紹介したが、同JAの熊谷健一常務は作品のなかで、次のように語っている。
「このビジョンづくりには、ヒナ型はない。誰に採点されるものでもない。自分の集落、自分の地域に合った形で、農家の一番大事ないのちである農地をどうするか、みんなで話し合いをして、役割分担をしてやっていくのが基本であって、何も国や全中、農協に言われてやるんじゃない。やれる範囲でやればいい」
こうして集落営農は、「みんなでやる」農家の共同の方法・技術として多様に展開していくことになった。集落営農を大規模企業的経営への一里塚としてのみ位置づける見方を農家はしりぞけた。先月・9月号の農事組合法人・近江飯ファームのように、米や野菜をみんなで食べる「集落内自給構想」を立ち上げる集落営農も生まれている。
農業の近代化路線批判・自給の見直しにむけて設けた『現代農業』の「主張」欄の第2回目・1970年4月号は「新しい自給生活を創りだそう」であった。
「これからの自給は、昔とちがって、『買えば買えるがあえて買わない』というものです。やむを得ずやる自給ではなく、積極的な(生活を大切にするための)自給です。工夫をこらすのは生産性の向上ではなくて『人間性』の向上、つまり、いかにうまいものを食うか、という点でしょう」
そして「主張」は次のように述べている。
「もう一つ新しい自給生活のやり方がかくれていると思われます。それは、自給する農家同士が融通し合うという方法です。『自給農家連合』というべきものを作るのです」「農協が生活の問題を真剣に考えるなら、新しい自給生活――自給生活連合の事務局になってもらいたいものです」
「みんなでやる」のは生産だけでなく、出来たものを分かち合い楽しみ、地域の食文化を築いていくことも含まれる。
▲目次へ戻る
庶民の“日常生活ブンガク”『日本の食生活全集』
地域の食文化の継承にむけて1984(昭和59)年、農文協は『日本の食生活全集』(県別編成・全50巻)の刊行を開始した。地域の自然・農業と不可分一体の食の原型をなんとしても残さなければと考えたのである。全国各地で、当時のお年寄りが思い出すことができる昭和初期の食生活の様子を聞き取り調査し、料理を再現してもらって撮影し、記録する。膨大な作業が予想されたが、都道府県別編成として、各県に編集委員会を組織し、生活改良普及員など地域に密着した活動をしている方々に尽力していただくことにした。こうして、国家的事業ともいうべき、『日本の食生活全集』が誕生することになった。
各県版では、県をいくつかの地域に区分し、その地域のなかから特定の町村を選び、さらにそのなかの1戸の農家にしぼり込み、時間をかけてていねいに聞き取りし、これをもとに原稿がつくられた。個+個の総和や平均を全体とする「科学的」な手法ではなく、個が全体を表現している(個即全)という見方で、ある農家の全体像に迫り、描こうとしたのである。こうして、単なる記録でも、調査報告でも評論でもない、人間の暮らし方にせまる独自の味わいをもつ作品になった。作家の富岡多恵子氏はいみじくも、本書に「文学的感動を覚えた」と記している。
「…わたしが『岩手の食事』という本に文学的感動を覚えたのは、だから『民話』の世界に感動したのではなく、ヒトが『ものを食べて』生きる事実に感動したのである。これは、『食通』の書く文章によって味わったことのないものだった」(「ブンガク『岩手の食事』」――『表現の風景』収録、講談社)
「ヒトが“ものを食べて”生きる事実」の豊かな広がり。
その感動は、食べて生きる背後には農耕の世界が厳として在ることの確認でもある。
「ブンガク」といっても小説のような読み物というわけではない。石毛直道氏(国立民族学博物館・元館長)が述べているように、『食生活全集』は食生活研究の第一級の資料であり、地域おこしに役立つアイデア集であり、わが家のメニューを豊かにする郷土食の料理書でもある。『食生活全集』のブンガク性は、高く深い「実用性」をもつ。
『日本の食生活全集』は庶民の日常生活ブンガクであることによって、人々を記憶の共有へと誘い、人と人をつなげ、一人ひとりが主体になった住民自治を築く力となる。暮らしと地域を伝承し、新しい豊かさをつくる未来にむけた本――それが『日本の食生活全集』なのである。
▲目次へ戻る
「地域の再生」
――地域に生きる一人ひとりが当事者に
この40年間は「地域」という言葉が特別な思いを込めて語られるようになった時期でもある。
1970年代後半、高度経済成長がもたらした都市への人口集中と地方で進む過疎化、都市と地方の格差増大を背景に「地方の時代」、「地域主義」の主張が盛り上がりをみせた。そしてその後、直売所の広がりや農家の共同への取り組みのなかで、理念にとどまらず現実的・実践的な課題として、「地域の再生」、「地域の自立」にむけた取り組みが着実に進んだ。その一つの象徴に「ないものねだりではなく、あるもの探し」の「地元学」がある。
地元学の推進者の一人、結城登美雄氏はこう述べている。
「地域とはさまざまな思いや考え方、そして多様な生き方と喜怒哀楽を抱える人々の集まりである。しかし、誰もが心のどこかでわが暮らし、わが地域を良くしたいと思っているのに、その思いや考えを出し合う場がほとんど失われてしまっているのも地域の現実である。
地元学とは、そうした異なる人々の、それぞれの思いや考えを持ち寄る場をつくることを第一のテーマとする。理念の正当性を主張し、押し付けるのではなく、たとえわずらわしくとも、ぐずぐずとさまざまな人々と考え方に付き合うのである。暮らしの現場はいっきに変わることはない。ぐずぐずと変わっていくのである」
「私は近頃つくづくと思うのだが、自分でそれをやろうとしない人間が考えた計画や事業は、たとえそれがどれほどまことしやかで立派に見えても、暮らしの現場を説得することはできないのではないか」(シリーズ地域の再生(1)『地元学からの出発――この土地を生きた人びとの声に耳を傾ける』より)
この結城さんの指摘で思い起こすことがある。出版史でも紹介した、1971(昭和46)年発行『農業は農業である』の著者、守田志郎氏(当時名城大学教授)のことである。守田さんは『現代農業』を通じて、農家の「自給」とこれを支える「むら」の大切さを農家に語りかけた。
「部落というものが『にっぽん社会』の風船のひもが求めている錘〈おもり〉となりうる唯一の本源的な存在のようにさえ思えてくるのである。部落の外に出たあまり者達が、足りない知恵で部落をなんとかしようとする気配がしばしばみられる。(略)その知恵の足りなさが悲しいのだ」(『日本の村 小さい部落』より)
40年前の「自給」と「むら」の見直しは、地域に生きる一人ひとりが当事者となり、地域の様々な団体や業種を結び、都市民とも連携して地域をつくる地域力の形成へと展開していったのである。
*
農文協は、農家をはじめ無数の方々に支えられて、出版の歩みを続けることができた。今後とも、農家に学び、地域とともに歩み続けていこうと、気持を新たにしている。
(農文協論説委員会)
▲目次へ戻る
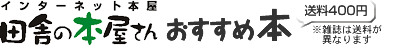
 |
この記事の掲載号
『現代農業 2011年10月号』
特集:土肥特集2011 液肥を自分で作る
高い有機液肥を手作り/パワー菌液/地域の有機物で堆肥栽培/うちの畑にも虫の糞/竹パウダー/最新・土壌病害克服法/産地の土の課題/北海道「省耕起」の今/イネ 元肥一発施肥/亜リン酸/塩害は乗り越えられる/放射能に負けない!/自慢のおやつ ほか。[本を詳しく見る]
|
 |
『農家に学び、地域とともに』農文協 編 出版史といっても「通史」的ではなく、テーマごとにその時期時期に話題になり、大きな影響力をもった作品を中心に記述し、農家や地域の取り組みに学びながら進めてきた農文協の出版活動の歩みを、個々の作品をして語らしめるという方法をとった。各テーマ・作品に関わってきた編集者が執筆し、さらに「普及から」ではその作品にまつわる普及の意気込みや苦労を普及職員が執筆、また単行本になった農家を中心に「農家列伝」のコーナーを設け、農文協の各支部での取り組みも紹介。結果として農家力、地域力を伝える異色の作品になった。
[本を詳しく見る]
|
 |
『今、引き継ぐ 農家の技術・暮らしの知恵 現代農業ベストセレクト集』農文協 編 怒りと決意の飯舘村/だれでもできる復興支援/むらとまち、地域と世界を結び直す/大震災を生き抜いて ほか。
[本を詳しく見る]
|
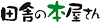
|