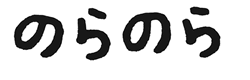 |
| 農文協 > 食農教育 > 2004年9月号 > |
|
|
食農教育 No.36 2004年9月号より
[特集]食育で校区が元気づく―高知からの発信―食育への提言
学校を核にしてコミュニティーの再構築を高知県教育長 大崎博澄さん
「食農教育」は広がりをイメージさせる
おおさき・ひろすみ
1945年吾川郡池川町生まれ。67年より高知県庁に勤務。著書に、『山畑の四季』(高知新聞社)『子どもという希望』(キリン館)など――今月号は、高知の食育、食農教育を特集しました。
大崎 まず、「食農教育」という言葉はとってもいいですね。食育ももちろん大事ですが、食育だけでは、なにか1つ足りない。自分たちが食べるものが生産されるプロセスを知ることにつながらないと、本当の食育にならないと思う。栄養のバランスとか、そういうものだけ学んでもいけないと思う。食べもののつくられ方、安全性、つくっておられる人のご苦労、さらに地域や地球の環境のこととか。そこまでの広がりをイメージさせるという意味で、この食農教育という言葉を考えついた人はすごい。いま、食育をすすめようという動きが広まっていますが、濃淡はあってもかまわないけど、「農」の部分を忘れないでほしいですね。
――教育長さんは農家のお生まれですか?
大崎 ぼくは池川町という、ものすごく険しい山岳地帯の出身です。町には、田んぼそのものの絶対量が少なく、ぼくの家には田んぼがありませんでした。でも、牛で田んぼを耕して、手植えして、っていうあの風景は見てましたね。見るのが好きでした。
それから、小さいころから母親といっしょに山の畑に行って、半分は遊んで半分手伝うというような感じでした。そんななかでサツマイモの植え方、世話の仕方、麦踏み、といった農作業は自然に覚えていきました。
――いまは、週末に山の畑を耕しているそうですね。
大崎 最初は町のなかの市民農園を借りていたけど、やっぱり雰囲気がどうも。理想のロケーションの畑をあっちこっち探したすえに、はじめて、あっ、ここがいいな、という感触を得た場所なんです。
車で1時間くらいかかりますが、小さい谷間に10枚くらい段々になっているうちの、1番上の畑。もともとは田んぼだったところです。日当たりもよくって北側が山で風もあんまり吹かなくて、近くに山桜が咲いてたり、ウグイスが鳴いてたり、谷川の音が下から聞こえたり。一目ぼれしました。
でも、残念ながら理想とはほど遠いんです。仕事のことで頭がいっぱい。農業に打ち込む心の余裕がこの4年くらいはないんです。いちおう、毎週30分でも1時間でも見には行ってますが、なかなか思うようにはいってない。
小さな農業をとおしてコミュニティーの復活を
ぼくは伝統的な農業に回帰したいと思っているんです。行政の農業政策は、いままで見てくれのいいものを合理的にたくさんつくってできるだけ高く売るという1点にしか目がいっていなかった。そんな競争は、たぶん「つかれる競争」だと思う。農家の方の健康にも悪いし食べる人の健康にも悪い。
でも、いまは価値観が大きく変わって、安全とか安心とかいうものが、評価される時代になってきた。そこに、伝統的な、小さな農業はもう1度生き残れる道があるんじゃないか、と思うんです。私の故郷のような小さな山の畑。あれはもう機械の入れようがないから、鍬でやるしかない。1つひとつていねいにつくったおいしい安全な作物こそが、いまいちばん価値がある作物じゃないかと思います。だんだんかしこい消費者が増えているから、ぜったい需要はある。形がきれいにそろってなくても、本当に安全でおいしいものを提供すれば、小さくても成り立つような農業経営があるんじゃないか、というのがぼくの持論なんです。そこから、どんどんすたれていっている高知の中山間地を、もういちどなんとか元気にしたい。
農業を中心にして、地域の産業が元気になったらコミュニティーが復活される。農業というのは、密接に隣近所が協力しないと成り立たない産業ですから。水の使い方にしても、農道の使い方にしても、みんな出役といって、いっしょに作業日を決めて草刈りをしたり、道の修理をしたりしてきた。そいうことが地域のつながりの復活につながると思います。
また、農業をベースにしたコミュニティーというのは、いちばん安定している。そうすると、教育がよくなると思う。あそこの子どもはどこで遊んでいても、ああ、あの顔してるのはどこの子や、というのが田舎ではわかるんです。名前は知らなくてもね。そうすると、危なかったら守ってやれるし、悪いことしたらしかってやれる。そういう状況ができたら教育のためにもすごくいい。だから、いまぼくがやっている教育の仕事と農業とは、非常に深いかかわりがあります。
食農教育というのは、子どもたちに安全でおいしいものを食べてもらう、その作物ができる由来をきちんと知ってもらう、それとともに、コミュニティーの復活にもつながるかもしれない。子どもたちが安全に安心して育つことのできる地域がもういっぺんできるかもしれない。そんな夢まで見せてくれるので、この言葉、非常に好きなんです。
子どもの教育とともに、健康な大人を育てたい
――農業をベースにしたコミュニティーは安定している、とはどういうことですか?
大崎 学者じゃないんでうまくいえないですが、たとえば食糧とか環境は地球的規模で非常に危機的な状態にある。でも、健全な農業が育っているような地域は、食糧の問題、環境の問題にしても、あるべきことを自信をもって世の中に示せると思う。われわれはこうやっている、ということが世の中に向かってきちっと発信できる、自信をもった大人たちが住める地域だと思う。そういう意味で安定している、という言い方もできるのではないでしょうか。
日本の国は、非常に不安定。エネルギーも食糧もいつストップするかもしれない。そうなると、たちまち崩れてしまうような社会ですよね。子どもたちをそういう社会で育てるのは、危ない賭け、綱渡りです。綱渡りでない社会で子どもたちを育ててやりたい。
コミュニティーを再構築するというのは、つまり健康な大人をつくることです。子どもの教育だけでなく、地域の食べものや環境と、自分の生き方とを、胸を張って発信できる大人を育てることが、すごく大事になっている。食農教育は、そこにもつながると思うんです。
それに、自分たちのための安定も大切ですが、農業や林業、漁業といった1次産業はそれだけで成り立っているわけではない。次の世代の環境や食糧の問題まで視野に入れたうえで、いまの自分たちの生産と生活がある。そういう社会を構築できたら、すごくいいと思います。
教育行政の究極・最終のテーマとは?
――農文協では、「校区コミュニティー」という言葉を使っていますが、小学校区ごとに、それぞれが元気な地域づくりをしていこうと提案しているんです。都会に行った人たちも、6年間通った小学校のことなら支援してくれる。核家族が進んだおかげで、お年寄りは自分の孫といっしょに畑に行きづらくなったかもしれませんが、近くの学校の頼みとあればどんどん孫たちに食農教育できますし。
大崎 「校区コミュニティー」ですか。これもいい言葉ですね。ぼくは、まったく同じ意味で、学校を核にしたコミュニティーの再構築ができないか、と言っています。これがもう、教育行政の究極の、最終のテーマですね。コミュニティーの再構築というのは言うべくして難しい。とくに1次産業で復活させるのは、ものすごく難しい側面がある。だから、学校を核にして、学校で地域の人が結びつく。そうすると農業をしていない方でも、勤め人の方でも、もういちど地域を振り返られるんじゃないか。それがいま、ぼくの最終目標になってるんです。
――1次産業でコミュニティーを復活させるのが難しい、というのはどういう意味でですか?
大崎 経済的な面で非常に難しい。それでも不可能ではないと思います。現にいろんな人が高知の田舎で農業をしながら、消費者と直接つながってがんばってます。ぼくも檮原町の人から野菜を買っています。これは応援になると思うんです。ほかと比べて高いか安いかわからないですけど、田舎で農業をがんばっている若くて元気な人を応援できると思ったら、安いと思うんですよね。そんな感じで直接消費者と生産者がつながりながら支援していくことで、1次産業の復活というのは、ある程度できるかもしれない。でも、決定的に仕上げることはなかなか難しい。
そのとき、もう1つの方法として、この学校を核にしたコミュニティーの再構築が大事だと思うんです。南国市の奈路という、ちょっと山間部の集落があるんですけど、そこがぼくの1つの理想ですね。小さな学校があって、周辺の人が学校と非常にいい関係を結んでいます。学校を一生懸命盛り立てようとしている。特認校といって、校区外から子どもを受け入れて、40人ほどの児童数のうち、10人くらいはよそからきている。まだ希望者があるけど、受け入れられないという状態です。非常に成功している。学校が元気だし、地域の人が「うちの孫と思って育てます」というふうなことをはっきり言うわけです。
――学校は、3年や5年で先生が移動してしまいますが、地域の人が運営の面まで入り込んでいくのは、教育にもコミュニティーづくりにも重要ですよね。
大崎 奈路なんかは、たぶん核になる先生が変わっても、もうあと戻りしない学校になっていると思いますね。地域のバックアップ体制が非常に強固になってますから。まさに校区コミュニティーができあがっているところだと思います。
タネまきから収穫までを、義務教育の期間中に
奈路のような例はまだ少ないと思いますが、食そのものの重要性についての認識は、かなり広がってきていると思います。食育をすすめる先生や地域の方にやっていただきたいことは、そこへもう1つ「農」をはめこむことです。「食」のバックグラウンドにある「農」をはめこむ。これをしっかりやっていきたいですね。
農業はやっぱり国のもとだと思う。通俗的な言葉ですが、農業が健全に行なわれて、健全な教育も成り立つものだと思う。タネをまいて作物が収穫できるまでを、子どもたちがきちんと義務教育の期間中に覚えることができる、というのが大切じゃないでしょうか。
地域あっての学校・学校あっての地域
南国市・奈路小学校区
県内初の小規模特認校
奈路小学校(北村初江校長)は、南国市北部の中山間地帯にある。奈路地区の10月に収穫される細身のタケノコ・四方竹は特産として有名であり、棚田で生産される米は南国市の学校給食米ともなっている。
奈路小学校に高知県ではじめて小規模特認校制度が導入されたのは平成12年のこと。ふつう児童が通学する学校は通学区域によって教育委員会の指定を受けるが、この制度は中山間の小規模校がもつ特色ある環境のなかで子どもに教育を受けさせたいと市内の保護者が希望する場合に、通学区域外でも認めようというものである。この年、奈路小には他学区から2名の児童が入学し、平成16年度には全校児童40名のうち他学区から通う児童が10名を占めるまでになっている。制度そのものは、南国市教育委員会(西森善郎教育長)の決断によるものだが、ここにいたるまでに地域と学校が築き上げてきた連携の実績なしにはこのような制度が導入されることはなかったという。
学校存続の危機に地域が立ち上がる
「1日じゅう学校のことが頭から離れない」と言う部落長の西内堅二さん(65歳、右)と副部落長の鮫島進さん(68歳) 奈路の人々が学校の将来のあり方に関心をもちはじめたのは、昭和の終わりころに校舎の増改築計画がもちあがったのがきっかけだった。このまま小学生の数が減っていったら、学校は統廃合して校舎は老人施設にでも転用すればいい、というような声も聞かれるなかで、地元の人々が「学校を100%残さなければ、地域の未来はない」と立ち上がったのである。実際平成2年には児童数が17名に減少し、奈路小は存続の危機に直面する。「地域あっての学校・学校あっての地域」は地域全体の合言葉になり、学校に子どもを通わせる家だけでなく、地域住民全体が学校にかかわるようになっていった。
いま奈路地区では「開かれた学校づくり推進委員会」(公民館運営審議会と表裏一体)が中心となって、春の運動会や三世代交流集会などの学校行事が地域行事として運営されている。総合的な学習の時間も推進委員会とPTA役員会と職員会の3つの場で協議しながらすすめられる。総合などで各学年で学んだことは「なろっこタイム」(全校集会)で全校児童に共有され、さらに三世代交流集会で地域に返される。こうしたなかで、地域からもさまざまな提案が生まれ、炭焼き体験学習のための窯づくり(平成9年)や北海道の支笏湖小との交流(平成10年から)など、活動の幅がひろがっていった。「子どもの育ちのもとは親」(北村校長)という共通の認識のもと、子どもと親、さらに地域の人が育て、育てられる関係ができているのである。
おやじの背を見て子も育つ
奈路名物「泥んこ球戯大会」の直後の泥田で行なわれる奈路小の運動会 このようなアイデアの源として、奈路のおじさんたちがつくる「AS奈路倶楽部」も大きな役割を果たしている。児童数の現象が著しかった平成4年結成。「子どもに何かをさせるのではなくて、大人が地域で勝手に楽しんでいる姿を見て、子どもが地域に誇りをもつ」(初代会長の川村一成さん談)がモットー。いま奈路といえば「泥んこ球戯大会」が有名だが、これをはじめたのもAS奈路倶楽部である。バレーボールが中心だが、相撲や菓子ひろいなど子どもの競技もある。午後には小学校の春の運動会も泥田で行なわれる。バレーボールには小学校の教員チームも参加、異動してきた先生にとっては地域に溶け込む蕫通過儀礼﨟のようなものである。田んぼからあがったら大人も子どもも消防ホースで水を浴び、ドラム缶の風呂に入る。そのあとの懇親会も楽しい。
このような学校と地域の楽しい交流のなかから、「田んぼの学校」のアイデアも生まれた。田植えの終わった田んぼの好きな場所を子どもたちめいめいが1m四方に囲って、プラカードを立ててオーナーになり、収穫した本数、粒数を計算する(「田んぼ1m2の教室」)、田んぼで泥んこ球戯大会・運動会をする(「1000m2の運動場」)、収穫した米でつくったおにぎりをもって、いちばん遠い上倉部落まで棚田のあぜ道をつたって子どもたちと歩く(「あぜ道5000mの通学路」)。子どもと大人がいっしょになった地域再発見のワークショップである。
「30年後、私たちがお年寄りと呼ばれるとき、そして子どもたちが私たちの年代になったとき『ああ、ここに住んで本当によかった』と思えるような奈路にしたい」(AS奈路白書より)という思いは、奈路の人々に共通するものであろう。

農文協 > 食農教育 > 2004年9月号 >
お問い合わせはrural@mail.ruralnet.or.jp まで
事務局:社団法人 農山漁村文化協会
〒107-8668 東京都港区赤坂7-6-12004 Rural Culture Association (c)
All Rights Reserved